NewsNewsみんなの障がいニュース
みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、
コラム形式でわかりやすくお届けします。
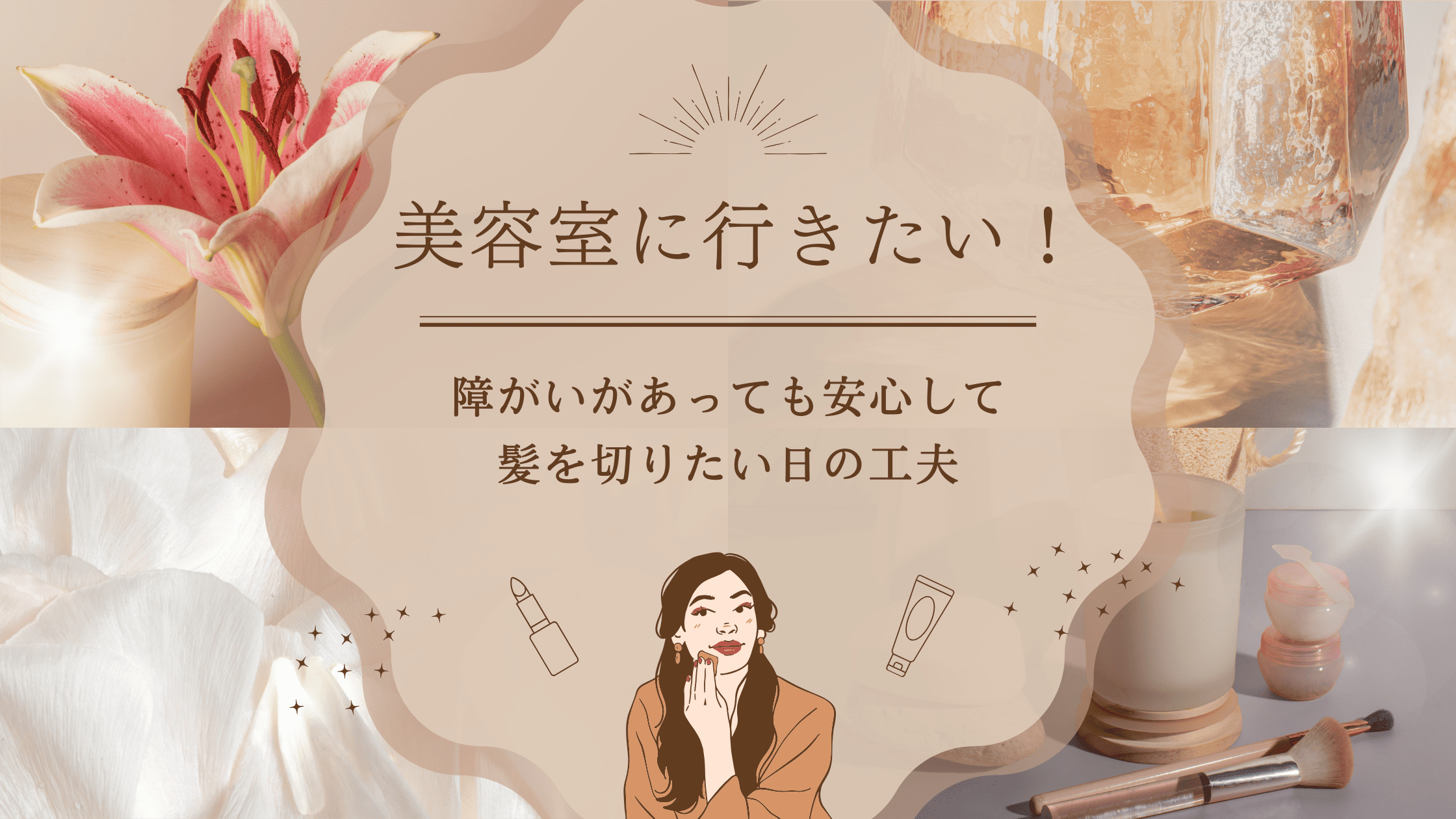
- 美容
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 感覚過敏
美容室が怖い!障がいがあっても安心して髪を切りたい日の工夫
「髪を切りたいけど、美容室が怖い」──そんな気持ちを抱いたことはありませんか?特に、身体障がいや発達障がい、感覚過敏などがある人にとって、美容室はハードルの高い場所になりがちです。
・車椅子で入れるか不安・カット中にじっと座っていられるか心配・シャンプーの水やドライヤーの音が苦手・美容師さんとの会話がストレスになる
こうした不安が重なると、「もう髪を切らなくてもいいか」と思ってしまう人も少なくありません。しかし、髪は日々伸びていきますし、身だしなみや気持ちを整えるためにも、定期的なヘアケアは大切です。
この記事では、障がいを持つ方が「美容室が怖い」と感じる理由を整理し、その不安を和らげる工夫や、安心して通える方法をまとめました。
美容室が怖いと感じる障害当事者のリアルな理由
車椅子ユーザーの不安
店内に段差があって入れないのでは?
シャンプー台に移乗できるか不安
トイレがバリアフリーでないと困る
発達障害や感覚過敏の人の不安
シャンプーの水しぶきが苦手
ドライヤーの大きな音がつらい
香料や薬剤のにおいに耐えられない
知らない人との長い会話がストレス
聴覚・視覚障害の人の不安
美容師との意思疎通が難しい
マスク越しの会話で口の動きが読めない
仕上がりイメージをどう伝えればいいかわからない
このように、「美容室が怖い」背景には、障がい特有の不安が重なっていることが多いのです。
安心して美容室に行くための工夫
1. 事前に情報を集める
バリアフリー対応美容室を探す「福祉美容」「バリアフリー美容室」と検索し、出てきた美容室に問い合わせたり、「Wheelog!」などでバリアフリー対応か確認する。
口コミを調べる「〇〇市 美容室 バリアフリー」などで検索すると、当事者の声が見つかることも。
支援者や仲間から情報をもらう当事者コミュニティやSNSで体験談を探す。
2. 美容師さんに配慮をお願いする
「大きな音が苦手なので、ドライヤーは弱風でお願いします」
「長時間座っていられないので、休憩を入れてください」
「会話が苦手なので、必要なことだけ伝えてほしいです」
事前に電話やLINEで相談しておくと安心です。
3. 自分で準備できる工夫
耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを持参(ドライヤーの音対策)
タオルや膝掛けを持参(感覚過敏の場合)
写真を見せてオーダー(言葉で伝えるのが難しい人におすすめ)
美容室が難しいときの代替手段
出張美容サービスを利用する
訪問美容は、障害や高齢の方が利用しやすいサービスです。参考リンク:Kami Bito
セルフカットや家族にお願いする
前髪だけセルフカット
家族にバリカンで整えてもらう
YouTube動画でセルフカットのやり方を学ぶ
https://youtu.be/0V9l3yIE-QA?si=t6fyM_uaY-p1ISrx
https://youtu.be/I_sp190csys?si=6bEh10l5maRO-YBO
まとめ
美容室が怖いと感じるのは、障がいを持つ方にとって自然なことです。大切なのは「行けないから無理」と諦めるのではなく、自分に合った工夫を取り入れること。
事前に情報を調べる
美容師さんに配慮をお願いする
出張美容やセルフカットを取り入れる
髪を整えることは、見た目のためだけでなく「心を整える時間」にもなります。自分らしい方法で、少しずつ「美容室の怖さ」を和らげていきましょう。
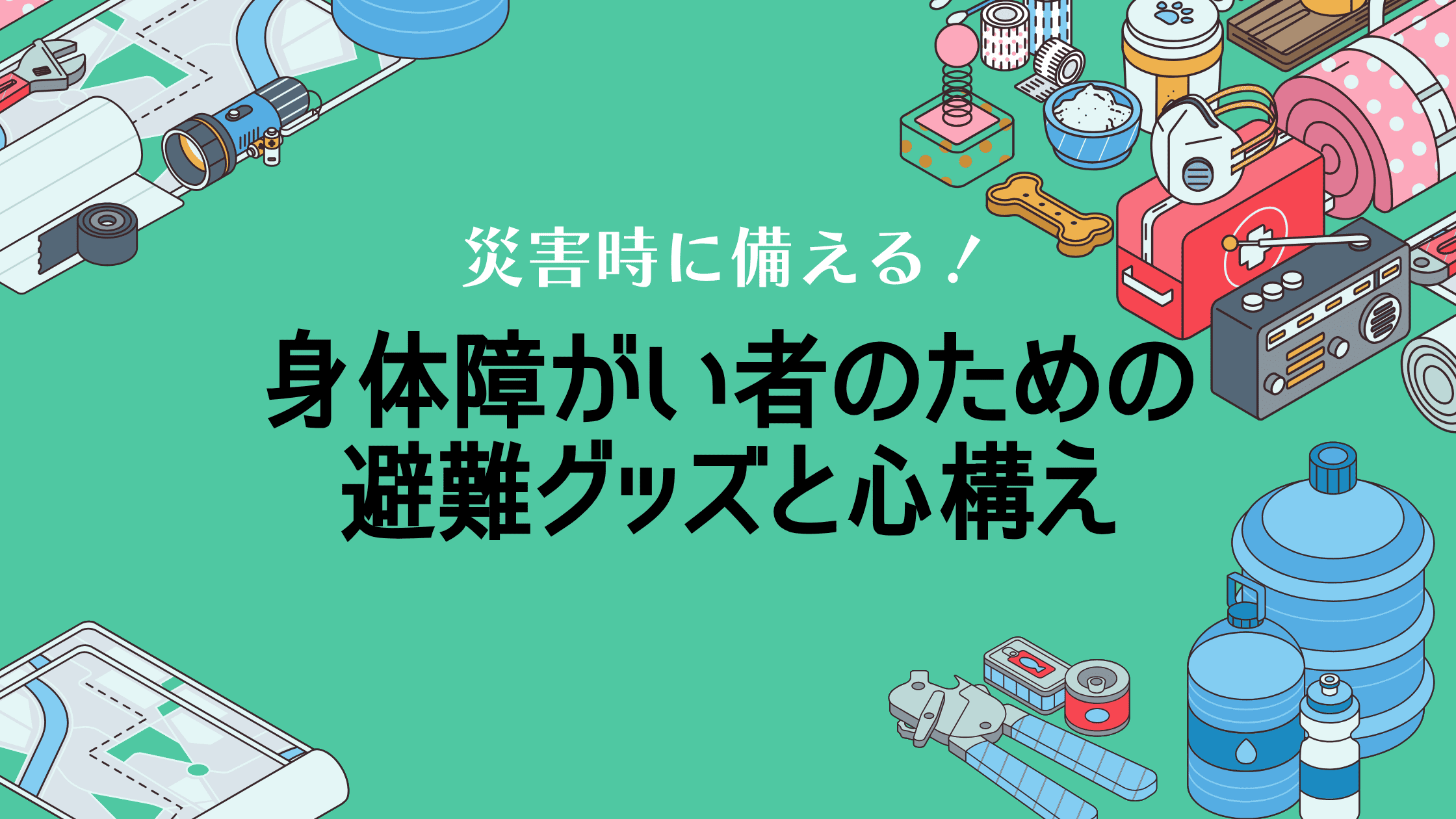
- 災害
- 情報
- 身体障がい
災害時に備える!身体障がい者のための避難グッズと心構え
はじめに:なぜ身体障がい者の備えが重要なのか
災害時には、多くの人が避難をする中で、身体に障がいがある人には特有の困難が生じることがあります。
車椅子、歩行補助具、日常的な介助や薬が必要な方々が、うまく避難できないケースも少なくありません。
自助・共助の視点を持ち、できる限りの準備を整えておくことが災害時の安心と安全につながります。
まず押さえておきたい基本情報
災害時に直面する課題とは?
身体に障がいがある人は、段差や狭い避難路、混雑した場面での移動が困難になります。
情報を得にくい場合もあり、また支援が得られにくい環境も課題です。
さらに、災害直後の安否確認や給水、避難環境への不安なども当事者の声として多く上がっています。
災害対策は日頃からの積み重ねが肝心
災害への備えは、いざというときに慌てないための「日常的な習慣」が重要です。
非常持ち出し袋の中身の見直し、避難経路の確認、避難場所の選定などを定期的に行いましょう。
障がい特性に応じた避難グッズ選びのコツ
車椅子や歩行困難のある方へ
車椅子のバッテリーや替えタイヤ、軽量レインコート、防寒用アルミブランケット、携帯しやすい非常食や飲料水も準備しておきましょう。
また、懐中電灯やモバイルバッテリーなどの電源確保グッズもあると安心です。
聴覚に頼らない通知手段を備える
災害放送やサイレンが聞こえない状況に備え、振動アラーム、光フラッシュ型通知器、災害用メッセージボードなどを用意しておくと安心です。
避難バッグ(非常持ち出し袋)の中身を見直す
一般的な非常持ち出し袋に加え、身体障がい者の方が必ず準備しておきたいアイテムをまとめました。
ヘルプカード:障がいの特性や医療情報、お願い事項を書いた補助カード
常用薬と予備の処方一覧:最低3日分、なるべく個別包装に
介護・排泄用品:紙おむつ、携帯トイレなど
補聴器用電池・白杖・補助具の予備部品など
筆談ボード・簡易ラベルカード:意思の伝達手段として
こうしたアイテムがあらかじめ整っていることで、避難所でも心と体の負担が軽減されます。
地域連携と共助の力を活かす
地元自治体の「福祉避難所」の情報を把握
災害時、通常の避難所とは異なる支援がある「福祉避難所」の設置場所や対応内容を把握しておきましょう。
ご近所同士の繋がりを日常から構築
緊急時に助け合えるのは、ご近所や日頃のコミュニティです。
「いつも通り」が乱れたとき、顔の見える関係が大きな力になります。
まとめ:自分に合った「備え」で自助と共助をつなぐ安心を
身体障がい者の災害備えは、自助と地域共助のバランスがカギになります。
“どこに何があるか”を整理し、必要なグッズを自分仕様にカスタマイズすることで、いざという時に自らと周囲を守る力になります。
「備え」があなたと周囲の安心をつくる第一歩です。毎日の備えを、少しずつでも進めていきましょう。
参考リンク
障がい者の防災対策~備え・もちもの・緊急時の対応~(実用的なチェックリスト付き)みんなの障がい
身体障がい者向け防災グッズ特集(移動や連絡に配慮したアイテム紹介)bowsai.net
聴覚に頼らない防災グッズ7選(音以外の情報手段を紹介)みんなの障がい
発達・知的障がい者の防災対策(感覚過敏やコミュニケーション配慮)bowsai.net
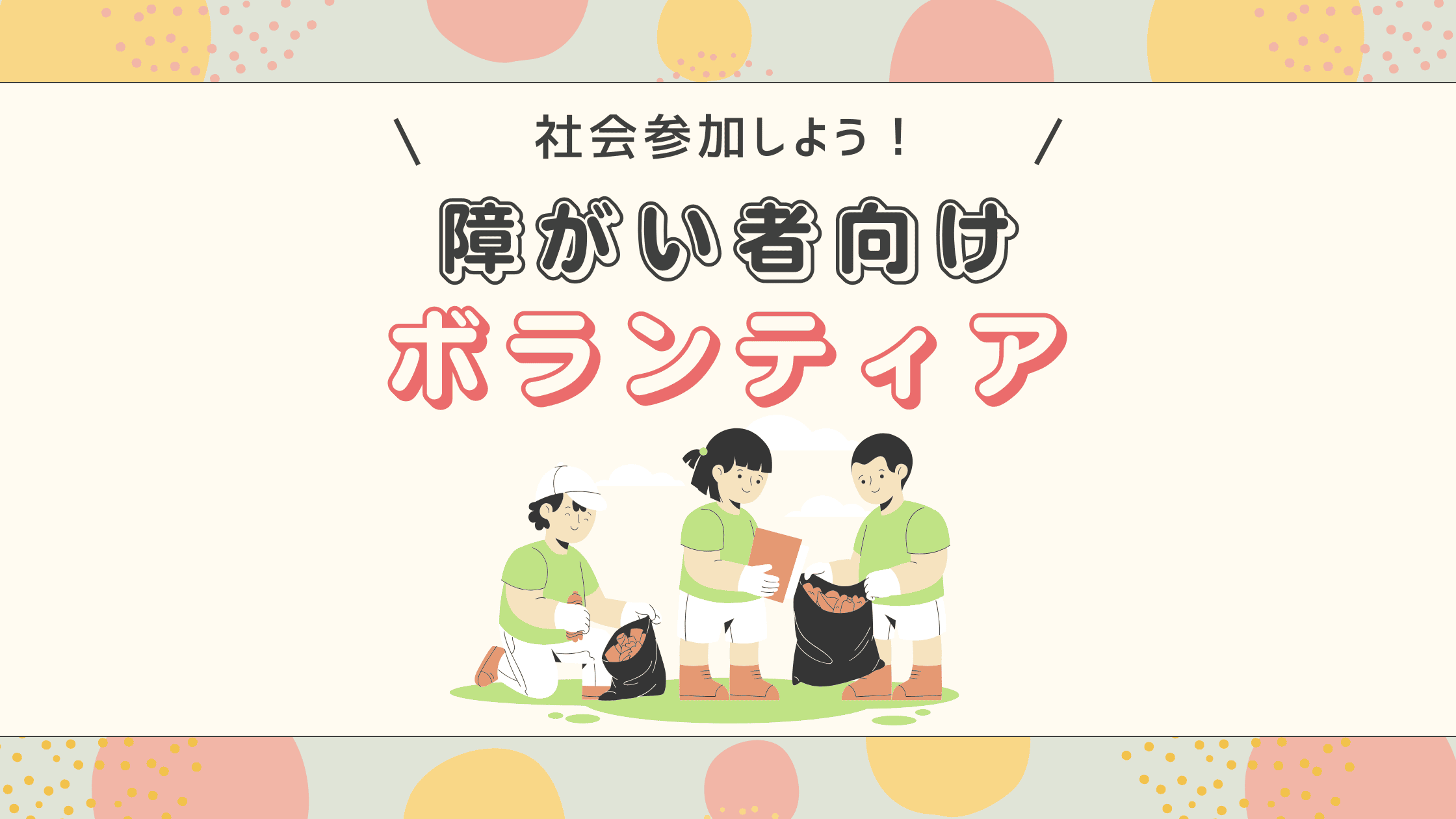
社会参加しよう!障がい者向けボランティア体験
はじめに:ボランティアがつくる参加とつながりの輪
障がいがあっても、人と関わり、役に立つ実感や社会参加の意義を得られる機会があります。ボランティア体験はそれを支える有効な手段です。
この記事では、障がいのある方々が経験できるボランティア活動やその効果、気軽に参加できる方法をまとめています。
ボランティアで広がる小さな共生の場
見えなくてもできる案内サポート(視覚障がい)
日本ライトハウスでは、視覚障がい者を対象にしたパートナー型ボランティアを募集しており、一緒に外出することで「移動の自由」を支援できます。
初心者でも研修があり安心して参加できる構造も魅力です。
参考リンク:社会福祉法人 日本ライトハウス
障がい者施設での日常サポート(知的障がい)
東京都府中市の府中ボランティアセンターでは、様々なボランティアを受け入れています。
手作業や外出同行などがあり、初心者やシニアの参加も可能です。
参考リンク:東京都府中市 社会福祉法人 社会福祉協議会
オリンピック・パラリンピックでのボランティア体験
視覚障がい者も大会ボランティアに
東京2020大会では視覚障がいを持つ方もField Cast(大会公式ボランティア)として活躍しました。
「大会の一員」として参加できた体験は、社会参加への自信とつながりを生みました。
共に支え合う体験が共生を育む
障がいのある人と一緒にチーム活動をすることで、互いのニーズや配慮を自然に学び合う環境をつくれます。
多様性とインクルージョンの実現を促進する貴重な場です。
ボランティア参加で得られるものとは?
自己肯定感・社会性が育てられる
参加を通じて役割を持ち、仲間と関わることで「自分も社会の一員である」と実感でき、自己肯定感が高まります。
社会参加支援の重要性にもつながる実例があります。
参考リンク:一般社団法人 エンジョイライフ
“できる”を実感する自己価値の再発見
「ありがとう」が返ってくる実感や、誰かの役に立てた感覚は、自分自身の価値や可能性を実感させてくれます。
小さな成功体験を積める場としても有効です。
参考リンク:障害を持つ方向け就職支援〜Salad〜|障害者がボランティア活動で得られるメリットは?
参加までの流れとポイント
まずは身近な施設に相談
気になる活動先の公式サイトや市の福祉窓口から、ボランティア募集情報を探してみましょう。見学や体験参加が可能な施設も多くあります。
無理せず自分のスタイルに合わせて
週1回だけ、1時間だけ、という方法でも参加可能な活動が増えています。まずは“無理のない関わり”から始めてみましょう。
安心して参加するために研修・交流機会を活用
施設によっては参加前に研修があり、必要な知識を得られます。参加者同士の交流もあり、新たなつながりとして広がる可能性があります。
まとめ:ボランティアでつくる小さな社会参加の輪
障がいがあっても「人と関わる」「役に立つ」という体験を通じて、自分の存在意義を感じることができます。
ボランティア活動は社会とのつながりを築く第一歩です。あなたらしいかかわり方で、ぜひ一歩を踏み出してみませんか?
凸凹村では月1回群馬県で募金ボランティア活動を行っています!
初めて参加の方にも楽しく気軽にご参加頂けるボランティア活動ですので、ぜひお気軽に参加してみてください✨

- ゲーム
初心者大歓迎!凸凹村 抽選券つきお楽しみゲーム大会 開催決定!
ぷよテト2で盛り上がろう!参加者全員に“抽選券”プレゼント!
障がいを持つ当事者が安心してつながれるコミュニティ「凸凹村(でこぼこむら)」では、2025年9月13日(土)に、初心者でも楽しめるオンラインゲーム大会を開催します!
今回のゲームは、直感的に遊べる人気ゲーム『ぷよぷよテトリス2(ぷよてと2)』パズルが苦手でも、みんなでわいわい楽しめます!
また、本大会はただのゲーム大会ではありません。なんと参加者全員に、ギフト券などが当たる「抽選券」をプレゼント! 抽選券は12月に開催予定の抽選会で利用可能。参加するほどチャンスが増える、継続型の「凸凹村お楽しみ企画」として実施していきます!
大会概要
タイトル:初心者歓迎!凸凹村 抽選券つきお楽しみゲーム大会開催日時:2025年9月13日(土)13:00スタート※Youtubeにて配信参加人数:最大20名(先着順)対象ゲーム:ぷよぷよテトリス2(Nintendo Switch版)参加費用:無料 ※凸凹村メンバー限定凸凹村に参加後、応募ページより応募ください凸凹村入村はこちら(10円から入村可能)参加特典:ギフト券などが当たる「抽選券」プレゼント応募方法:応募ページから事前申し込み(※受付締切:9月6日)受付締め切り後、大会専用Discordサーバーにご参加いただく予定です
こんな方におすすめ!
ゲームは好きだけど、対戦大会に出るのは初めて…
ゆるく楽しく参加できるイベントを探している
障がい当事者同士でつながりたい
プレゼントが当たる企画にワクワクする!
抽選券について
抽選券は凸凹村で不定期に開催される「プレゼント抽選会」で使用できます!(12月開催予定) ギフト券や限定グッズ、次回イベントの優先参加権など、今後も特典を拡充予定です。 大会に出るだけでもらえる“うれしいチャンス”をお見逃しなく!
今後の展開
このゲーム大会は今後も定期的に実施予定。(次回12月開催予定)回を重ねるごとに、異なるゲームタイトルやコラボイベントも企画中です。 「また出たい!」と思ってもらえるような、やさしく楽しい大会を目指します。
主催:凸凹村(でこぼこむら)
障がいのある方たちの居場所づくりと、情報交換・交流・課題解決の場の提供を目的としたオンラインコミュニティです。現在、村民募集中!
📩お問い合わせ
凸凹村運営事務局Mail:dekobokomurakoushiki@gmail.com公式サイト:https://dekobokomura.net
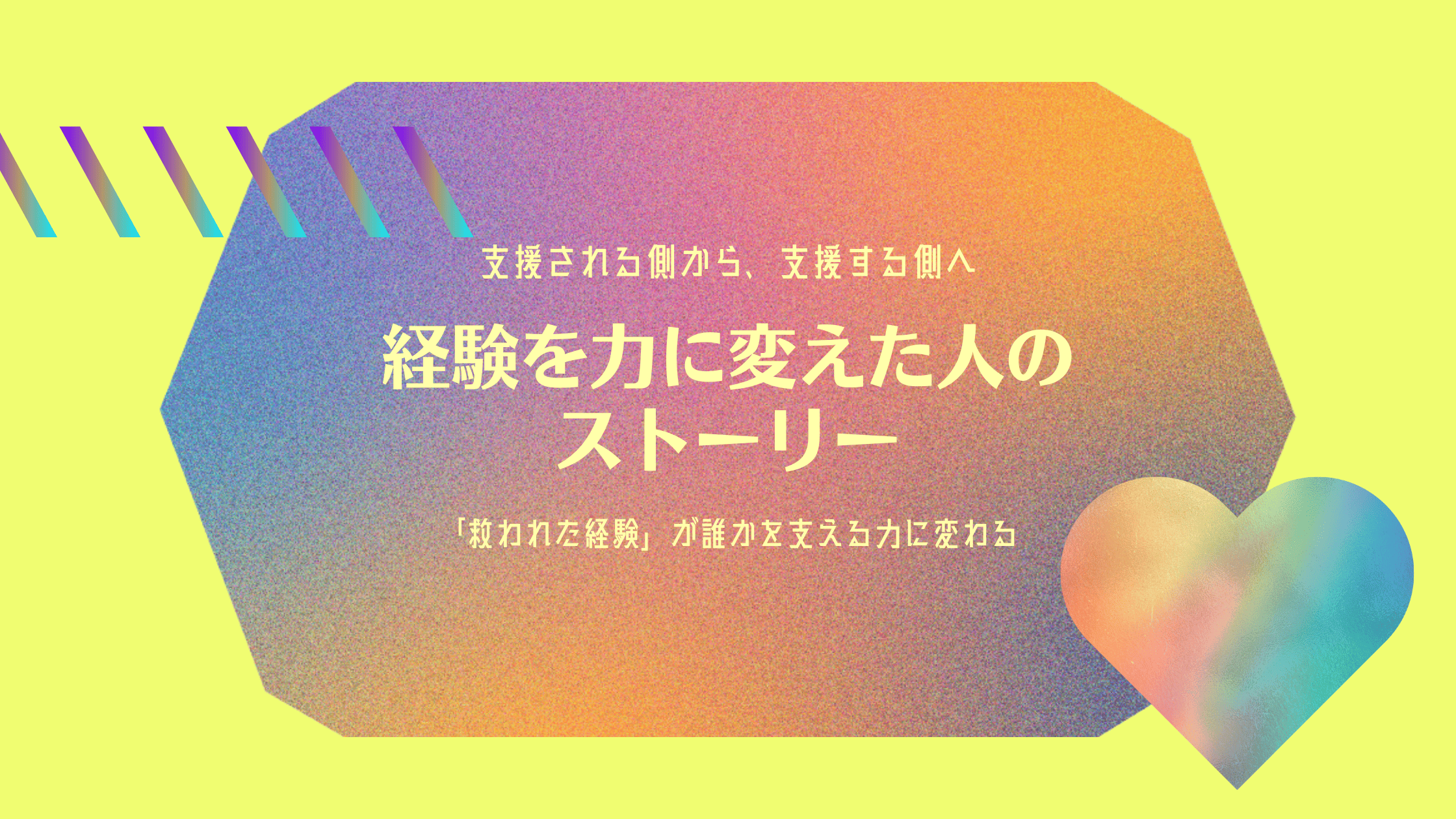
- 情報
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
- 仕事
支援される側から、支援する側へ。経験を力に変えた人のストーリー
はじめに:「救われた経験」が誰かを支える力に変わる
人生には支援を受ける時期もあれば、誰かを支える側に立つ時期もあります。
特に精神障害当事者や身体障害者などが「支援する側」へ転じる場合"同じ経験を乗り越えた人だからこそ伝えられる言葉"が、多くの人に力を与えます。
この記事では、当事者から支援者へ歩んだ具体的な事例や制度も含め、その力の構造を探ります。
当事者経験から支援者へ:成功事例に学ぶ
ピアスタッフとして就労し、支援を広げたケース
精神障害を抱えていたAさんは、就労継続支援B型を経てピアスタッフ職員として採用されました。
その後、当事者会の設立や電話相談センターの運営なども手掛け、経験を基にした支援活動を軸にしています。
参考リンク:堀合 研二郎 氏「精神障害を持つ本人として 同じ境遇の人の助けになりたい」
「ギルドケア」による支援活動スタート
「支援を受ける側」から一歩踏み出し、「保護ではなく機会を与える」を理念に活動するギルドケアでは、多くが元利用者。
社会で孤立しがちな境界知能や発達障害の人々に対して、機会を作ってきた実践が評価されています。
参考リンク:きっかけをつくるギルドケア
ピアサポート導入で支援の質向上
就労の場において、当事者経験を持つ支援者(ピアサポーター)の存在により、職場全体に“リカバリーの視点”が浸透し、偏見の減少や支援の質向上に繋がった事例もあります。
参考リンク:障害者職業総合センターNIVR
支援者としての葛藤と学び
当事者経験が諸刃の剣に
当事者だからこそ特有の共感や理解を提供できる一方で、同じ経験でも背景が異なることへの葛藤や、主観の押し付けを自覚するケースもあります。
支援者は、当事者としての経験を活かしながらも、自他の違いをわきまえる必要があるのです。
参考リンク:当事者が支援者になるということ
「内と外」からの理解が支援を深化させる
支援の現場では、定型者(非当事者)と当事者の双方が、「支援する側」「される側」として互いに意見を交わす機会が重要です。
「支援者が理解できない」ものであっても、話し合いを通じて歩み寄りが成されます。
参考リンク:発達支援交流サイト はつけんラボ
制度と仕組みで支援者を応援する仕組み
「ピアサポート体制加算」に見る制度的後押し
精神障害当事者が支援に携われる仕組みとして、障害福祉サービス報酬に「ピアサポート体制加算」が導入され、制度として当事者支援者の位置づけが強固に。
特に50代など同世代の支援者による就労支援も効果を上げています。
参考リンク:場面緘黙症とうつ病日記
リカバリーカレッジなど共に学ぶ教育の場
イギリス発のリカバリーカレッジは、支援者と利用者が対等な「学生」として共に学ぶ場。
当事者と支援者が共創しながら回復を目指す教育モデルは国内でも注目されています。
参考リンク:リカバリーとは医療現場でどのような意味を持つ?種類や支援の方法を解説(医師ジョブblog)
支援される喜びが支援する力に変わる瞬間
共感がもたらす安心とエンパワメント
当事者同士だからこそ生まれる「あなたの気持ちわかる」という理解は、安心感と自尊心を育てる。
そのプロセスそのものが、支援を“受け取る”を超えた共創となります。
参考リンク:当事者の関わり(ピアサポート)について
自分の物語を語ることの力
自身のリカバリーストーリーを話すことで、同じ悩みを抱える人に希望が届く。
語ること自体が“支援者になるプロセス”にもなり得ます。
こうした活動は「リカバリーのバトン」として次につながる力になるのです。
参考リンク:世田谷区ピアサポート活動ワーキンググループ
まとめ|支援される「経験」が、人を支える力になる社会へ
「支援される側」から「支援する側」へ。そこには、自分が受けたケアを次の誰かへつなぐ、強い意志とやさしさがあります。
社会において当事者の声や視点が活かされることで、支援はより豊かになり、相互理解と共生が進みます。
あなたのその一歩が、支援する力を育むきっかけになるかもしれません。
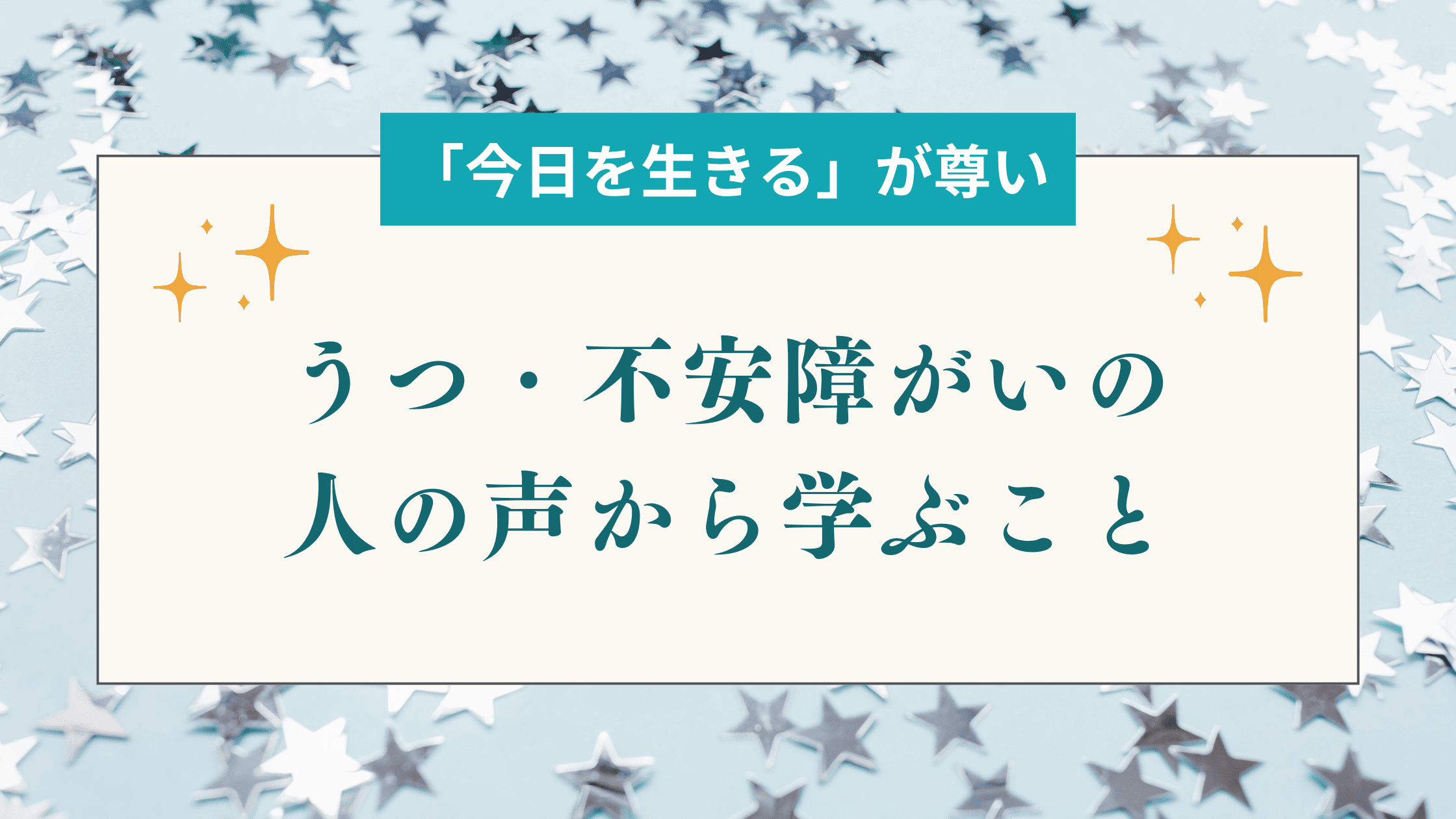
- 精神障がい
「今日を生きる」が尊い。うつ・不安障がいの人の声から学ぶこと
うつ病や不安障がいとともに生きる人々の日々には、他者にはわからない葛藤や苦しみがあります。
しかし、それでも「今日を生きる」「小さな希望に手を伸ばす」姿勢には、強さと尊さが宿っています。
本記事では、当事者の声を通じて、日常を支え、未来をつくるヒントを探ります。
当事者が語る“つらさ”と“それでも生きている理由”
統合失調症と長年付き合うMさんの体験
精神障害を抱えながら、就労を経て「自分の人生を生きたい」と決意したMさんの人生軌跡は、多くの困難を乗り越えた上での「今」を見つめる姿が印象的です。
病気からの孤独を乗り越える中で、「自分の人生の責任は自分にある」と気づけたと語っています。
参考リンク:「自分の人生を、自分の責任で生きることが大事」 ~就労を目指してきたMさんの体験談から学ぶこと~ Media116
うつ病と不安のなかで見つけた“居場所”
ある方は、10年にわたる統合失調症との闘病生活を通じて、自己への探求や表現の手段を見出しました。
「うつ」を通じて得たものもあると語り、苦難を越えることで得た内面の強さが書かれています。
参考リンク:「闘病生活から見つけた私の居場所そして生きがい」 すまいるナビゲーター
「書く」「創作する」ことが救いに
「うつ」や不安に直面しながら、SNSやレビュー・アクセサリー創作を通して自己表現を続ける方もいます。
「自分の素直な気持ちを出す」ことで、生きづらさの中から自己肯定感を育んだ実感が語られています。
参考リンク:過剰に不安を感じる「不安障害」。休職して気づいたのは、どんな気持ちも受け入れる大切さ soar
具体的な“日常の工夫”と回復のヒント
ゆっくりで構わない:ペースを自分に戻す
うつの方の声には「無理をしない」「嫌なことはやらない」「好きなことをする」など、自分の気持ちに正直になることで少しずつ楽になる思考の変化が見られます。
支えを得る勇気を持つ:専門家・相談者が重要
多くの当事者が、「専門機関に相談することが救いになった」と語っています。
「病院選びは合うかどうか試してみる」「早めの受診」が転機になることもあります。
参考リンク:北九州市 いのちとこころの情報サイト
声かけ・関わり方が心を軽くする
うつ病の人に対して、「無理しないでいいよ」「休もうか」「話したいときいつでも聞くよ」といった受容的で肯定的な声かけが、安心感につながるとされています。
参考リンク:ひだまりこころクリニック
日々の「小さな一歩」が生む自己価値の回復
日記・記録・創作で自己との対話を
文章や作品を通じて「今の気持ち」を外に出すことで、感情と向き合う余裕が生まれます。
当事者の中には、ウェブ発信・創作で居場所を見つけ、生きる意味を得ている人もいます。
参考リンク:みんなのうつ病体験記
安心できる合間をつくる(休息の習慣)
体調が悪い日は無理せず、「今日は休む」と自分に許可を与えることが大切です。
休息によって回復力を保ち、別の日に少しずつ前へ進む体力をつくります。
小さな成功と報酬を組み込む日々設計
調子の良い日には、好きな食事を作る・外を散歩する・誰かにメッセージを送る…など、小さな行動を“成功体験”と捉える習慣が、自己肯定感を育てるきっかけになります。
回復を支える周囲の関わり方と制度支援
聞き手に徹する姿勢が信頼を生む
話を遮らず、相手の気持ちを受け止める「傾聴」が大きな支えになります。
「否定せず共感する」ことが回復の支援に繋がります。
支援制度・相談窓口の利用をためらわない
一人で抱えこんでしまうと、ますます閉じこもってしまいがちです。
精神保健福祉センターや障害者支援団体、生涯教育センターなど、まずは相談窓口へ連絡することが大切です。
参考リンク:こころの耳 社会不安障害(SAD)体験記
社会制度との連携で「生活の安定」を図る
就労支援や障害手帳、作業所利用、補助制度など、自分に合った制度を活用することで、経済的・生活的な安心をつくることができます。
まとめ:「今日を生きる」は、小さな奇跡の連続
うつ病や不安障がいと向き合うことは決して容易ではありません。ただ、その中にある“今日を生き抜く力”“小さな希望を信じる心”には、強い美しさがあります。
当事者の声を通して知るのは、苦しみだけでなく、そこから見える「生きる尊さ」です。
無理せず、ゆっくりと、自分のペースで。誰かに頼り、誰かとつながりながら、今日という日を尊く、できる限り温かく生きていきましょう。
関連リンク・参考動画
「統合失調症と共に生きることについて」(当事者の実話体験談)障害者ドットコム
「同じこと、違うこと 精神障がい『症状と生活を知る』」講座用映像(統合失調症の暮らしに寄り添う内容)
https://youtu.be/5dZSiVL9MmM?si=bgtWu4QpU5NoTE9N
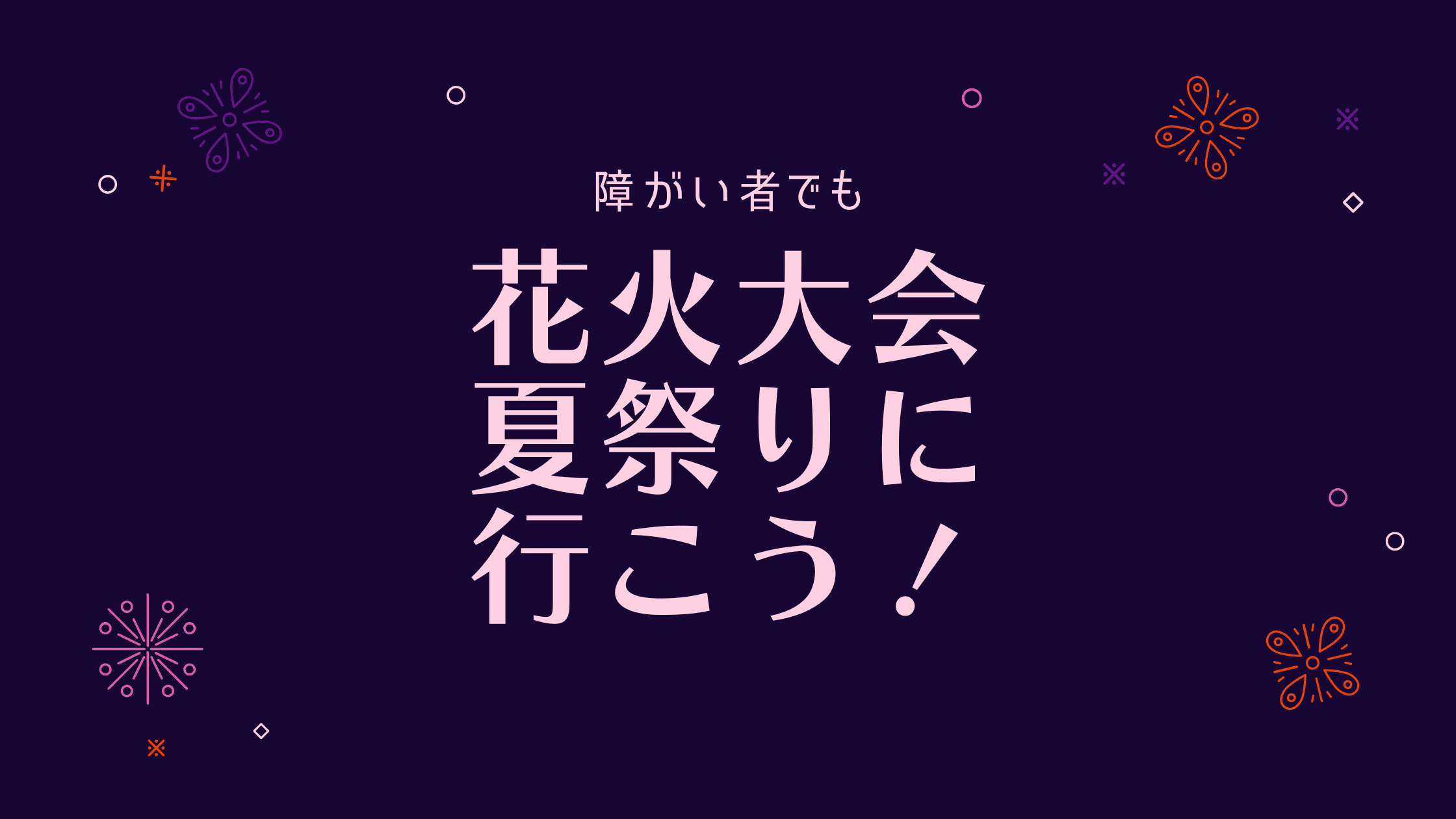
- 夏
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 感覚過敏
障がい者でも花火大会・夏祭りに行きたい!
毎年夏になると、全国で花火大会や夏祭りが開催されます。しかし、障がいや感覚過敏などの特性を持つ人にとっては、「行ってみたいけど不安」という声も少なくありません。
そこで本記事では、障がいの種類別に「どんな配慮があると安心して楽しめるか」「おすすめの準備・サービス」などを紹介します。
車いすや歩行困難な方が安心して参加するために
バリアフリー観覧エリアの選び方
会場によっては車椅子専用スペースが設けられており、案内誘導のあるところもあります。
たとえば都内では車椅子優先レーンや多目的トイレ完備の例も多く、事前に主催者や公式パンフレットで確認することが大切です。
旅行ツアーで安心プラン
障がいのある方向けに添乗員付きで負担軽減した旅行ツアーも増えています。
熱海や高山など温泉地で花火を観覧するプランでは、車椅子席・移動サポートが整っており安心です。
視覚障がい・聴覚障がいのある方が楽しむ工夫
花火×音楽×朗読劇の融合
「みんなの花火」プロジェクトでは、障がい者アーティストの歌や手話通訳、点字パンフレットや花火朗読劇など、視聴覚に障がいがある方でも楽しめる演出を提供しています。
参考リンク:PR TIMES
音と振動で楽しむ工夫
大曲の花火では、振動型デバイス(例:Hapbeat)や難聴者用スピーカーを活用した実験的な取り組みがあり、映像に頼らず五感で楽しむ仕組みが試されました。
参考リンク:PR TIMES
精神障がいや自閉症スペクトラムのある方が楽しむ工夫
混雑や音が苦手な方向けに
多くの花火会場では、早めに到着して静かな鑑賞スペースを確保する工夫が重要です。
川原など混雑しやすい場所を避けるのが安心です。
休憩できる場所と時間を確保
会場周辺に座って過ごせるスペース、公園の芝生、休憩所などを確認しておきましょう。
予備の飲料や耳栓・アイマスクなども準備することが役立ちます。
ゆったり楽しめる場所選び
観客の少ない穴場スポットや混雑が緩やかな小規模イベントを選ぶことで、過度な刺激を避けつつ楽しめます。
感覚過敏がある人が楽しむ工夫
音・光・においの刺激に注意
感覚過敏のある方は、「音」「光」「におい」などの強い刺激に苦しむことがあります。とくに花火大会では、・爆音(音の刺激)・光のフラッシュ(視覚刺激)・人混みと屋台のにおい(嗅覚刺激)が大きな負担になることも。
対策アイテムを活用しよう
・ノイズキャンセリングイヤホンやイヤーマフ・サングラス・マスク
これらのアイテムで刺激を軽減できます。事前に会場の動画で雰囲気を確認して、無理のない参加を心がけましょう。
参考リンク:精神科看護特化型訪問看護ステーション
家族や友人と一緒に楽しむためのポイント
情報収集は早めに
障がいを持つ方が同行する場合、事前に車椅子スペースの人数やバリアフリー案内有無を確認することを推奨します。
ツアー・イベントを活用する
観覧席確保や介助体制の整備された添乗員同行の夏祭り・花火イベントを利用すれば安心して参加できます。
アクセシビリティへの対応事例
障がい者対応ツアーでは、歩行補助車両、貸出車椅子、障がい対応トイレなど、ハードとソフトの両面から配慮が提供され、参加者に好評です。
参照リンク:心の翼バリアフリーツアー
行きたい!参加したい!おすすめ花火大会・夏祭り事例
立川まつり国営昭和記念公園花火大会(東京)
5000発の打ち上げとともに、身体障がい者用駐車場、多目的トイレ(39か所)など、設備面が充実しています。
混雑緩和のため事前来場が推奨されています。
隅田川花火大会(東京)
東京最大級の人気大会ですが、公式パンフレットに車椅子優先エリアや案内情報が記載されています。
早めのルート確認が安心です。
大曲の花火 秋の章(秋田)
「障がい者も楽しめる花火」として、視覚・聴覚障がい者向けの朗読劇や振動体験を試行。
特別な配慮のある芸術体験として注目されています。
安全・快適に楽しむための事前準備ガイド
混雑時間を避けて訪れる計画を
入場ピークや終了直前は混雑が最大になりますので、早めの移動・場所確保が鍵です。
帰り道の安全確保も考慮しましょう。
支援機器・用品の持参と使い方
車椅子用の簡易チェア、歩行補助杖、耳栓やアイマスク、予備の飲料・医薬品など、緊急時にも対応できる準備が望まれます。
周囲と連携する安心感
当日現地の係員やボランティアに早めに声をかけておくと、案内や配慮につながります。
受付やインフォメーションセンターの利用も有効です。
まとめ:すべての人が夏の魔法を楽しめるように
障がいがあっても、花火大会や夏祭りの楽しみはあきらめる必要はありません。
事前準備・情報確認・配慮された観覧環境を整えることで、安心して参加できる場が増えています。
あなたや家族、友人が同じ夏の風景を共有できるよう、ぜひ参考にしてみてください。

- アプリ
- スマホ
- 情報
障がい別おすすめスマホアプリ
はじめに:現代のスマホが支援ツールになる時代
スマホアプリは、様々な障がいを持つ方の生活を支える強力な味方です。
視覚・聴覚・コミュニケーション・移動などの困りごとを、スマホひとつで軽減できるアプリが増えています。
ここでは、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、発達障がいなど、障がい別に厳選したアプリをご紹介。実際に使える日本のサービスを中心に、特徴・使い方・導入のヒントをわかりやすくまとめます。
視覚障がいにおすすめのアプリ
Seeing AI|Microsoftが提供する全視覚支援アプリ
「Seeing AI」はスマホのカメラで対象物を撮影すると、文字・人物・物体・色彩・表情などを音声で説明してくれます。日本語対応もしており、印刷物やバーコードを読み取りながらの買い物、知らない人への案内確認など、生活の様々な場面で活用できます。
参考リンク:ケータイWatch
Eye Navi|日本発の歩行支援アプリ
東京都立大学と共同開発した「Eye Navi」は、歩行中の障害物や信号、点字ブロックなどをリアルタイムで音声案内します。
道案内機能に加えて、障害物検出や地図ロギングまで備えており、外出時の安心感を高めます。
参考リンク:視覚障がい者歩行支援アプリ Eye Navi アイナビ
聴覚障がいに役立つアプリ
UDトーク|リアルタイム音声→字幕表示
聴覚障がい者との会話や講演などを、音声を認識して即座に字幕表示できるアプリ。
多言語字幕も可能なので、訪日外国人との交流にも便利です。
対応端末の複数共有や音声翻訳機能もあり、コミュニケーションの幅が広がります。
参考リンク:UDトーク
こえとら|会話を支援する文字と音声の変換
「こえとら」は、音声を文字に変換したり、文字を音声で読み上げたりできるコミュニケーション支援アプリ。
健聴者との対話を支援し、対面でもスムーズなやり取りが可能です。
無償提供・iOS/Android両対応なのも嬉しい点です。
参考リンク:こえとら
肢体不自由や移動の支援アプリ
ミライロID|障害者手帳をスマホで提示
全国4,000以上の施設で使えるデジタル障害者手帳アプリ。
手帳の携帯・提示が不要になり、電子クーポンの提供や割引案内などのライフサポート機能も備えています。
参考リンク:みらいID
WheeLog!|車いす利用者のためのバリアフリーマップ
車いすユーザーが投稿するバリアフリー施設のレビューやルート情報が地図上で共有できます。投稿されたルート情報は緯度・経度や傾斜なども記録されており、事前に移動計画を立てるのにも役立ちます。
参考リンク:WheeLog!
GPSナビ(GoogleMapなど)|視覚障がいや車いすユーザー向け
オープンソースの地図データを使い、音声による屋内外のナビゲーションを提供するGoogleMapのようなアプリは、駅や商業施設での移動をサポートします。
参考リンク:GoogleMap
発達障がいやコミュニケーション支援
ヘルスチェッカー
発達障がいや精神の体調を記録・管理できるアプリです。
気分や体調の変化をグラフ化し、医療機関や支援者とも共有できる点が特徴で、自己理解と支援連携の土台をつくります。
参考リンク:アスピック
Voice4u
言葉の代わりに「アイコンや絵カード」を選択することで、テキストや音声で伝えられるコミュニケーションアプリ。
思考を伝える手段として、自発的な意思表示が可能になるサポートツールです。
参考リンク:Voice4u
汎用支援アプリ&最新アクセシビリティ機能
Voice Access|声だけでAndroid操作
Googleが提供する音声操作アプリで、スマホ操作を言葉だけで完結できる支援ツール。
手が不自由な方や発語を使いたくない場面でも電話や検索などが可能です。
参考リンク:Voice Access
Be My Eyes/Be My AI|視覚支援のグローバルボランティアアプリ
世界中の視覚障がい者が体験をシェアできるコミュニティ型アプリ。
ライブ映像でボランティアに物を見せたり、AIが説明してくれたりと、多彩な支援が可能です。日本国内でも利用者が増えています。
参考リンク:Be My Eyes
利用時のチェックポイント
自分の障がい・目的に応じたアプリを選ぶ
それぞれの障がいに合うアプリが多数あります。
まずは自分の困りごとや周囲のサポート環境を検討し、それに合ったものを選びましょう。
プライバシー・セキュリティに配慮
位置情報や個人情報を扱うアプリが多いため、利用前にはプライバシーポリシーを確認し、安全性を確保してから活用してください。
日常生活の一部として気軽に使う
すべてを一度に導入するより、ひとつずつ試して生活の一部にすることで、より継続的な利用が期待できます。
困りごとを軽減しながら、新しい生活の可能性を広げていきましょう。
まとめ:スマホアプリがもたらす「自由で安心な日常」
障がいに関する困りごとを、スマホアプリが解消してくれる時代になりました。視覚障がい、聴覚障がい、発話・移動・発達など、それぞれに適した支援ツールを活用することで、日常の自由度がグッと上がります。まずは自分に合うアプリを探し、気軽に使ってみることから始めましょう。あなたの生活がもっと快適に、もっと自由になりますように。
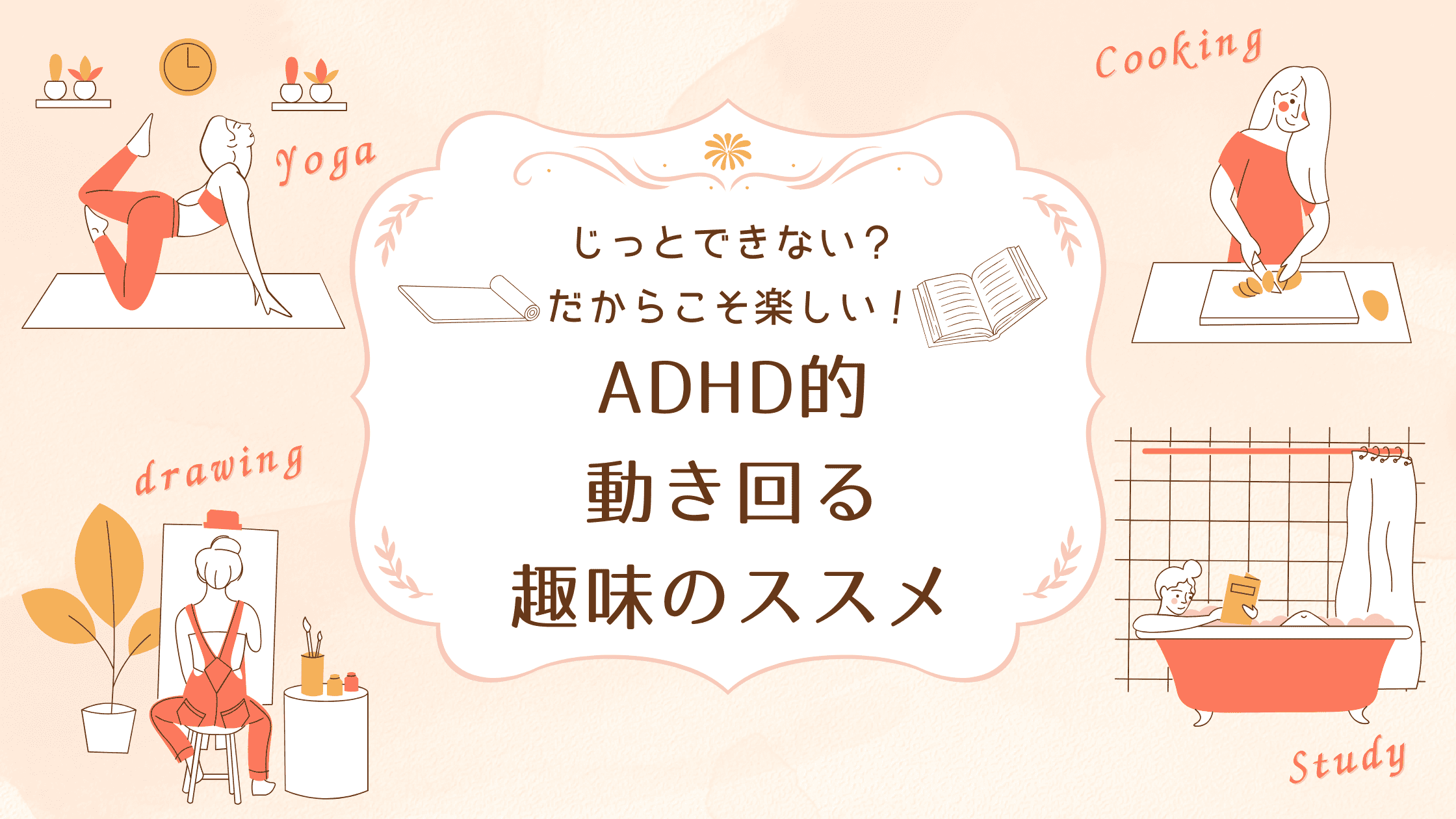
- 趣味
- 発達障がい
じっとできない?だからこそ楽しい!ADHD的・動き回る趣味のススメ
はじめに:ADHD(多動)の「じっとできない」は才能の源泉
ADHD、特に多動の症状が強い人は、静かに座っているよりも体を動かしてこそ集中力が高まることがあります。エネルギッシュに動く趣味を取り入れることで、毎日がより豊かに、心地よく変化します。当事者やその家族・支援者にとっても役立つ内容です。
動きが鍵!身体を動かすアクティブ趣味
有酸素運動で心と体に刺激を
ランニングやサイクリング、ダンスなど、リズムと運動を組み合わせた趣味は、集中力を高め、不安感を減らすのに効果的です。
特に身体を使う活動は感情のコントロールにもつながるとされています。
格闘技・ボルダリングで心を整える
ボクシングや柔術、ボルダリングなど反復動作と挑戦要素のある体験は、ADHD傾向の脳に適した刺激が与えられ、集中力や達成感が得られます。
水中やヨガで心地よく動く
水泳のような浮力のある運動や、ヨガ・ストレッチで体を軽く動かす習慣は、緩やかな身体活動と心の安定を叶えてくれます。
創造と動きを融合するハイブリッド趣味
音楽・ダンスで五感をフルに刺激
楽器演奏やダンスは、身体とリズム、音楽を連動させる刺激が豊富で、感情表現や集中力にもプラスになります。
DIYや手作業で集中と気分転換を両立
木工や陶芸、手芸といった創作活動は、手と身体の感触で集中状態を作りやすく、達成感を感じやすい趣味です。
料理やガーデニングで体と意欲が動く
料理では食材を切ったり混ぜたりする動的な工程があり、ガーデニングも土いじりや世話の行動で身体が自然に動くため、心身のバランスを整える趣味として優れています。
ADHD脳に効く「動き」の科学的背景
刺激が必要なADHD脳の特徴
ADHDの方はドーパミン系の働きが弱いため、「刺激」が必要で、単調な状況では集中が続きづらい傾向があります。
有酸素運動や変化のある行動は、その不足を自然に補ってくれます。
揺れや動作が集中を補助する
「フィジェッティング」と呼ばれる小さな動き—例えば、脚を揺らす、指を動かす—が、注意を高める補助行動として有効であるとされています。
フィジェットトイというADHDのサポートアイテムもあるので、参考にしてみましょう!
https://www.youtube.com/watch?v=vxw8BVoPygo
始める前に押さえたいヒントとコツ
自分に合うスタイルを探す
反復リズムに安定を感じるタイプもいれば、変化あるアクションの方が楽しいタイプもいます。まずは日常の中で無理なく続けやすいものから始めることが大切です。
小さな成功体験を積み重ねる
掃除、ストレッチ、短いウォーキングなど「できた」を日々感じられる活動を積み上げることで、習慣化しやすくなります。
周囲との協力が継続に力をくれる
家族や仲間と一緒に楽しむことで、励まし合いながら継続する意欲が生まれます。共有できる趣味ほど続けやすいです。
まとめ:じっとできないあなたこそ、動いてこそ輝く
「じっとできない」はADHDの多動の特性。ただそれをマイナスとせず、動きながら集中し、楽しむ習慣を持つことで、集中力や創造力、自己肯定感を伸ばせます。
あなたのリズムで動く楽しさを、ぜひ取り入れてみてください。
参考リンク・参考動画
ADHDの子どもにおすすめの習い事|選び方や続けるコツを解説メガジュン
ADHDの人におすすめの趣味や習慣(note)
低予算!ADHD向けのんびり趣味8選(note)
https://youtu.be/gZm6mNzb6GM?si=ILCo-UDx3_p1CmkF
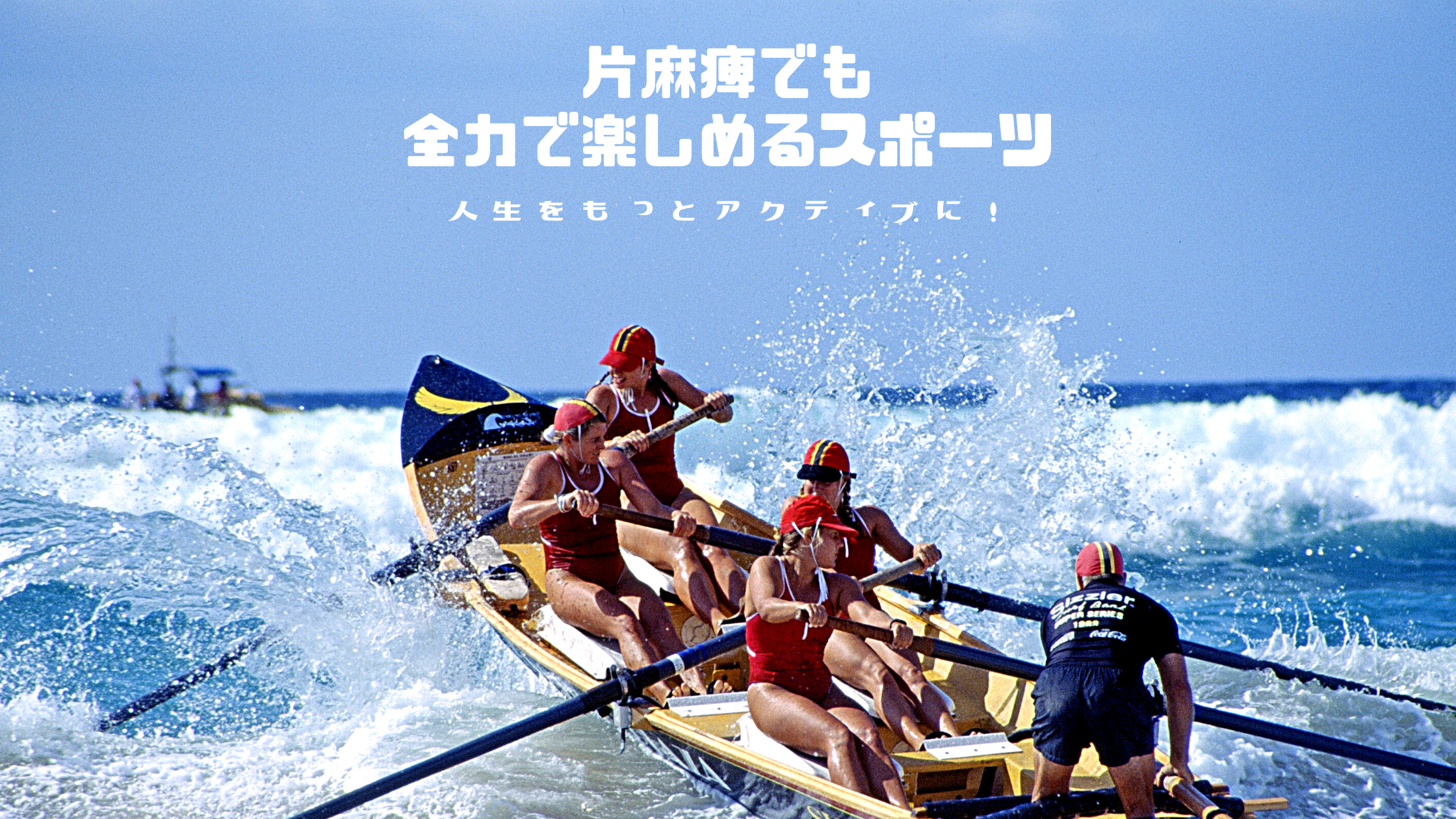
- スポーツ
- 趣味
- 身体障がい
片麻痺でも全力で楽しめるスポーツで人生をもっとアクティブに!
片側に麻痺のある片麻痺でも、スポーツは思い切り楽しめます。
むしろ、身体を動かし続ける中で、自己肯定感が高まったり、新しい仲間と出会えたりすることも。
本記事では、
片麻痺でも気軽に始められるスポーツ
実践者の声や支援情報
を、実例や動画とともにお届けします。
特に、健康的な生活を大切にする片麻痺の当事者や、そのパートナー・家族が一緒に楽しめる内容を目指しました。
スポーツで自分らしく動く喜び
車いすテニス/バドミントンで笑顔倍増
車椅子テニスとバドミントンは、片麻痺の人でも取り組みやすいスポーツ。特に下半身の麻痺がある方に適しており、上半身を使って力強いスイングが可能です。
障がい者スポーツ連盟が明確なルール整備を進めており、初心者から大会出場を目指す競技者までスムーズに参加できます。
参考動画
https://youtu.be/gouJixYiq34?si=NjcYqiIHh_AB_nG9
https://www.youtube.com/watch?v=EOJTba5diYY
フレームランニング(歩行補助走)にチャレンジ
地面に固定されたランニングフレームにまたがり、歩く・走る動きを安全に楽しめるスポーツです。
もともとは脳性麻痺の人向けに生まれましたが、片麻痺の方にも人気。
参考リンク:フレームランニングの良さを広めたい
障害があっても乗れる自転車で風を切る爽快感
自転車に乗るのは難しい…と思いがちですが、障害があっても乗れる自転車なら、片側麻痺でも比較的スムーズに乗車可能です。バランス補助付きで安全に風を感じながら運動できます。
リハビリにも効果があり、医療機関でも導入事例があります。
参考リンク:NPO法人アダプティワールド
水辺から雪山まで!アウトドアを楽しむアイデア
スイミングで全身運動
水泳は、浮力があるため関節や体に負担がなく、疲れにくい運動として片麻痺に適しています。
プールでの自由な体の動きは、筋力・可動域・バランス感覚を自然に向上させてくれます。温かい水でリラックスしながら行える点も魅力です。
シットスキーで雪上ウォータリング
本格的な雪山遊びを望むなら、シットスキー(座ったまま滑走できるスキー装置)がおすすめ。
座位でも雪と触れ合える喜びは格別です。
カヤック&パドルスポーツで自然とつながる
座位でも操作可能なカヤックは、腕力と体幹を使った水上アクティビティ。自然の音や風を近くに感じられる、リフレッシュ効果の高いレジャーです。
体験会や教室も増えており、安全面も配慮されたサポート体制が整っています。
自宅や仲間と楽しむスポーツ&エンタメ
ボッチャや卓球で盛り上がる
ボッチャは、ボールの位置を狙うゲームで、身体的ハンデに関わらず楽しめます。卓球も卓上ラケットで片手対応可能。
家族や友人、地域住民とのふれあいの時間にぴったりです。
自宅で楽しむ視聴覚エンタメ
運動が難しい日は、パラリンピックの名場面動画を楽しんでみましょう!
YouTubeには多数の公式・ファン動画があります。
実践者の声「できた!の瞬間が人生を変える」
片麻痺でもマラソンなどに挑戦する姿
脳梗塞や片麻痺の後、マラソンやトライアスロン、100kmウルトラマラソンに挑戦する方が増えています。
早見さんは「B-SUB4プロジェクト」という挑戦を通じて、自分の可能性を広げました
参考リンク:soar(ソア)
12歳で片麻痺からパラローイング日本代表候補へ
片麻痺があっても競技スポーツに挑戦している少年のストーリーが話題に。
パラローイング日本代表候補になるまでのエピソードが紹介されています。
参考リンク:Spportunity
始める前に知っておきたい3つのポイント
じっくり続けられる第一歩を選ぶ
初めは自宅でできる体操や軽い運動、あるいはボッチャや家族と楽しめるものから始めましょう。無理なく続けられる習慣が大切です。
専門家のサポートを活用する
理学療法士やトレーナーに相談しながら、安全なフォームや補助器具の選び方を確認しましょう。
仲間との出会いが継続の鍵
イベントや支援団体、アダプティブスポーツの体験会に参加すると、同じ境遇の仲間や理解者と出会いやすく、モチベーションの維持につながります。
まとめ:楽しく続けることで得られるもの
片麻痺があっても、スポーツやエンタメを楽しむ力は誰にでもあります。重要なのは“最初の一歩”と“継続する工夫”。少しずつできることを増やし、自分にぴったりの活動を見つけていきましょう。
運動による心身の変化、仲間とのつながり、新たな趣味として取り入れる楽しさ。これらが揃えば、「できない」が「できた!」に変わり、人生の幅がぐっと広がります。
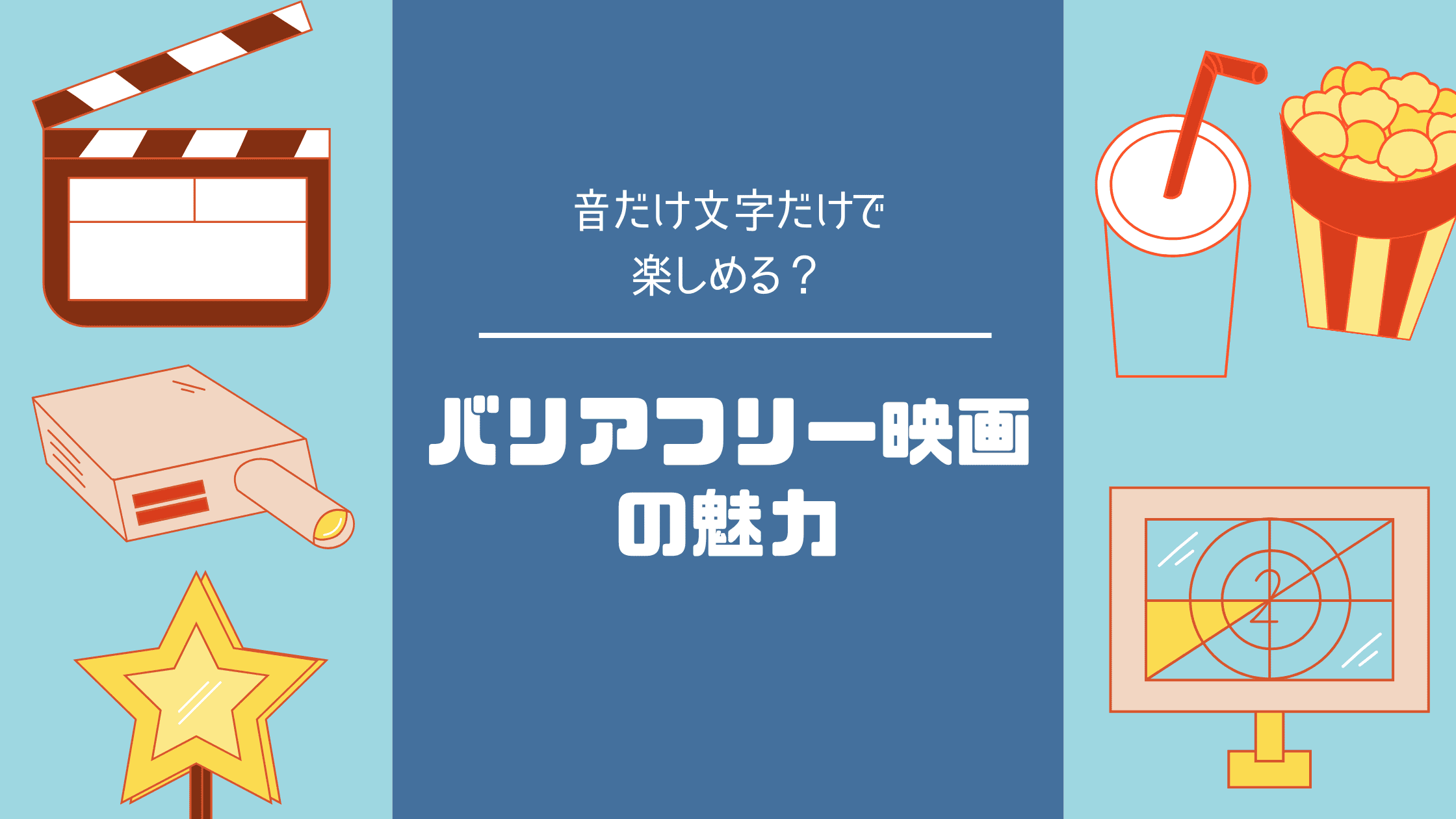
- 映画
- 趣味
- 身体障がい
音だけで、文字だけで楽しめる?バリアフリー映画の魅力
はじめに:誰もが「映画」を楽しめる世の中へ
映画は感動を共有し、想像を掻き立てる文化です。しかし視覚や聴覚に制約がある人にとっては、それが当たり前ではありません。
そこで注目されているのが、音声ガイド付き上映やバリアフリー字幕などの「映画におけるバリアフリー化」。これらは、見えなくても聴こえなくても、映画を同じように楽しむための大切な取り組みです。
バリアフリー映画とは?
音声ガイド付き上映とは?
音声ガイドとは、映像の動きや表情、場面の変化を音声で補足する仕組みです。
たとえば登場人物の表情や動機、景色の説明をナレーション化し、映像の主音声(セリフや音楽)に被らないよう工夫され、絶妙なタイミングで挿入されます。
日本では、ソニー・ピクチャーズが提供する“バリアフリー日本語音声ガイド”が代表例です。
参考リンク:SONY Pictures バリアフリー日本語音声ガイドとバリアフリー日本語字幕
バリアフリー字幕とは?
字幕には「耳の聞こえない人向けに音で伝わる情報を文字で伝える」機能があります。通常の字幕に加えて、環境音や効果音、音楽の説明まで網羅します。
バリアフリー字幕は「補助的な字幕」とは異なり、構成から専門基準をもって制作されています。
オープン方式とクローズド方式
オープン方式:映像に字幕や音声ガイドが埋め込まれており、誰でも利用可能。
クローズド方式:専用デバイス(スマホ・スマートグラス)を使い、必要な人だけが享受できる形式。
参考リンク:NPOメディア・アクセス・サポートセンター(MASC)
日本における実際の取り組みと利用法
HELLO! MOVIE/UDCast:スマホ・スマートグラス一台で
「HELLO! MOVIE」はスマホやスマートグラスで、映画に音声ガイドや字幕ガイドをリアルタイム同期できる無料アプリです。2024年時点で10万以上ダウンロードされています。
使い方は簡単!
アプリをインストール
鑑賞前に音声ガイドか字幕ガイドを選択・ダウンロード
映画館で再生される音をスマホが認識し、自動でガイド開始
アプリDL:HELLO! MOVIE公式サイト
映画館での“バリアフリー上映会”
全国の映画館や特別上映会では、ヘッドホンと音声ガイドで視覚障がい者に合わせた上映や、字幕グラスによる聴覚障がい者対応上映を実施しています。
「映画みにいこ!」では最新のバリアフリー上映情報やポッドキャストも提供中です。
参考リンク:映画みにいこ!バリアフリー映画情報
バリアフリー映画の魅力と効果
映像の「共有」が可能になる喜び
音声ガイドや字幕を通じて、見えない人も見える人も同じ映画の感動を共に体験できます。
友人や家族と「選択肢」ではなく「共感」ができる場となることは、映画の本質そのものを高めています。
表現への新視点と創造性の拡張
特に音声ガイドは、描写表現の芸術として昇華しうる存在です。
河瀬直美監督の『光(Radiance)』では、音声ガイド制作の担当者である主人公の葛藤や苦悩を通じて、“どこまで説明すべきか”という問いの芸術性を観客に深く考えさせる構造になっています。
音声ガイドは作品の一部として、ただ映像を補完するだけでなく、映像が持つ意味や感情を翻訳しようとする高い創造力を帯びて描かれています。
映画紹介:『光』公式ページ
自宅でも楽しめる!サービス&アイテム紹介
SONYバリアフリーBD:映画を家でも音声ガイドで
ソニー・ピクチャーズは家庭向けに、バリアフリー音声ガイド&字幕付きBlu‑ray/DVDを多数発売しています。
参考:ソニー バリアフリーBlu-ray作品一覧
THEATRE for ALL:多彩なジャンルでバリアフリー対応
THEATRE for ALLは、演劇・ダンス・映画・メディア芸術などを対象に、多様なバリアフリー対応(音声ガイド/字幕/手話通訳)を施した映像作品を配信しています。
スマホ・タブレット・パソコンでストリーミング視聴が可能で、作品ジャンルも幅広く、アート鑑賞の裾野を広げています。
多言語対応や知的障害・発達障害に配慮した設計もされており、視覚障害者に限らず包括的な設計が特徴です。
公式サイト:THEATRE for ALL 映像アーカイブ
利用者の声とリアルな体験
スマートグラスで字幕上映の感動
字幕メガネとHELLO! MOVIEの組み合わせで、家族や友達、恋人と一緒に映画を楽しめたという感想が寄せられています。
映画館へ一人で出かける安心感を手に
視覚障がいのある方からは「一人でも映画館へ行く勇気が湧いた」「友人と一緒に共感できた」という声があり、映画館が身近になったと喜ばれています。
今後に期待したい展望と課題
対応作品数の拡充と全国展開
スマホアプリなどの技術を活用して、全国どこでも誰でも利用できるバリアフリー化が理想です。
映画会社や自治体との連携がカギとなります。
音声ガイドのクオリティ改善
ナレーションのバランスは重要で、「説明しすぎは想像の余地を奪う」という指摘もあります。
適切なガイダンス設計が求められています。
おわりに:すべての人が感動を共有する未来へ
音声ガイドやバリアフリー字幕は、一部の人のためだけのものではなく、全ての映画ファンを包み込む普遍的価値です。
「音だけで、文字だけで楽しめる」世界は、ひと昔前には想像できませんでしたが、いまでは映画文化に欠かせない一要素になりつつあります。
ぜひ次回の映画鑑賞は、こうした社会に優しく、自分にも優しい選択肢を試してみてください。共有された感動が、あなたの映画体験をさらに豊かにしてくれるはずです。
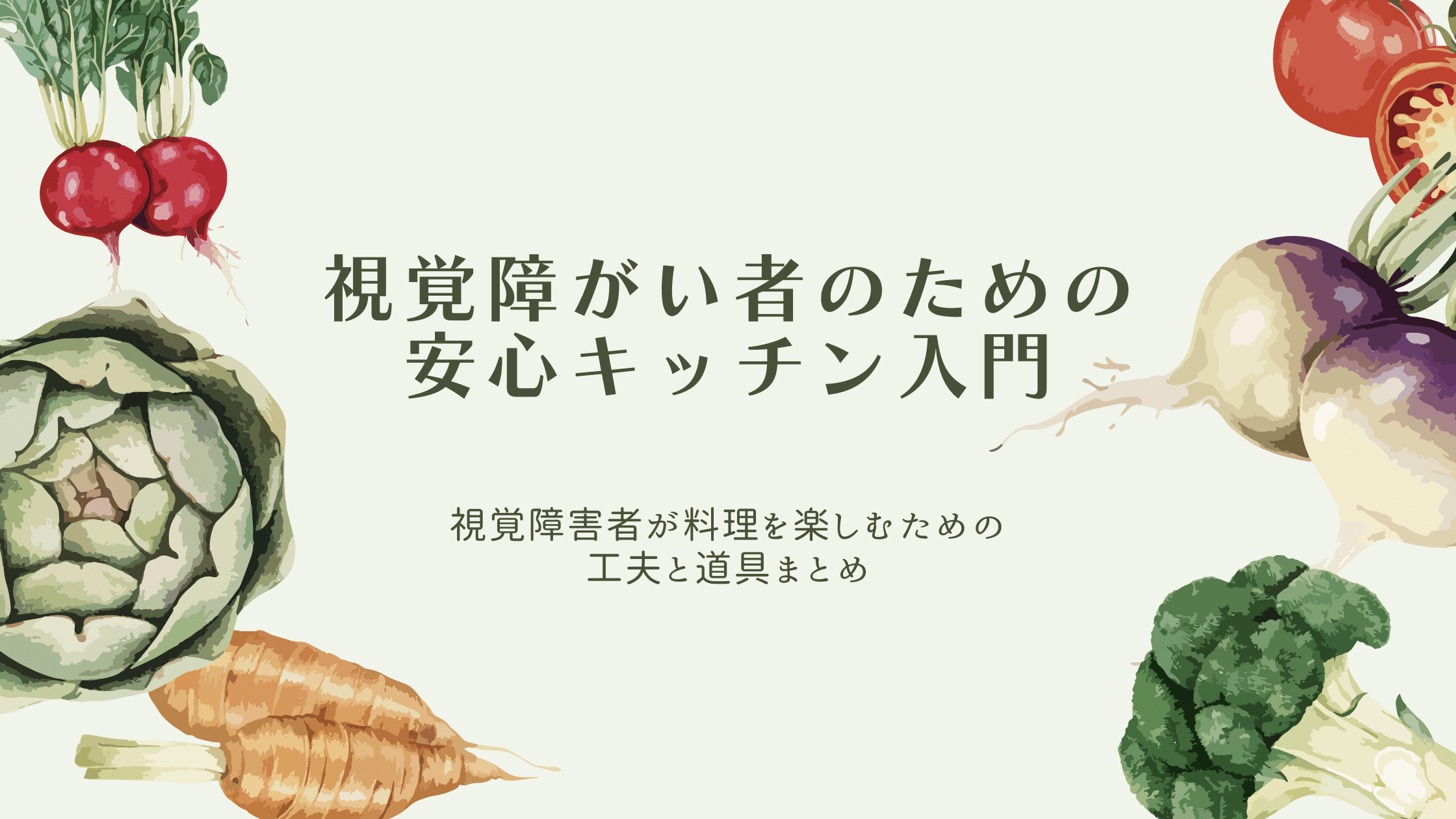
- 趣味
- 生活
- 身体障がい
- 料理
視覚障がい者のための安心キッチン入門
「視覚障がいがあると料理は危ない」「包丁や火を使うなんて無理」
こう思われがちですが、実はそんなことはありません。視覚に頼らずとも、調理を安全かつ楽しく行うための道具や工夫は、近年急速に進化しています。
この記事では、視覚障がいを持つ方が自宅で料理をする際に安心して使えるサポートアイテムや、日々の調理を快適にするコツ、失敗しにくい環境づくりまでを解説します。
視覚に頼らない料理ってどういうこと?
他の感覚を活用した調理スタイル
視覚以外の感覚——特に聴覚・触覚・嗅覚——を活かすことで、調理の進行を把握できます。
フライパンが熱されたときの「パチパチ音」や、ニンニクの香ばしい香り、加熱した鍋の温度を触って確認するテクニックなど、感覚を研ぎ澄ませることで料理の“状態”を見極められるようになります。
参考動画
https://youtu.be/KXGwnvwxDFA
テクノロジーの進化が後押しに
音声ガイド付きのスケールや温度計、スマホアプリ「Be My Eyes」や「Seeing AI」「Envision AI」など、生活支援技術の進化によって、見えない部分を“聴く・伝える”ことが可能になりました。
調味料の識別、加熱状態の確認、レシピの読み上げなど、視覚の代替を担うアイテムが日常に溶け込んでいます。
参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=akOEH8qDGeM
文字認識スマホアプリ「Envision AI」を使って全盲ママがカレーを作ってみた
安全・快適なキッチン環境づくり
調理道具の定位置管理
使う道具は定位置に置きましょう。
たとえば、包丁は必ず同じ場所に戻し、棚には触って分かる「バンプドット」などを貼っておくことで、目に頼らず調理動線が安定します。
参考動画
https://youtu.be/cMpJa61z1jE
火や刃物の“見える化”ならぬ“感じる化”
ガスコンロのつまみに触れる位置に印をつける、IHヒーターに音声操作やタイマーを組み合わせることで、誤作動や火傷リスクを減らせます。
包丁も、滑り止め付きのまな板や指ガードと併用することで、ケガのリスクを最小限に抑えられます。
事前準備が成功の鍵
具材や調味料はあらかじめ計量・仕分けしておきましょう。
すべての材料を手前に配置し、手順通りに並べておくだけで混乱を防げます。
実際に使える“神アイテム”5選
話すキッチンスケール(音声読み上げ)
商品ページ
視覚に頼らずに正確な計量ができるデジタルスケール。
指定の重さを読み上げてくれるため、砂糖・塩・小麦粉などの分量調整が安心です。
液体調味料が定量出せるさじかげん
商品ページ
一押しで10ccと15ccが出せる計量器。
決まった量の調味料が出せるので、味が濃くなったり薄くなったりすることがありません。
黒色まな板
商品ページ
弱視の方向け用。
例えば白い豆腐など、黒色のまな板だとコントラストで良く見えるようになります。
自助食器
商品ページ
縁が高く、食材を集めやすい構造。
片手で食事をすくいやすく、食べやすい設計です。
点字シール
商品ページ
家電スイッチや棚、調味料などに貼ることで、触っただけで操作や位置が判断できます。
安価かつ汎用性が高いのも魅力です。
参照:川崎市視覚障害者情報文化センター 視覚障害者用調理グッズ、coocpod news
視覚障がい者が料理を続けるためのコツ
成功体験を積み上げる
はじめは「卵かけご飯」「サラダ」「冷凍うどん」といった簡単なレシピから挑戦しましょう。
「できた!」という体験が自信を生み、次への意欲を高めてくれます。
習慣化と一貫性が鍵
使う調味料・道具の配置、レシピ手順を一定に保つことで、余計な混乱やストレスを回避できます。
毎日同じ流れをつくることが安心へつながります。
楽しむ気持ちを忘れずに
料理は義務ではなく“楽しみ”でもあります。
たまには香りクイズや食材当てゲームなどで、調理を遊びとしても取り入れてみましょう。
まとめ:道具と工夫で“料理できる自分”へ
視覚障がいがあっても、料理は十分に楽しむことができます。必要なのは、少しの工夫と、安心を支える道具たち。技術の進化とともに、料理の自由度は確実に広がっています。
最初から完璧を目指すのではなく、少しずつ「できる」ことを増やしていきましょう。
安心できる調理環境と、“できた”を積み重ねる日々が、あなたの暮らしに大きな自信と楽しさをもたらしてくれるはずです。
■参考動画
「全盲で一人暮らし?」火を起こす?手を切る?(料理編)
https://www.youtube.com/watch?v=4IIOuTgMVyI
視覚障害弱視の「料理あるある」てんこ盛視覚に障害があっても作れる!おすすめレシピ3選
https://www.youtube.com/watch?v=7zJR9nTRu8g