NewsNewsみんなの障がいニュース
みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、
コラム形式でわかりやすくお届けします。
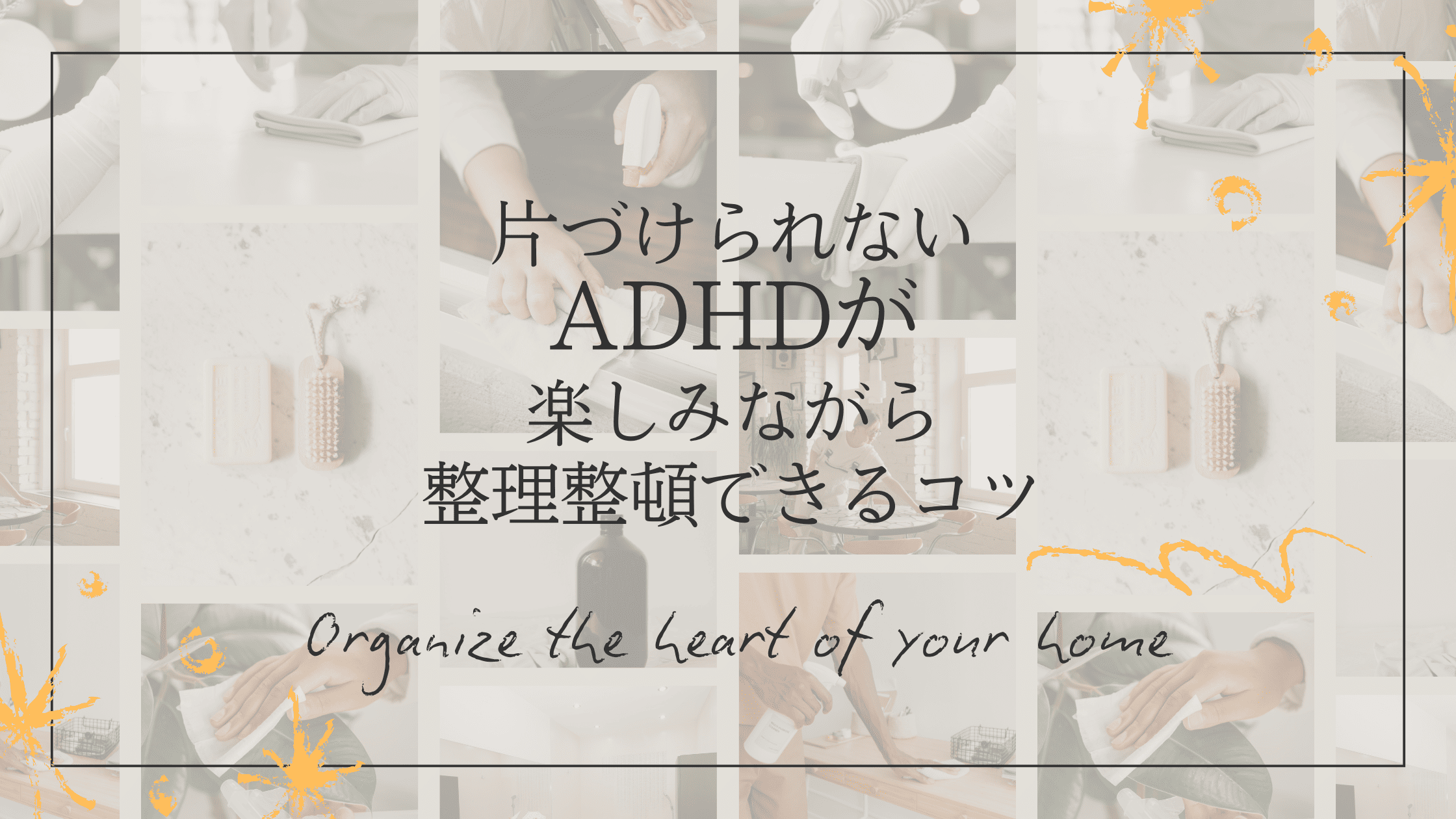
- 発達障がい
片づけられないADHDが楽しみながら整理整頓できるコツ
ADHD(注意欠如・多動症)の特性としてよく挙げられるのが、「片づけが苦手」という悩みです。やるべきことに集中できなかったり、目の前の物に気を取られて整理が中断したりすることが多くあります。
そのため、「片づけられない自分はダメだ」と感じてしまう方も少なくありません。しかし実際には、ADHDの特性を理解し、工夫を加えることで、整理整頓は“楽しみながら”できるようになります。
本記事では、ADHDの方が無理なく片づけを続けられる方法を、具体的なコツと実例を交えてご紹介します。
ADHDの特性を理解することから始めよう
注意の切り替えが難しい
ADHDの方は、興味のあることには集中できる一方で、興味が持てないタスクには集中を維持するのが困難です。
片づけは「終わりが見えにくい作業」なので、取りかかるまでに時間がかかるのも自然なことです。
物への注意が散りやすい
「片づけよう」と思っても、途中で見つけた雑誌を読み始めたり、別の場所の片づけに移ってしまったりすることがあります。これはADHDの特性であり、意志が弱いわけではありません。
仕組み化で改善できる
だからこそ、「やり方を工夫して、楽しみながら続けられる仕組み」を作ることが重要になります。
片づけを“楽しい”に変える工夫
ゲーム感覚で進める
片づけを「タスク」ではなく「ゲーム」に変えると、ADHDの特性に合いやすくなります。
タイマーを3分に設定して「どれだけ片づけられるか」チャレンジ
音楽を流して「1曲分でできる範囲」だけを片づける
スマホアプリで達成を記録する
ゲーム化することで「楽しい感覚」が先行し、無理なく続けられるようになります。
視覚的にわかりやすくする
収納場所に写真やイラストのラベルをつけることで、「どこに戻すか」が一目でわかります。とくにADHDの方は「見える化」が有効です。
箱に中身の写真を貼る
引き出しに色分けシールを使う
オープン収納で“見えている状態”にする
こうした工夫は、「探すストレス」を減らし、片づけを習慣化しやすくします。
ごほうびを設定する
小さな片づけが終わったら、自分にご褒美をあげましょう。お茶を飲む、好きな音楽を聴くなど、“楽しいこと”を関連づけることで、片づけをポジティブな行為として脳が認識しやすくなります。
ADHDの人におすすめの片づけ方法
小さな単位に分ける
「部屋を片づける」と考えると途方に暮れますが、「机の上だけ」「バッグの中だけ」と細かく区切れば達成しやすくなります。
モノを減らす習慣を作る
片づけが苦手な人ほど、モノが多すぎることで負担が増えてしまいます。買い物前に「本当に必要?」と自分に問いかけたり、1つ増えたら1つ手放す“ワンイン・ワンアウト”のルールを作るのも効果的です。
定位置を決める
ADHDの方は「後で置こう」と思うと忘れがちなので、「必ずここに置く」という定位置を決めておくと安心です。
鍵や財布などの“なくすと困る物”から始めると良いでしょう。
片づけを支える便利アイテム
カラーボックス&収納ケース
中が見える透明ケースや色で分けられるカラーボックスは、ADHDの人に向いています。100円ショップでも手に入るため、手軽に始められます。
タイマー付き家電・アプリ
「掃除を10分だけ」と区切るのに便利なタイマーや、ゲーム感覚でタスクを管理できるアプリもおすすめです。
参考リンク:片付けられないのは発達障害のせい?実際の事例や対策について紹介します
支援を受けながら片づけを続ける
専門家に相談する
片づけがどうしても進まない場合、整理収納アドバイザーや発達障害支援センターに相談するのも有効です。
第三者のサポートで、負担が軽減されます。
家族や友人に「一緒にやってもらう」
1人でやると気が散りやすい場合でも、誰かと一緒なら「会話しながら」「進捗を共有しながら」進められるため、楽しく片づけられます。
動画で学ぶ
整理整頓の具体例を動画で学ぶのもおすすめです。
参考動画:
https://youtu.be/23nTWu4v4Lg?si=7hCpFlQtTfXsC4qA
まとめ:片づけは「楽しく」続けることが大事
ADHDの人が片づけられないのは、「性格のせい」ではなく「特性によるもの」です。そして工夫次第で片づけは“楽しい時間”に変えることができます。
ゲーム感覚で片づける
視覚的にわかりやすくする
小さな単位に分ける
支援やアイテムを活用する
このように工夫を重ねながら、少しずつ自分に合った整理整頓法を見つけていきましょう。
「片づけは苦手だけど、自分なりに工夫してやっている」と思えるだけでも、心はぐっと軽くなります。
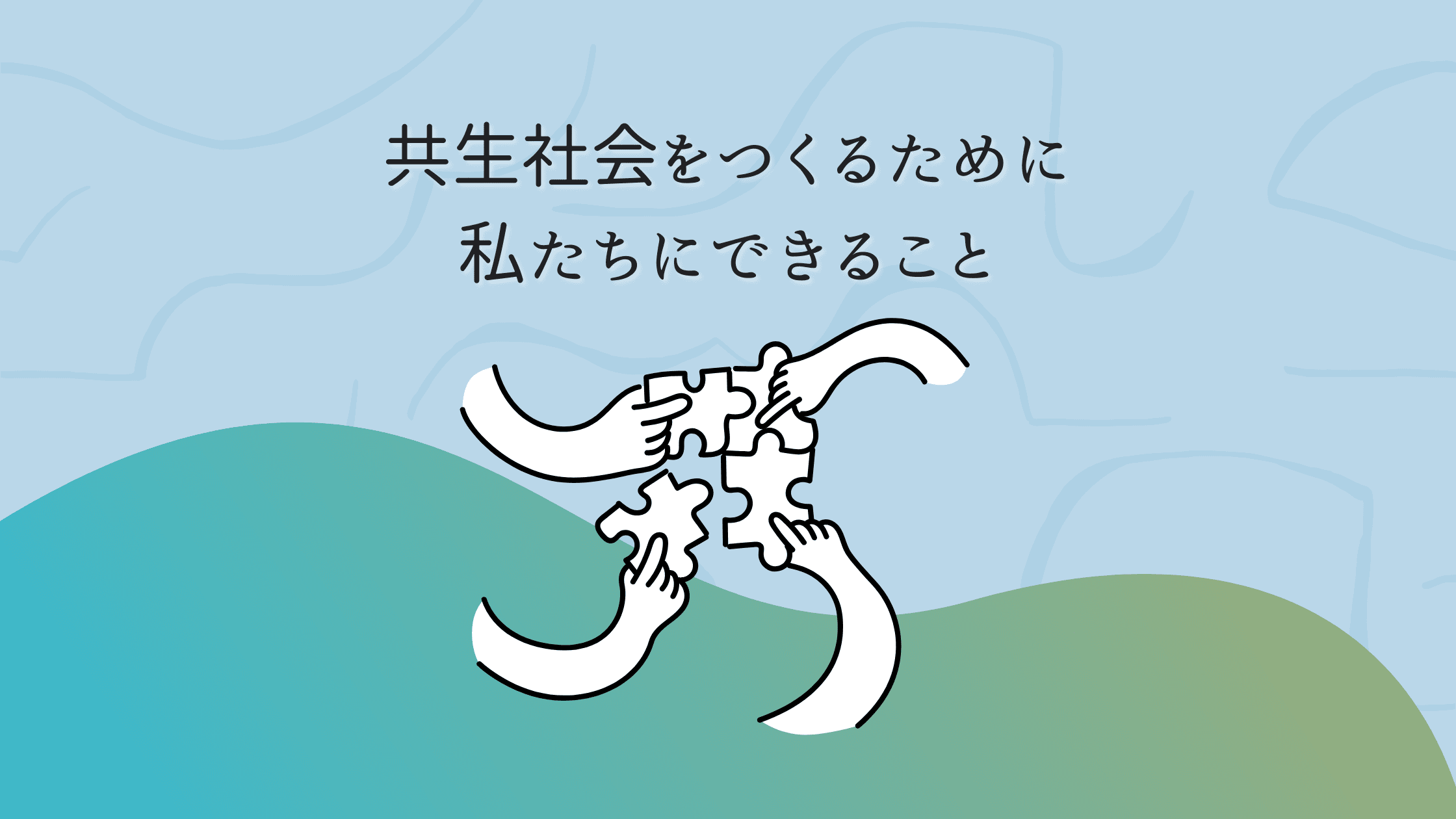
- 福祉
- 情報
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
- コミュニケーション
共生社会をつくるために私たちにできること
はじめに:共生社会とは何か、自分の立ち位置を知る
「共生社会」とは、障がいのある人・高齢者・子育て世帯など、社会を構成する多様な人々が互いに尊重し合い、助け合いながら暮らせる社会のことです。単にバリアを取り除くだけでなく、制度・文化・日常の中で「一人ひとりの違い」を当たり前に受け入れられることが求められています。
では、私たちは具体的にどのような行動を取れるのでしょうか。
この記事では、個人でもできる「共生社会を育むアクション」を紹介します。
自分ができることのヒント:理解と態度を変える
障がいについて学んで誤解を減らす
障がいには外見で見えるものだけではなく、見えにくい・見えないもの(発達障がい、精神障がい、知的障がいなど)があります。
まずは、新聞・書籍・公式サイトで正しい情報を収集すること。知識を持つことで、「どう声をかけたらいいのか」「どう接したらいいのか」が見えてきます。
例えば、日本財団の DO-IT Japan では、若者たちに障がいについての理解や自己決定、自己主張(セルフアドボカシー)の教育プログラムを提供しています。これにより、当事者も周囲の人も「共に選択できる社会」への意識が育まれています。 日本財団
日常の行動で「小さな配慮」を実践
理解が深まった後は、具体的な行動へ。
例えば、公共交通機関で高齢者・障がい者を見かけたら席を譲る、歩く速度を少し落とす、話しかけるときにゆっくり明瞭に話す、案内表示に注意を向けるなど。これらは非常に小さな行動ですが、周囲への影響は大きいです。
また、情報の受け取り手の立場を考えた発言や書き言葉を使うことも含まれます。「健常者」「障がい者」で区別する言葉遣いを見直したり、バリアを感じさせない表現を心がけたりすることなどが、理解ある共生の環境を作る上で役立ちます。
自分の得意を活かして関わる場を見つける
誰でも得意なこと、好きなことがあるはずです。それを共生社会づくりに活かすことができます。
例えば、絵や音楽などのアートが好きなら地域の学校や福祉施設でワークショップを手伝う、本の読み聞かせ、イベントでの手話通訳やサポートなど。得意分野を活かすことで、障がいのある人々との距離が縮まり、自分自身にとっても達成感が得られるでしょう。
制度・コミュニティと手をつなぐ
地域共生社会の制度を知ること
日本では「地域共生社会」の実現に向けて、自治体・国による政策が進められています。厚生労働省の「地域包括ケア」や障がい者基本法の合理的配慮など、制度を知ることで、どこでどう参加できるかのヒントがつかめます。
特に自分の住む自治体がどんな共生社会政策を導入しているかを調べることは有用です。
参考リンク: 「地域共生社会」の実現に向けて
ピアサポートやボランティア活動に参加する
障がいのある人自身が参加する活動(ピアサポート)や、障がい者支援団体のボランティアは、共生社会を体現する場です。
参加者は互いの経験を共有し、学びあいながら、支え合いのかたちを広げられます。自分に合ったペースで参加できる活動を探してみましょう。
「合理的配慮」をくり返し求める声を上げる
学校、職場、公共施設などで「この部分がこうだったらもっと使いやすいのに」という場面に出くわしたら、声を上げるまたは改善案を提示することが共生社会につながります。
合理的配慮は法律で定められており、その要望は決して特別扱いではなく、平等のための調整です。
参考リンク:共生社会の形成に向けて
支えられる側の視点も尊重する
自己決定・自己表現を尊重する
共生社会では、障がいのある人が「何を望むか」「どう暮らしたいか」を自分で決めることが重視されます。周囲が先回りして判断するのではなく、意見を聞き希望を尊重することが大切です。
これは学校・家庭・医療・福祉などあらゆる場面で意識されてきています。参考リンク:共生社会とは?実現のために自分でできること・取り組みの具体例
支援される側が支援を求めることを遠慮しない
もし何かに困っていたら、支援を求めることは恥ずかしいことではありません。
合理的配慮をお願いする、相談窓口を利用する、必要な情報を得るなど、自分のできる範囲で支援を受けることも、自立と共生の一部です。
実際の取り組み・事例から学ぶ
DO-IT Japan:若者に自分らしい選択を促すプログラム
DO-IT Japan は、中学〜大学院までの障がいや病気のある若者を対象に、テクノロジーを使った学びやワークショップ、オンライン・オフラインでの交流を通じて「自分の未来をどう描くか」を自分で考え、選べるようにするプログラムです。
これにより、多くの参加者が自己理解を深め、自信を持って進学や就労へ歩み始めています。
参考リンク:「自分らしい選択ができる」社会に。DO-IT Japanが活動を通じて障害のある若者に伝えたいこと
政府の政策と制度による土台づくり
日本政府は、障害者基本法・障害者差別解消法などを通じて、教育・就労・公共の場での合理的配慮の提供を促進し、制度として共生社会を支える仕組みを整えています。
これにより、障がいのある人が社会参加しやすくなる環境が少しずつ広がっています。
参考リンク:障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現に向けた取組
動画で共生を感じる:共生社会の現場を知る
YouTube チャンネル「964万7千分の一」は、障がいや障害者の家族の日常をリアルに伝え、共生社会に必要な視点を届けてくれます。
参考リンク:964万7千分の一
まとめ:共生社会を形にするために今、できること
障がいについて正しく学び、誤解を減らす
日常の中での小さな配慮を意識する
自分の得意を活かして支え合いに参加する
制度を知り、必要な合理的配慮を求める
自分の希望・意見を大切にし、声をあげる
共生社会は「待つもの」ではなく「つくるもの」です。
ひとりひとりができることを少しずつ行動に移すことで、障がいの有無に関わらず居心地のいい社会は確実に近づいてきます。
あなたにも、あなただからできる共生社会への一歩があります。その一歩を今日から、踏み出してみませんか?
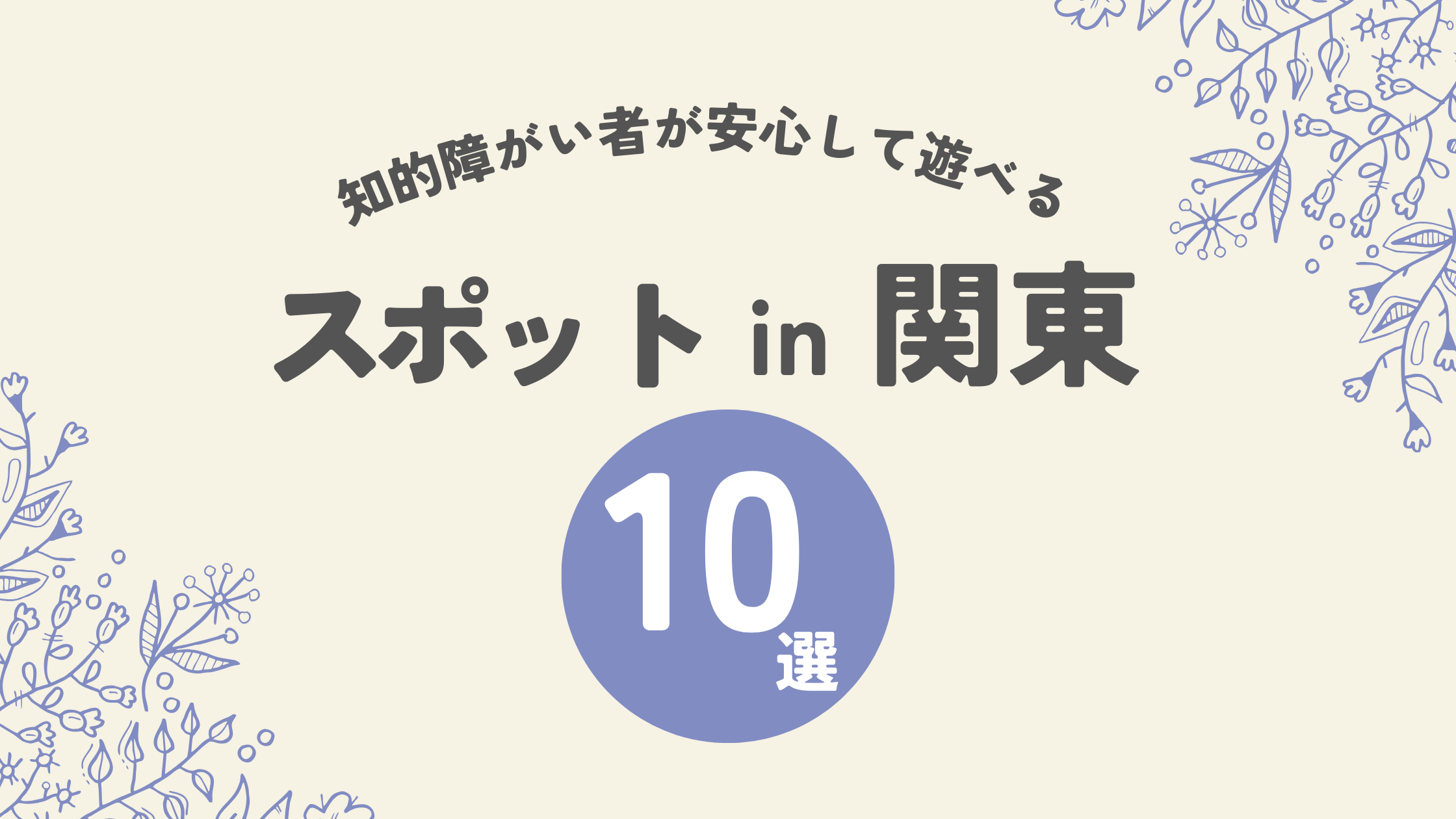
- 子育て
- 家族
- 知的障がい
知的障がい者が安心して遊べるスポット 関東編
知的障がいを持つ方やそのご家族にとって、「安心して楽しめる場所」を探すのは意外と大変なことです。人混みや音の大きさに不安がある、サポート体制が整っていないと心配、という声もよく聞きます。
本記事では、関東地方で知的障がい者と一緒に安心して楽しめるスポットを紹介します。遊び場・文化施設・自然体験・テーマパークなどジャンルごとに整理しました。また、実際に運営されている日本の公式サイトや参考動画もリンク付きで紹介するので、訪れる前にチェックできますよ。
テーマパーク・遊園地で楽しむ
東京ディズニーリゾート(千葉県)
知的障がいのある方に人気のスポットが、東京ディズニーリゾート。
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、アトラクション待機列に関するサービスである「ディスアビリティアクセスサービス」「合流利用サービス」と、ショーなどを優先鑑賞できる「優先鑑賞エリア」を利用できます。アトラクションに並ぶ時間を短縮できたり、スタッフが丁寧に対応してくれるので安心です。
参考リンク:ゲストアシスタンスカードの代替えとなるサービス
参考動画:【公式】東京ディズニーリゾート チャンネル
よみうりランド(東京都稲城市)
比較的混雑が少なく、広々とした遊園地として知られるよみうりランド。知的障がいを持つ方も利用しやすいバリアフリー設計が進んでおり、観覧車やゆったり楽しめる乗り物が多いのが特徴です。
公式サイト:よみうりランド
水族館・動物園でのんびり過ごす
すみだ水族館(東京都墨田区)
東京スカイツリー内にある「すみだ水族館」は、落ち着いた空間づくりが魅力です。照明が柔らかく、座れるスペースが多いため、知的障がいのある方でも安心して楽しめます。ペンギンやクラゲの展示は特に人気です。
公式サイト:すみだ水族館
上野動物園(東京都台東区)
日本で最も有名な動物園のひとつ。障がい者手帳を提示すると入園料が無料になり、付き添いの方1名も無料です。園内はスロープや案内板が整備され、知的障がいのある方でも無理なく散策できます。
公式サイト:上野動物園
科学館・博物館で学びながら楽しむ
国立科学博物館(東京都台東区)
恐竜の化石や宇宙展示など、見て触って学べる展示が多く、知的障がいのある方も夢中になれる博物館です。混雑が心配な場合は、平日の午前中に訪れるのがおすすめです。
公式サイト:国立科学博物館
日本科学未来館(東京都江東区)
ロボットや宇宙開発の展示で有名な未来館。展示物に触れたり体験できるものも多く、知的障がいを持つ方が楽しみながら学べる環境が整っています。
公式サイト:日本科学未来館
自然を感じられるスポット
国営昭和記念公園(東京都立川市)
広大な芝生広場や季節の花畑が楽しめる国営公園。ゆったりとしたペースで自然を満喫でき、車いすやベビーカーでも移動しやすい設計です。知的障がいのある方も落ち着いて過ごせる環境が整っています。
公式サイト:国営昭和記念公園
こどもの国(神奈川県横浜市)
自然体験や遊具、動物ふれあいがそろった総合施設。体を動かしたいお子さんから静かに過ごしたい方まで幅広く楽しめるスポットです。
公式サイト:こどもの国
芸術・文化を身近に感じる場所
東京都美術館(東京都台東区)
美術館というとハードルが高い印象がありますが、東京都美術館はバリアフリーに力を入れています。音声ガイドやワークショップもあり、知的障がいを持つ方がアートを身近に感じられる取り組みがあります。
公式サイト:東京都美術館
神奈川県立近代美術館 葉山館
海を眺めながらアート鑑賞ができる施設。静かで落ち着いた空間が広がり、ゆったりとした時間を過ごせます。
公式サイト:神奈川県立近代美術館 葉山館
まとめ:安心できる場所を選んで楽しい思い出を
知的障がいを持つ方にとって、「安心して楽しめるかどうか」が外出の大きなカギになります。関東にはサポート体制が整ったテーマパークや、水族館、博物館、公園などがたくさんあります。
出かける前に公式サイトや動画を確認し、混雑状況やサポート情報を把握しておくと安心です。楽しめる場所を選び、家族や友人と素敵な時間を過ごしましょう。
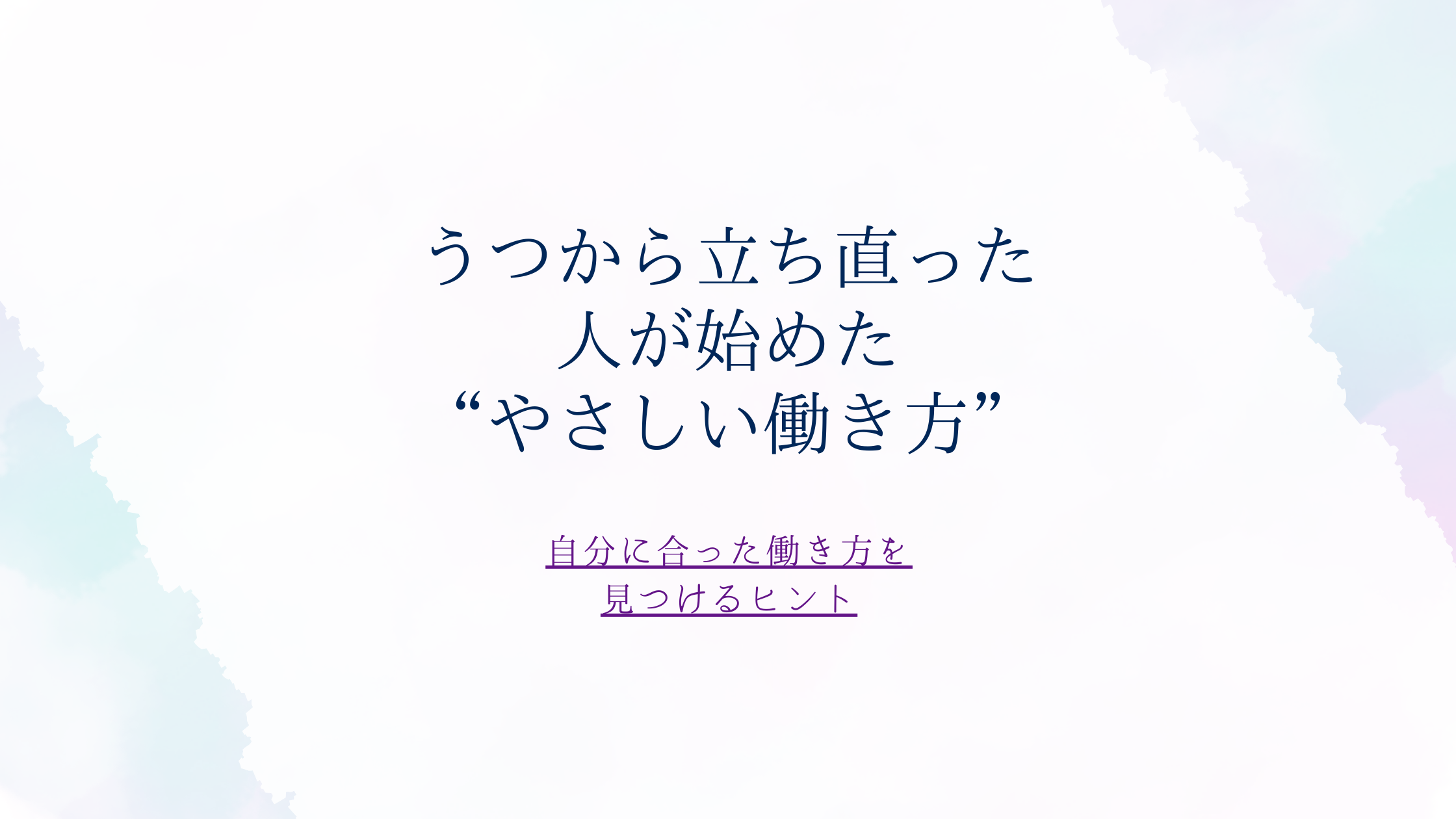
- 精神障がい
- 仕事
うつから立ち直った人が始めた“やさしい働き方”自分に合った働き方を見つけるヒント
はじめに
うつ病を経験すると、仕事への復帰には勇気が必要です。
再発への不安、周囲の評価への恐れ、自分への信頼喪失――。
そんな中で、「もう一度、でも無理はしたくない」と感じる人も少なくありません。
そこで注目したいのが、“やさしい働き方”。これは、自分の状態やペースに応じて働く選択肢を自らつくることです。
この記事では、実例や支援制度をもとに、その具体的な方法を紹介します。
安心して働く環境をつくる|復帰への第一歩
私に合う働き方とは何か、自分を知る
うつからの復帰では、まず「自分が安心して働ける働き方」を見つけるのが大切です。
例えば、仕事を続けながらも負担が少ない短時間勤務や、環境調整を伴う部署異動などがあります。
医師と相談し、職場にも状況を共有することがポイントです。
参考リンク:未来トレーニング「うつ病の方でも無理せず長くはたらき続けられるコツ
途中で辞めた私が就労移行支援で変われた理由
30代女性・Mさんは、うつの後に就労移行支援機関LITALICOワークスを通じて復職しました。
明るい雰囲気と少しずつ慣れる支援に触れ、「また働きたい」という気持ちが蘇ったそうです。
参考リンク:うつ病(精神障害)のある方の就職事例を紹介|支援員で働く30代女性
生活リズムと働き方の工夫|無理せず続ける秘訣
短時間勤務や在宅ワークを取り入れる
朝つらい、通勤がストレスになるという人には、短時間勤務や在宅勤務が有効です。
環境を自分で整えられる在宅ワークは、特に効果的な選択肢として注目されています。
参考リンク:きづきカンパニー「うつ病のある人にオススメの働き方」
周囲に理解を得ることで負担を軽く
うつは「理解されにくい病気」でもあります。
だからこそ、上司や同僚に「日の状態に波がある」ことを共有し、フォロー体制を整えることが重要です。
参考リンク:LIVA「うつ病の克服~仕事しながら克服するために大切な5つのこと~」
仕事を選び直すという道もある
軽作業や一般事務が意外と向いている
人との関わりやプレッシャーが少ない職種は、うつの回復期には働きやすい傾向にあります。
その代表が、倉庫での軽作業やデータ入力などです。
参考リンク:福いろ「うつ病の人にが働きやすい仕事」
自分の体調にあわせて無理せず働く
一般事務や軽作業はマニュアルが整備され、プレッシャーが少ない傾向があります。
作業に集中できる環境が、精神的な安定に繋がります。
参考リンク:atGP「うつ病の人に向いている働き方とは?」
社会復帰のリアルな物語
北海道に戻り、新たな選択肢を見つけたケース
入社10年目でうつ病になった男性は、支援を受けながら地元に戻り、障がい者枠での就職を実現。
やりがいと働きやすさのバランスを探りながら、新しい道を歩んでいます。
参考:Doda「うつ病/40代男性/総務職での転職ストーリー」
安心できる職場で自信を取り戻したM.Mさん
接客業を続ける中でうつを経験した後、障害者雇用枠でパーソルダイバースに再就職。
休憩を「仕事の一部」ととらえ直し、少しずつ自信とやさしさが戻ったという事例です。
参考:with パーソル「うつ病を抱えた私が見つけた『安心してはたらける職場』と『障害と向き合う工夫』」
再発を防ぎながら働くポイント
ストレスの少ない習慣を心がける
脳と心の健康には、休憩や生活リズムが重要です。
過重労働を避け、定期的な医療フォローを継続するなど、予防に努めましょう。
参考:MedicalDoc「再発を防ぐ働き方」
周囲に相談して環境調整を
変化が苦手な人にとって、働き方の工夫(早退可能、業務負荷の調整など)を職場と話し合って決めるのは、大きな安心に直結します。
まとめ:「やさしい働き方」で人生に再び輝きを
うつからの復帰には、無理しない、自分に合った働き方が鍵になります。短時間や在宅勤務、人を選ばない職種、支援制度の活用など、「やさしい働き方」があなたのやる気と心を守ります。
自分にやさしい選択が、やがて社会への貢献にもつながります。焦らず、一歩ずつ。あなたのゆるやかな再出発を心から応援します。
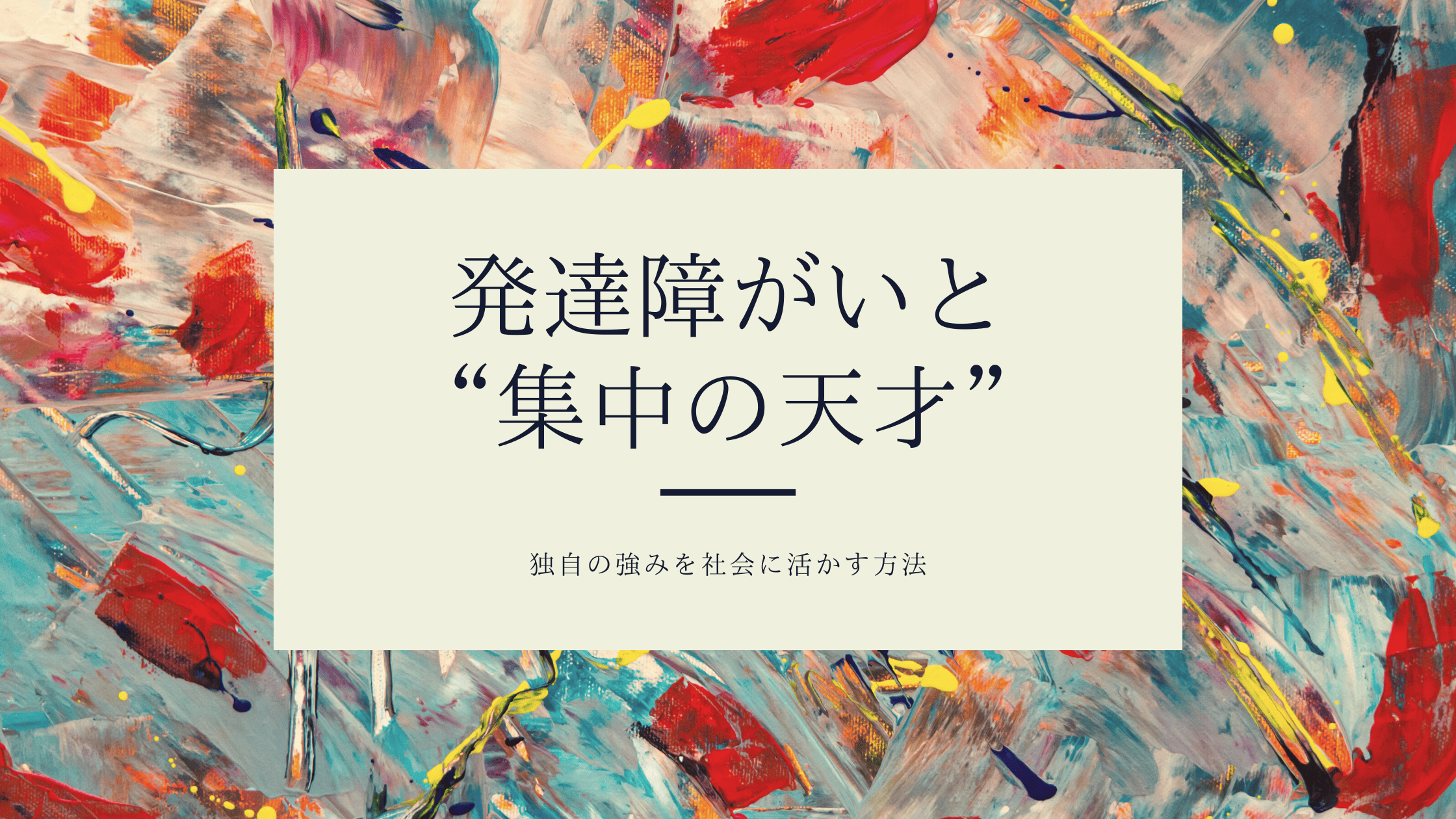
- 発達障がい
- 仕事
発達障がいと“集中の天才” 独自の強みを社会に活かす方法
発達障がいと「集中力」の関係を理解する
過集中(ハイパーフォーカス)という特性
発達障がい、とくにADHDやASD(自閉スペクトラム症)の人には、「過集中」と呼ばれる特性があります。これは「好きなこと」「興味があること」に対して、周囲の音や時間を忘れるほど深く没頭できる力のことです。
一般的には「注意散漫」「集中が続かない」と思われがちですが、実際には“特定の対象への異常なほどの集中”という、両極端な特性があるのです。
例えば、プログラミングに没頭して気づけば朝になっていたり、趣味の研究に取り組んで数時間が一瞬で過ぎていた、という経験を持つ人も少なくありません。
これは単なる「欠点」ではなく、適切に活かせば社会において大きな力となるものです。
「好き」をエネルギーに変える
過集中は「嫌いなこと」には発揮されにくい一方、「好きなこと」には大きな成果を生み出します。つまり、自分の興味や関心の方向を見つけることが、才能を活かす第一歩となります。
厚生労働省の調査でも、発達障がいのある人が自分の強みを生かせる職場環境にいるとき、就労継続率が高い傾向があると報告されています。
参考リンク:厚生労働省「経営の観点から見た障害者雇用の効果と進め方」
発達障がいの強みが発揮される分野
IT・クリエイティブ分野での力
プログラミング、デザイン、動画編集、音楽制作などの分野では、細部に没頭できる力が活きやすいです。コードのバグを探す、映像を丁寧に編集する、音を重ねて理想の音楽を作るといった作業は、まさに「集中の天才」の力が試される場です。
YouTubeには、発達障がいのあるクリエイターが自分の強みを活かして発信している例も多くあります。
https://youtu.be/ibSBeSoxNrg?si=bHgYoFrkyB9W1-DG
https://youtu.be/_g9qy3ilt8w?si=ho9dW1xJc6pSUhzD
研究・学問分野での成果
発達障がいのある人の中には、特定の分野に関する膨大な知識を蓄え、専門家顔負けの洞察力を持つ人がいます。
歴史、昆虫、宇宙、数学など、一見マニアックに思える知識が、研究分野や教育の場で大きな武器になることもあります。
ビジネスや企画の場での発想力
一方向に集中するだけでなく、独自の視点から新しいアイデアを生み出すことも強みです。
固定観念にとらわれず自由に発想できることは、イノベーションの源泉でもあります。
強みを活かすための環境づくり
自分に合った働き方を見つける
発達障がいの特性を理解したうえで、自分が成果を出しやすい働き方を模索することが大切です。例えば、リモートワークやフレックス制度は、自分の集中が高まる時間帯に作業できるというメリットがあります。
近年では「就労継続支援」や「特例子会社」など、発達障がいの特性を理解した職場も増えています。
参考リンク:発達障害者支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)
周囲とのコミュニケーションを工夫する
強みを活かすには、周囲の理解も欠かせません。そのために有効なのが「アサーション(自己表現)」です。
「自分はこの環境だと力を発揮しやすい」「この作業は得意」など、具体的に伝えることで、周囲との協力体制が生まれます。
参考リンク:自分でできるアサーショントレーニング(国分寺イーストクリニック)
休むことも“才能を活かす力”
過集中は疲労に気づきにくいため、休むことを意識的に取り入れることも必要です。
ポモドーロタイマー(25分集中+5分休憩)などを活用し、心身を守りながら長く才能を活かせる環境を整えましょう。
https://youtu.be/B3UM8TizqYQ?si=DgeCrXhWhGkhcqW2
事例紹介:発達障がいと強みの活かし方
芸術家やクリエイターの例
世界的に有名な画家のゴッホや音楽家のモーツァルトは、発達障がいの特性を持っていたのではないかといわれています。
彼らの作品に宿る圧倒的な独創性は、「集中」と「こだわり」が生み出したものです。
現代日本でのロールモデル
近年は、日本でも発達障がいを公表しながら活動する著名人が増えています。
タレントの栗原類さんは、発達障がいを公表しつつ俳優・モデルとして活躍しています。彼の著書『発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由』は、多くの人に勇気を与えています。
参考書籍:発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由(栗原類)
まとめ :発達障がいの強みを社会で輝かせるために
発達障がいは「できないこと」に焦点を当てられがちですが、実際には「集中の天才」ともいえる強みを持っています。自分の興味・関心に基づいた分野を見つけ、環境を整え、周囲に伝えることで、その強みは社会の中で輝きを放ちます。
障がいは「個性」であり、視点を変えれば大きな可能性に満ちています。一人ひとりの「集中の天才」が認められ、社会の中で活かされる未来を築いていくことが、私たち全員にとっての希望になるでしょう。

- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
障がいのある自分を好きになる|認めて愛することで広がる前向きな生き方
障がいがあると、「できないこと」「不便なこと」に気持ちが向きやすくなります。しかし、同じくらい「できること」や「自分だけの強み」も必ず存在します。障がいは自分を否定する理由ではなく、新しい可能性を見つけるきっかけにもなり得るのです。
この記事では、障がいを持つ自分を「好きになる」ための考え方や工夫を、心理学や体験例を交えて紹介します。
自分を認める第一歩“できない”から“できる”へ
視点を変えるだけで毎日が違って見える
たとえば、「文章を書くのが遅い」ではなく「丁寧に書ける」ととらえるか。同じ出来事でも視点を変えるだけで「できた自分」「工夫できた自分」を発見できます。
この小さな切り替えが、自己否定から抜け出す第一歩です。
他人と比べず、昨日の自分と比べる
「人より遅い」「できない」と思ってしまうのは自然なことです。
でも、比べるべきは他人ではなく「昨日の自分」。昨日より少しだけできたことがあれば、それは立派な成長です。
心理学者アドラーも「自分の人生を生きることが大切」と説いています。
自分を好きになる工夫|小さな自己肯定感の積み重ね
感謝日記やポジティブ日記
毎日「できたこと」や「ありがたかったこと」を3つ書いてみましょう。「散歩できた」「好きな音楽を聴いた」など小さなことで大丈夫です。積み重ねるうちに「自分は意外と頑張れている」と実感できます。
褒め言葉を素直に受け取る
「ありがとう」「助かった」と言われたら「そんなことないよ」と否定せず、「そう言ってもらえて嬉しい」と返してみましょう。
褒め言葉を受け入れることは、自分を認める練習にもなります。
仲間と気持ちを分かち合う
同じ経験を持つ人と話すと「自分だけじゃない」と安心できます。
孤独を減らし、自己肯定感を育むためにも、当事者コミュニティへの参加はおすすめです。
参考リンク:凸凹村(障がい当事者のSNSコミュニティ)
自分を愛するということ|やさしさを自分にも向ける
休むことは“怠け”ではなく“ケア”
「今日は疲れたから何もできなかった」と思う日もあるはずです。
でも、それは「体を大切にできた日」と考え直すこともできます。責めるより、自分をいたわる気持ちを持つことで心は軽くなります。
人に頼る勇気を持つ
「迷惑になる」と思って頼れない人は多いですが、頼られることは信頼の証でもあります。友人や支援者に助けを求めることで、関係はむしろ強くなります。
自分を愛せると、他人も愛せる
自己否定していると他人も受け入れにくくなります。逆に、自分を愛せるようになると、自然と人の良さも見えるようになります。自分を大切にすることは、人間関係を豊かにする基盤になるのです。
障がいがくれる強み|前向きに生きるヒント
工夫する力
生活の中の小さな壁を工夫で乗り越える経験は、柔軟な発想や問題解決力につながります。これはビジネスや日常の人間関係でも大きな武器になります。
共感する力
自分が悩んだ経験があるからこそ、人の痛みに寄り添えます。「わかるよ」と伝えられることは大きな力です。
挑戦する力
障がいがあると当たり前のことも挑戦の連続。その積み重ねは「挑戦を恐れない心」を育てます。
参考動画:NHK「バリバラ」YouTube公式
日常で試したい実践ワーク
鏡の前で「ありがとう」と言う
鏡の自分に「今日も生きてくれてありがとう」と声をかける。少しずつ自己肯定感が育っていきます。
言葉をポジティブに変換する
「歩けない → 移動の工夫が得意」「じっとできない → エネルギッシュ」言葉の変換は心の変換につながります。
SNSや日記でシェアする
前向きな気づきを発信すると、自分だけでなく誰かの励みにもなります。「誰かを元気づけられる自分」という実感が、自分を好きになる後押しになります。
おわりに|自分を愛することが未来を変える
障がいは「マイナス」ではなく「個性のひとつ」。それを認め、好きになり、愛せるようになると、人生の見え方が変わります。
「できないこと」ではなく「できること」「負担」ではなく「強み」
そう思えるようになったとき、世界はもっと優しく広がります。今日から少しずつ、自分に「ありがとう」を伝えてみませんか?

- 身体障がい
- ファッション
車いすだからこそ映えるスタイル|個性と自由を着こなすファッションの楽しみ方
車いすを利用していると、「服が着にくい」「おしゃれできない」と感じることは少なくありません。
ですがその制約の中にこそ、工夫や個性、スタイルの可能性が生まれます。
ファッションは誰もが楽しむ権利。車いすだからこそ似合う、格好よく見えるファッションの可能性を探ってみましょう。
車いすファッションの魅力は「個性」と「自由」
見た目の自由さが生むスタイルの個性
東京・原宿でストリートスタイルを発信している車いすのスタイリスト・徳永啓太さんは、車いすに座ったまま着こなしを楽しむスタイルで注目を集めています。
彼のInstagramは多くのファンを魅了しています。
参考リンク:VogueBlog: https://medium.com/@capsuleringo15Instagram: https://www.instagram.com/keita.tokunaga_/
https://www.youtube.com/watch?v=-IWpsFKEFR0
「車いすだからこそかっこいい」発想の服づくり
日本福祉医療ファッション協会 代表理事の平林景さんは、「車いすだからこそかっこいい」と語ります。
車いすでも着やすく、かつスタイリッシュな服を目指すブランド『bottom’all』は、パリコレ出場へ向けて注目されています。
参考リンク:note(ノート)公式HP:https://keihirabayashi.com/
ファッションが変える“見え方”、そして社会
包括的ブランドの先駆け「tenbo」
ブランド「tenbo」は、障がいの有無に関わらず誰でも着られるインクルーシブな服を展開。
障がいのあるモデルとないモデルを同じ舞台で紹介し、新しい視点をファッション業界に持ち込みました。
参考リンク:Metropolis Japan公式HP:tenbo公式Youtube:https://www.youtube.com/@tenboofficial2414
https://www.youtube.com/watch?v=DLFsYimZxlA
“福祉×おしゃれ”が社会を変える一歩に
“福祉におしゃれは無用”という固定観念を覆す動きも。
平林さんが提案したファッションブランドやその活動は、障がいとおしゃれの垣根をなくし、偏見を変えようとする挑戦の象徴です。
参考リンク:オシャレで変えていく。障害や病気に関わらず、皆が自由に着られる『bottom’all』とは?
車いすユーザー向けファッションの工夫ポイント
着脱しやすく設計された服
車いすに座ったままでも脱ぎ着しやすい服が求められています。
例えば、「bottom’all」は巻きスカートをヒントにして、車いすユーザーが独立して着替えやすい構造を実現しています。
参考リンク:「批判があれば大成功」車椅子ファッションから社会を変えるーーパリコレでショー開催に挑戦する「bottom’all」
高機能とデザインの両立
重度心身障害を持つ方を対象に、機能性とデザイン性を兼ね備えた洋服も進化しています。
見た目にも配慮したデザインで、介助負担を減らしながらおしゃれを楽しめる取り組みです。
参考リンク:「おしゃれをあきらめない」——重度心身障害者の“装う自由”をファッションショーで実現!
ファッションは「自己表現」と「社会へのメッセージ」
見本となるモデルの存在
東京ファッションウィークや国際的な舞台で活躍する車いすのモデルやアーティストは、「車いすだからこそ映える」というポジティブな見本となり、多くの人に影響を与えています。
参考リンク:nationthailand、Vogue
アートでファッションの常識を超える
両足が義足のアーティスト片山真理さんは、義足や服装を創作と美の一部に昇華。
ファッションを通じて身体の多様性を問い、前向きに自己表現する姿は多くの人の「自由」を刺激します。
参考リンク:Accessible Japan、AKIO NAGASWA
https://youtu.be/LHmZePW_SMs?si=QSTJGaWfoohVA10O
まとめ:「車いす×ファッション」は可能性のスタートライン
車いすだからこそ体現できるスタイルや個性がある
包摂的なブランドや活動が、ファッションの常識を変えている
機能性とデザインが両立すれば、おしゃれはさらに楽しくなる
社会へのメッセージとなるファッション表現も可能
車いすと服が組み合わさったとき、そこには“新しい美しい表現”が生まれる可能性があります。
次のファッションシーンで見かけるその姿は、「生きる楽しさの象徴」として輝きを増すことでしょう。
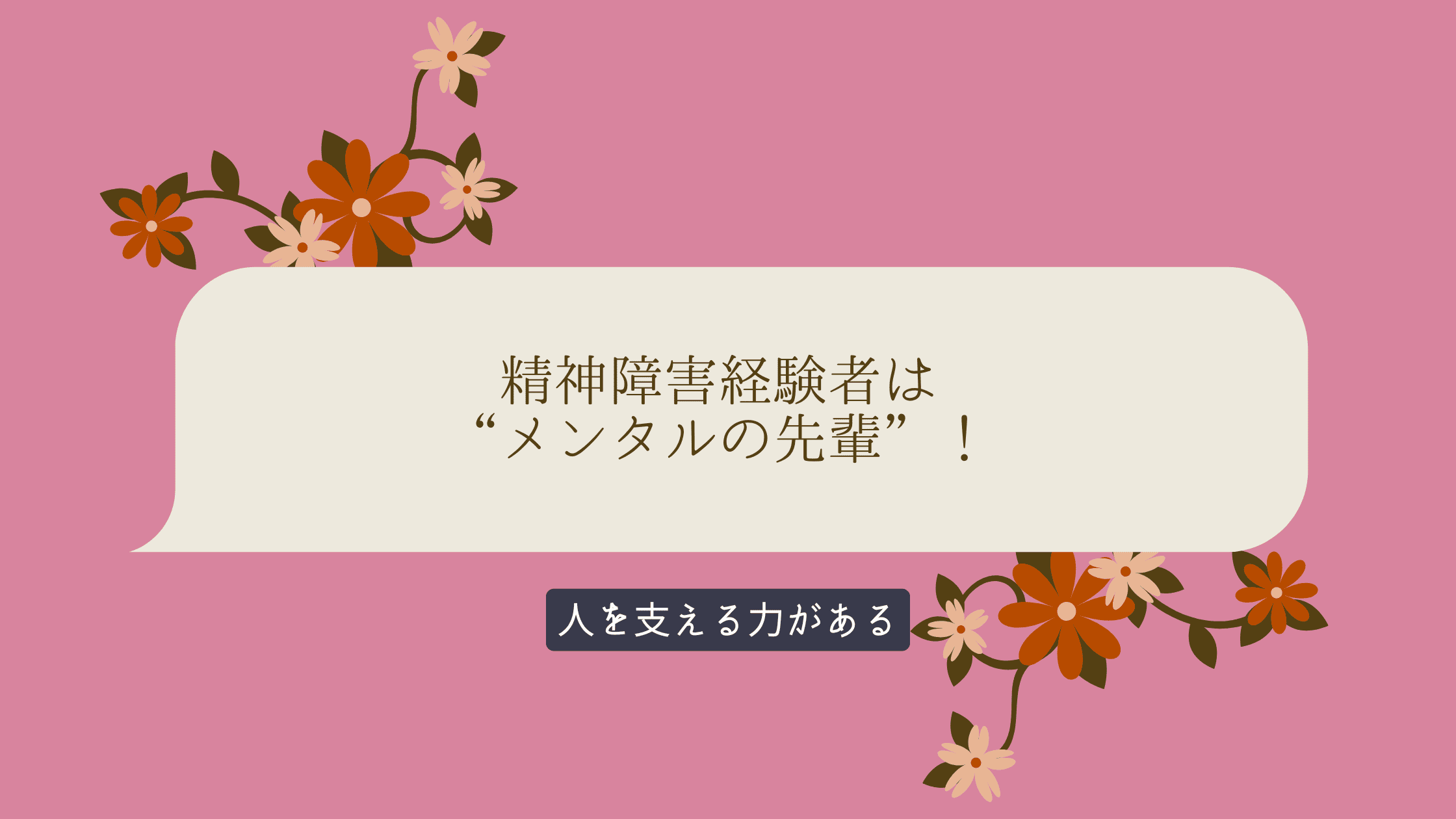
- 精神障がい
精神障害経験者は“メンタルの先輩”!人を支える力がある
はじめに:経験が“支えの力”になる理由
しかしその経験を乗り越えたからこそ見えてくる「支え合いの価値」。
精神障がいは、痛みや困難を伴うものです。
経験した人だからこそ発揮できる共感や気づきが、同じ悩みを抱える人にとっては大きな励みになります。
当事者が“メンタルの先輩”として活躍する価値と背景を探っていきます。
ピアサポートとは何か:経験知から生まれる支援
ピアサポートの源流と日本での広がり
ピアサポートは、1900年代初頭のアメリカで発生した精神科医療への反発から始まり、同じ経験を持つ者同士による支え合いが基盤となっています。
日本ではセルフヘルプグループやクラブハウス形式の活動を経て、リカバリー志向の支援として定着しています。
参考資料: 厚生労働省
当事者自身が「先輩」として活躍する背景
たとえば、ある精神障がい当事者は精神保健福祉士の資格を取得し、大学院で学びながら仲間への講演や執筆を行っています。
こういったおなじ障がいを持つ人が努力する姿に「私も頑張ろう」と感化される仲間も多いです。
参考リンク:ピアサポートとは何か
回復と支え合いのプロセス|支援の質が高まる理由
回復過程で得られる共感力
ある研究では、精神障がい当事者が地域の精神科デイケアを利用する中で「似た立場の人を助けたい」と感じ、自然とピアサポートへの参加が進んだことが明らかになっています 。
自分が回復した経験が他者への支えに変わる心理がここにあります。
参考リンク:SpringerLink
精神的距離の近さが安心を生む
当事者同士だからこそ「言いにくさ」や「遠慮」が少なく、本音が共有できます。
「理解されている」「分かってくれる」安心感は、専門職には真似できない支援の質につながります。
ピアサポートの社会的意義と実践
地方自治体での制度的導入
福島県では、ピアサポーターの養成研修を修了した方を認定し、退院促進や地域定着支援などを担う制度を導入。
地域生活の構築に当事者の回復ストーリーが役立っている事例があります。
参考資料:ピアサポーターを活用した事業事例集
専門職との協働による支援の質向上
精神保健福祉士や看護師など専門職とピアスタッフが協力することで、支援の幅が広がります。
日本の実践例では、専門職がピアスタッフとの協働から得た学びについても報告されています。
参考資料:メンタルヘルス領域におけるピアスタッフとの協働にむけた専門職者の経験
メンタル“先輩”の支えを日常へ活かす工夫
自分の経験を語ることで希望になる
ピアサポーターが自身の回復までの過程を語ることは、同じ苦しみに悩む人に「自分もできるかも」という希望を届けます。
実話としての語りは、最も心に響く支援になります。
支え合いの場を作る意義
グループ形式やコミュニティ形式の支え合いの場では、互いに支え、支えられる関係が生まれます。
「自分も誰かの支えになれる」という体験は、自尊感情と社会参加を促進するのです。
まとめ:“メンタルの先輩”が照らす未来
精神障がい経験者には、自分の経験を活かして人を助ける“先輩”としての価値があります。
その強みをシステムとして活かすことが、誰もが支え合える社会につながります。
アサーションや支援体制と同じように、当事者自身の声と経験をもっと社会に届けていきましょう。
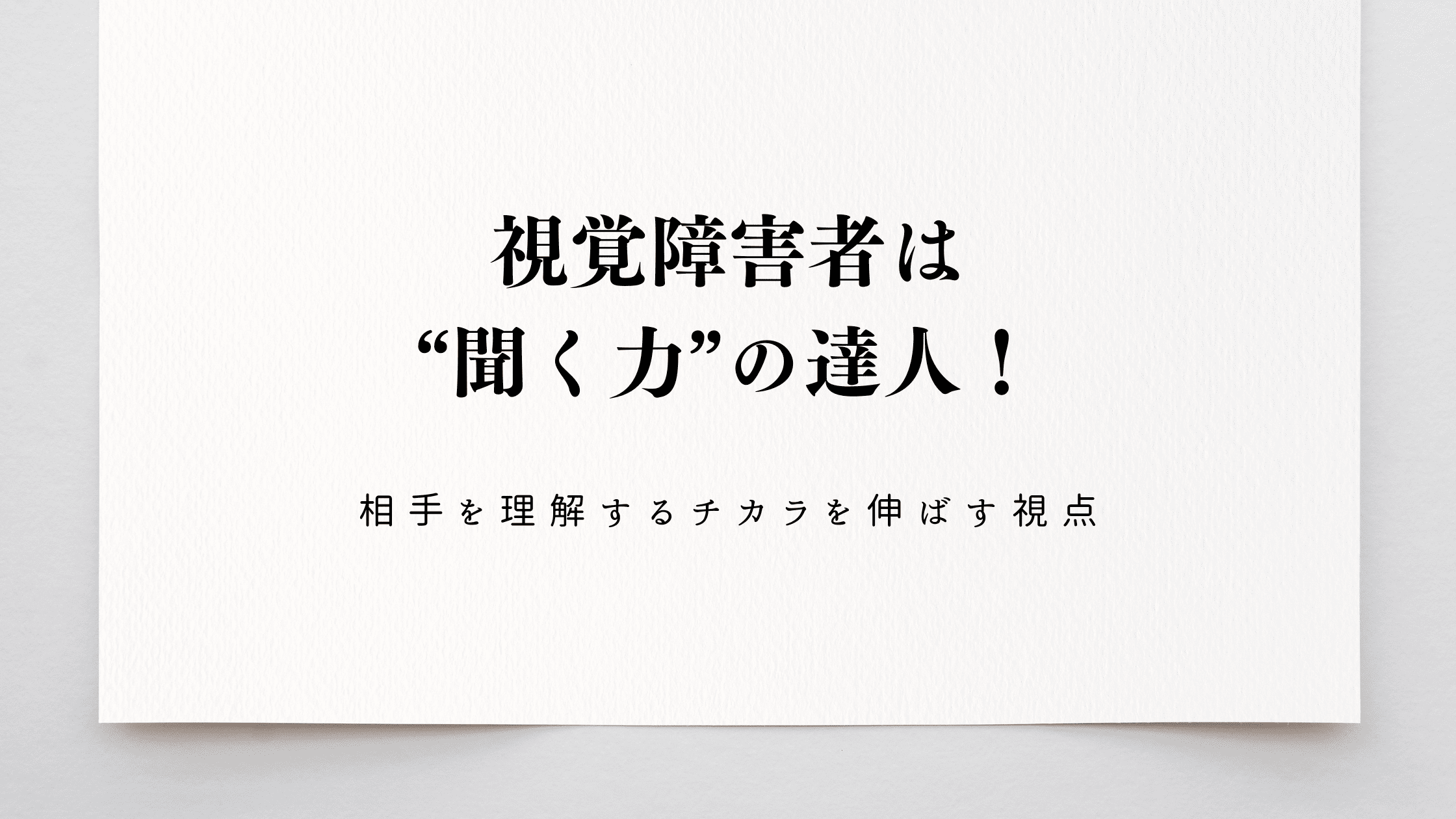
- 身体障がい
- コミュニケーション
視覚障害者は“聞く力”の達人!相手を理解するチカラを伸ばす視点
目に見える世界が制限される中で、視覚障害者は「聴く力」に磨きをかけてきました。
ピッチの違いを識別したり、周囲の音から位置を察知したりする能力は、私たちにはない才能とも言えるでしょう。
この記事では、「聴く力」が生む強みや、それを活かすコミュニケーションや社会参加のヒントを、具体例や研究を交えて紹介します。
聴覚能力の驚くべき鋭さ
ピッチの差を見分ける力の高さ
視覚障害者は、音の高低の変化(ピッチ)を識別する能力が非常に優れており、その速度は視覚保持者の10倍以上にもなるという研究があります。
これは自然と培われた聴覚の鋭敏さといえるでしょう。
参考リンク:視覚障害者の優れた聴覚
頭の動きと両耳聴で障害物を感知
さらに障害物を目で確認できなくても、音や反響を頼りに“障害物の存在”を察知する「障害感覚」が培われます。
頭を動かしながら両耳で聴くと、音源の距離や方向の特定がさらに精度を高めることも確認されています。
https://www.youtube.com/watch?v=BefuWzZq4bU
「聴く力」はコミュニケーションで生きる
書かれた言葉を“音で読む”速さに注目
視覚障害者の中には、音声読み上げの速度を通常より2.6倍速く設定しても理解できる人がいるという報告もあります。
これは、聴く力の高さが情報処理速度にも及ぶ例です。
https://youtube.com/shorts/ucLrGoT7Qyg?si=drY6clK_RkZj-PIs
見えない世界と世界をつなぐ感性
『視界良好2』の著者・河野泰弘氏は、「それぞれの“目”を合わせれば、見えは進化するかもしれない」と述べています。
視覚の制約を、異なる感覚で補い合う可能性と捉える視点は、共生社会の方向性を指しているといえます。
参考リンク:見る力と聞く力:人と世界を共有する道筋
視覚障害者としての一歩としての“聴く力”の発見
noteで視覚障害当事者が綴る文章では、自身の苦手に感じていた「見えづらさ」が「聴く力」という武器に変わった経験が語られています。
自分の中に眠る強みに気づくヒントにもなる言葉です。
参考リンク:見えづらさが教えてくれた、「聴く力」という強み
聴く力が拓く新しい可能性
音があれば楽しめるエンタメも広がる
アメリカでは「Auditory Uta-Karuta」といった、音声でゲーム情報を伝えるよう工夫された視覚障害者向けのゲームが生まれています。
共に遊びを楽しむ文化も広がっていることは明るいニュースですね。
https://www.youtube.com/watch?v=PhW4v1kFwSU
見えなくても伝承できる芸・文化の魅力
盲目の女流歌手・広沢理恵子さんは、視覚によらず伝承されてきた盲人伝統の「行脚芸能」を今に継承してきました。
聴覚や記憶、感受性の力で歴史をつなぐ姿が、多くの人の共感を呼んでいます。
参考リンク:ガーディアン
おわりに:聴く生活が豊かにする“つながり”
視覚障害者ゆえに研ぎ澄まされる「聴く力」は、単なる代替ではなく、豊かなコミュニケーションの源泉です。
音を通じて世界を読み、人とつながり、文化を受け継ぐ――視覚に頼らない“聴く世界”だからこそ見える豊かさがあります。
この記事が、聴くことの力を見直すきっかけになればうれしいです。

- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
- コミュニケーション
介助者との意思疎通を円滑にするアサーションとは
介助を受けながら生活していると、「本当はこうしてほしい」「でも言いにくい」と感じる場面は少なくありません。
逆に介助者の立場でも、「どうサポートするのが良いのか分からない」「遠慮されているのでは」と悩むことがあります。
そんなとき役立つのが「アサーション」というコミュニケーションの方法です。
この記事では、介助者と当事者がお互いに尊重し合い、よりよい関係を築くためのコツを紹介します。
アサーションとは?介助関係に活かせる考え方
自分も相手も大切にするコミュニケーション
アサーションとは、「自分の気持ちや考えを大切にしながら、相手も尊重して伝える方法」です。
単に自己主張するのではなく、お互いが気持ちよくやりとりできることを目指します。
攻撃的でも受け身でもない「真ん中」
・攻撃的な伝え方…相手を傷つけてでも自分の主張を通す・受け身な伝え方…相手を優先しすぎて自分を押し殺す・アサーティブな伝え方…自分も相手も尊重する
介助関係は、相手への思いやりが強すぎて「受け身」になりがちですが、アサーションを意識するとバランスがとりやすくなります。
介助をお願いするときのアサーションの実践法
「事実・気持ち・提案」をセットで伝える
アサーションでは、「事実」「自分の気持ち」「どうしてほしいか」をセットで伝えるとスムーズです。
例)「車椅子を押していただくときに少しスピードが速くて怖かったです。もう少しゆっくり進んでもらえると安心できます。」
これは相手を責めずに、自分の感じたことと希望を伝える方法です。
感謝を添えて伝える
お願いや修正をするとき、「いつも助けてもらってありがたいです」と感謝を言葉に添えると、お互いに前向きな気持ちになれます。
小さなことから練習する
「今日は右側に座ってくれると嬉しい」など、小さなお願いから伝えていくと、アサーションに慣れていけます。
介助を受ける側・する側の両方に大切な視点
受ける側に大切なこと
・「頼む=迷惑」ではなく「頼む=関係を築く一歩」と考える・不安や遠慮をため込まず、少しずつ表現する・自分の希望を伝えることで、相手も安心して介助できる
介助する側に大切なこと
・「何でもやってあげる」ではなく「どうしたいかを聞く」姿勢を持つ・相手の選択や意思を尊重することが信頼につながる・「ありがとう」を受けとめ、自分も無理をしすぎない
共通して意識したいこと
「お互いに支え合っている」という対等な感覚です。介助は一方的なものではなく、信頼と感謝で成り立つ関係性です。
アサーションを学べる実践的なリソース
アサーションは本や講座、動画などで具体的に学ぶことができます。
実際の会話例や実践方法を知ると理解が深まります。
アサーショントレーニングの方法(スマカン)
書籍『改訂版 アサーション・トレーニング』平木典子著
【要約】夫婦・カップルのためのアサーション: 自分もパートナーも大切にする自己表現 【野末武義】(Youtube)
これらを参考にしながら、日常の介助場面で少しずつ実践してみると効果を感じやすいでしょう。
まとめ
介助者との関係は、ただの「助ける側」と「助けられる側」ではなく、対等なパートナーシップとして築いていけるものです。
アサーションを活用すれば、本音を伝えやすくなり、信頼や安心感が深まります。小さな一歩から始めることで、お互いにストレスを減らし、より心地よい介助関係を育むことができます。
「言いにくい」と感じたときこそ、アサーションの出番です。勇気を持って伝えることで、介助の時間がただのサポートではなく「一緒に生きるための大切な時間」に変わっていくでしょう。
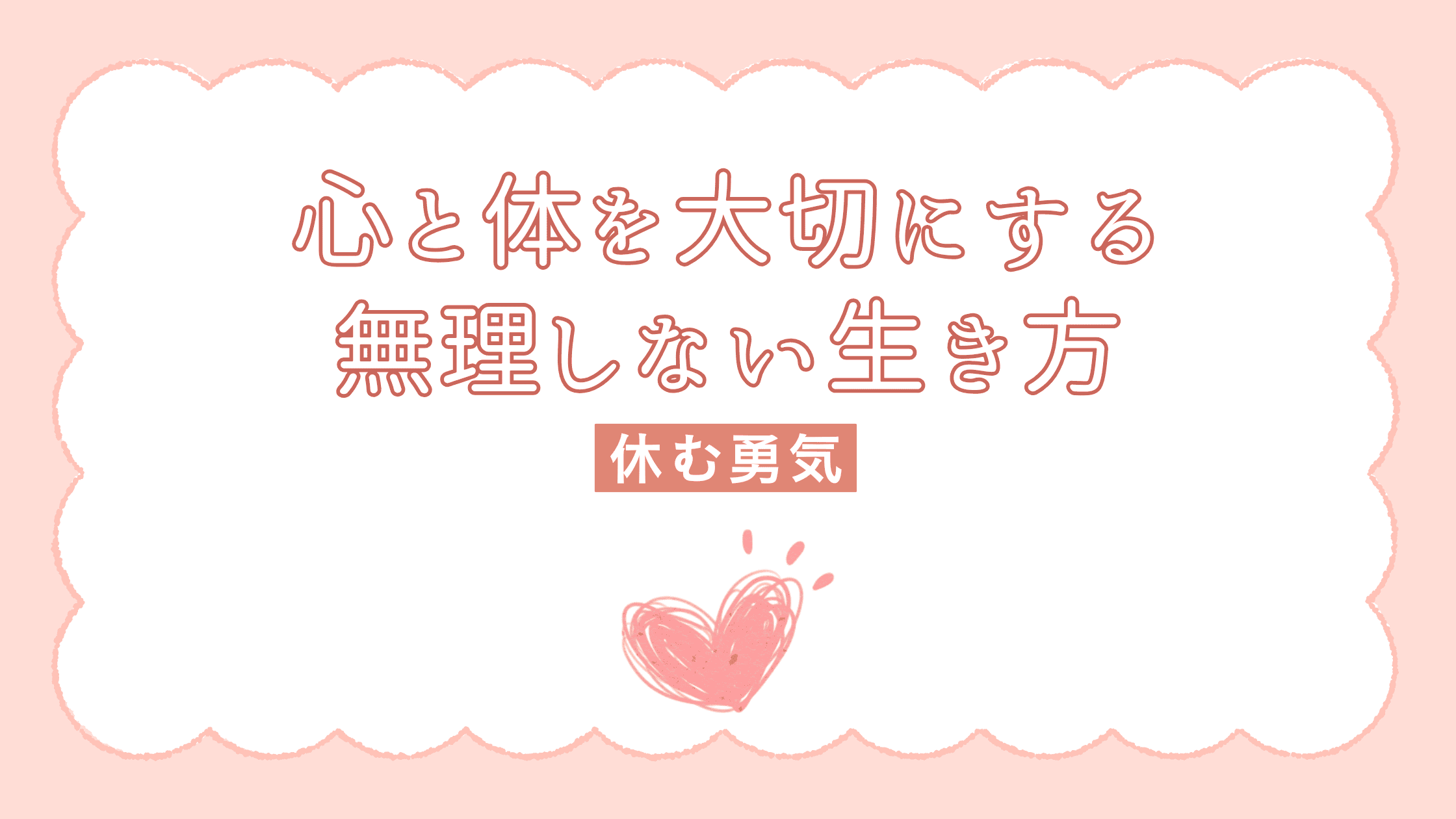
- 精神障がい
- 発達障がい
“休む勇気”心と体を大切にする無理しない生き方
はじめに:「休む勇気」がもたらす、大きな安らぎ
「まだ頑張れる」「他の人に迷惑をかけたくない」──そんな思いから、自分を追い込みすぎてしまうことはありませんか?でも、必要な時にきちんと立ち止まる“休む勇気”は、心身の余裕と人生の質を高める大切な力です。
この記事では、「休む勇気がもたらす心のゆとり」を当事者や専門家の言葉を交えて探っていきます。
休むことへの罪悪感、どう乗り越える?
「休むことはサボりではない」と自分に言い聞かせる
身体を休めないと調子が戻らないことは科学でも明らかになっています。だからこそ、「休むこと=悪」ではなく、「次へのステップ」としての大切なプロセスと捉えましょう。
休む勇気を持って自分を大切にする
心療内科医・鈴木裕介先生も語るように、適切な休息は心身の回復につながる重要な習慣です。焦らず自分に優しく接することが、幸せへの第一歩になります。
参考リンク:専門家が明かす「本当の休み方」。最高のパフォーマンスを引き出す "休養活動" とは?
具体的な「休む勇気」の持ち方と実践方法
小さな休息から始める習慣
1日たった5分、「何もしない時間」を意図的に確保するだけでも、自律神経が整い、心がゆっくり本来のリズムを取り戻します。
感謝日記でポジティブを積み重ねる
感謝日記には「今日はこんなことで救われた」という小さな喜びを意識する力があります。それが日々の幸福度アップにつながることが研究でも指摘されています。
参考動画
https://youtu.be/gAHXHNI0g7c?si=dLh7DXGYc5LU36Xd
休むことが育む、心のゆとりと他者への優しさ
心に余裕が生む笑顔とつながりのやさしさ
ある保育者の体験では、「今日はただ子どもたちと楽しもう」と決めた瞬間から、子どもたちの自主性が自然に引き出されたといいます。自分を解放することが、周囲にも良い影響をもたらすのです。
単なる休息ではなく、“質の回復”が鍵
心療内科医の視点では、深呼吸や自然に触れるなど、心をリセットする工夫が回復力の向上につながるとされています。
参考動画
https://youtu.be/AgtG7fcalVM?si=Vblsj5MTN-zZDGLT
休む勇気が形になった先にあるもの
原貫太さんが語る、罪悪感を超える勇気
適応障害の経験から得た学びとして、「身体が限界を感じたら休むことは恥ずかしいことではなく、むしろ自己防衛である」という深い気づきを得た原貫太さんの体験は、多くの共感を呼びました。
参考リンク:原貫太のブログ
休息が創意・信頼・幸福を生む
休むことで、心に余裕が生まれ、クリエイティブな発想や気遣いが自然とできるようになります。また、周囲からも「頼れる存在」として信頼されるようになります。
まとめ:「休む勇気」は自分を幸せにする選択
休むことは決して怠けではなく、人生を豊かにする力です。
深呼吸や感謝日記など、小さな習慣から心にゆとりをつくりましょう。
自分を大切にすることが、結果として他者にも優しく接することにつながります。
自分との向き合い方を少し変えるだけで、心の余裕と日常の喜びが増えていきます。
「休みたい」が「休んでいい」に変わる瞬間を、あなたの人生にぜひ迎えてください。
関連リンク・参考記事
「休む勇気があなたを守る|休むことに罪悪感を抱いてしまう方へ」https://www.kokoro-odayaka.jp/f-post/25623/
「休む勇気は必要なのか!」(Life Changeプロデューサー・斉藤敏行氏)https://note.com/toshi_saito/n/n3e77ad15808f
「心を休めることの大切さとは?効果的な5つの方法」https://note.com/sakurajpau/n/n8257d87c056b
「休む勇気:立ち止まることも仕事のうち…」https://ameblo.jp/imasami72/entry-12923509664.html
「心身を回復させる本当の休み方とは?心療内科医が教える」https://yoi.shueisha.co.jp/body/mentalhealth/9737/
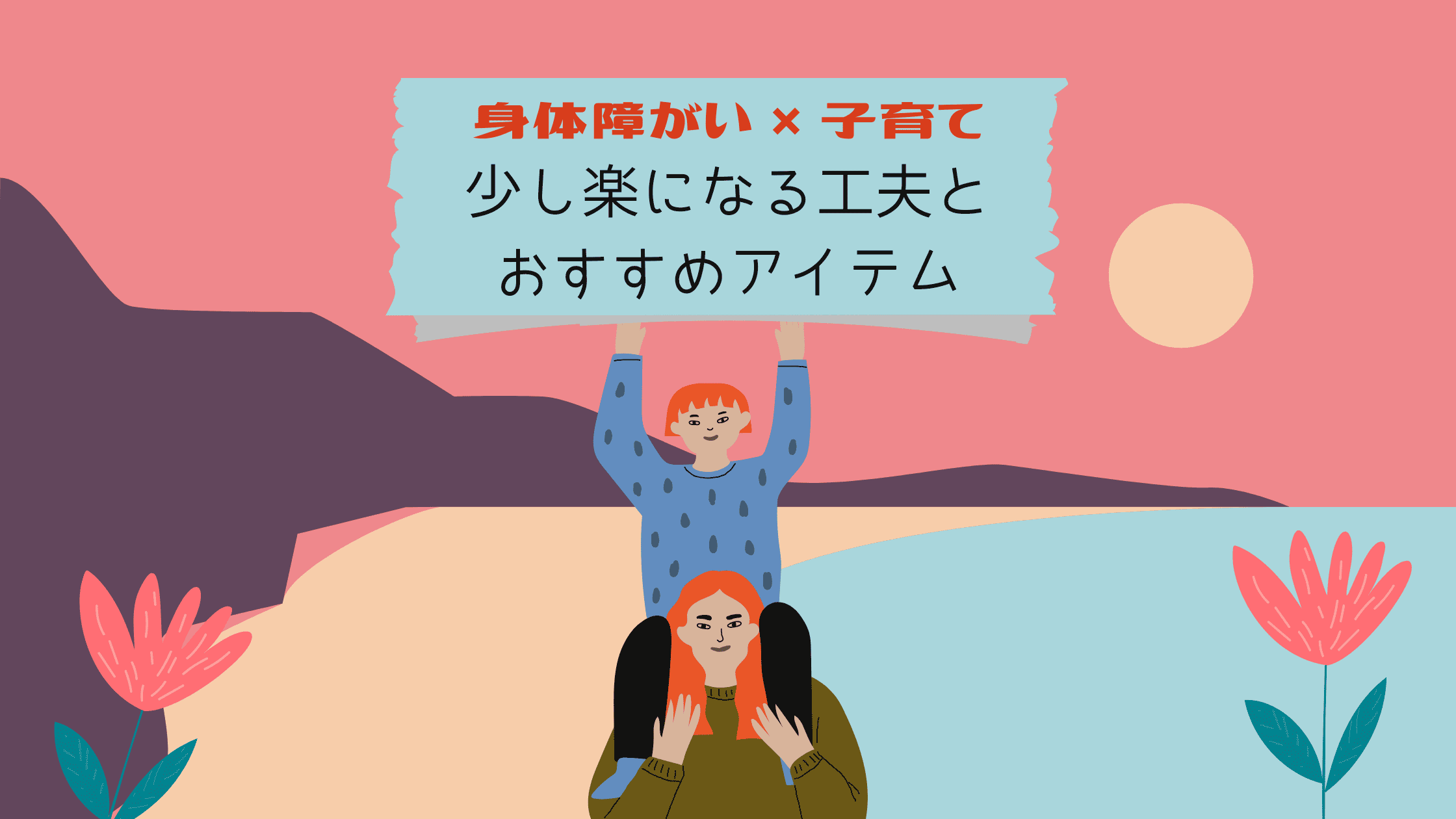
- 子育て
- 家族
- 身体障がい
身体障がい × 子育て|少し楽になる工夫とおすすめアイテム
はじめに:“できない”より“できる”工夫を
身体障がいがありながら子育てをする方は、日々の育児で「こんな工夫があったら楽なのに」「快適に過ごせるアイテムがあったら」と感じる瞬間が多いはずです。
この記事では、そうした親御さんの声に寄り添い、「育児を少し楽にする工夫」と「障がい特性に配慮したアイテム」をたっぷり紹介します。
子育てのヒントを探している方にぜひお読みいただきたい内容です。
身体障がいがある親だからこその工夫とアイディア
環境的な工夫
身体の制約を補うため、家具の高さや配置を見直すことが有効です。
低めの家具や滑りにくい床材に変更するだけで自立支援につながります。
また、子どもの世話がしやすいように、例えばストレッチャーや座位保持椅子を活用するなど、物理的な融通が育児の負担を減らします。
参考リンク:バリアフリーのための家具や設備、家具をもっとインクルーシブに。障がい者の日常を変えるイケアのプロジェクト「ThisAbles」
役割分担の工夫
たとえば入浴や着替えといった動作の多い場面は、可能であればパートナーや家族、支援者に協力を求め、動画や写真を示して意思伝達をスムーズにすると安心です。
無理せず「できるところだけ」やるスタイルを意識しましょう。
参考動画
https://youtu.be/KuQ6LpKS-5c?si=zlw9bb20ws3aV7by
子育てを支えるアイテムのご紹介
授乳や抱っこを助けるグッズ
チェストハーネス型の抱っこひもは、腕への負担を軽減し、片手しか使えない状況でも赤ちゃんを安全に抱けるアイテムとして人気です。
また、授乳用スリングやクッションも、体の負担を和らげます。
参考リンク:『あってよかった!』出産直後に活躍した意外なグッズ
日々の世話や移動をサポートする道具
回転式チャイルドシート:車への乗り降りが自力では難しい場合でも、安全に対応できます。
ベッドや車椅子に適した折りたたみチェア・移乗補助具:小さなスペースで物理的な支えがあると、子どもの移動がラクに。
知識共有と支え合いのネットワークも大切
親同士のコミュニティ、オンラインフォーラム、SNSグループで情報を共有することで、自分に合ったアイテムや工夫が見つかります。
特に障がいを持ちながら子育てする親ならではの「リアルな工夫」が集まりやすく、励みになります。
参考リンク:仲間として支援者として自分らしい子育てを目指して~障害のあるパパママコミュニティ「S・I・O・N(すくすく生きる親の仲間)」立ち上げへの思い~
まとめ:“安心”が生まれる子育ての工夫
日常環境の工夫:家具配置や補助具で動作をラクに
育児アイテムの活用:抱っこひも・回転座席・手作りグッズなど
つながる・支え合う:同じ境遇の親たちの知恵と情報から学ぶ
身体障がいを持つ親御さんにとって子育ては時に挑戦ですが、少しの工夫と適切なアイテム、そして仲間の支えがその重さを軽くしてくれます。あなたの育児のヒントになれば嬉しいです。