NewsNewsみんなの障がいニュース
みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、
コラム形式でわかりやすくお届けします。

- 身体障がい
- 料理
かんたん・時短・みんなで楽しめる片手でできるクリスマス料理&スイーツ
クリスマスが近づくと、キラキラした料理や甘いスイーツの写真を見て「作ってみたい!」と感じる方も多いかもしれません。しかし、片手が使いにくい、握力が弱い、細かな作業が難しい…そういった身体の特性を持つ人にとって、料理はハードルが高く感じられがちです。
でも実は、片手でもつくれるクリスマス料理はたくさんあります。
市販品を活用したり、便利な補助グッズを使ったり、工程を工夫するだけで、“クリスマスらしさ満点の料理” は誰でも楽しめます。
この記事では、
片手でできる簡単クリスマス料理
市販品をアレンジするだけのレシピ
便利な調理グッズの紹介
家族や子どもと一緒につくるための工夫を、分かりやすいステップで紹介します。
片手でできる簡単クリスマス料理アイデア
レンジでできる“ほったらかし”ローストチキン
オーブンで本格ローストチキン…は大変ですが、片手調理なら 電子レンジが最強です。
●作り方のポイント
鶏肉はフォークでところどころに穴をあける
チャック付き保存袋に鶏肉としょうゆ・砂糖・酒・にんにくなどを入れ30分漬ける
30分漬けたものを耐熱皿に出し、ラップをする
レンジ600Wで約15〜20分加熱する
袋に材料を入れるだけなので、包丁もフライパンも不要。レンジに入れる前に「袋から皿へスライドするだけ」なので盛り付けも不要。
●参考リンク
キリンレシピノート「レンジでふっくらローストチキン」
切らない・混ぜるだけクリスマスサラダ
サラダを作りたいときは「切らない」が最強。
●おすすめ食材
ミニトマト(洗うだけ)
ベビーリーフ(袋から出すだけ)
カットサラダ(開封して盛るだけ)
サラダチキン(片手で裂いてトッピング)
赤(トマト)+緑(ベビーリーフ)を合わせると、自然とクリスマスカラーになります。
●ワンポイント
盛り付けをリース型にするだけで一気に“映え”。片手で丸く形作るなら、大きめの皿に外周にそって食材を置くだけでOK。
参考リンク:COOKPAD「クリスマスにぴったり❗️サラダのリース」
片手で作れるポテトグラタン
グラタンもレンジとトースターでクリスマスらしく仕上がります。
●作り方
玉ねぎと鶏もも肉を適当に切る
全ての材料と小麦粉・牛乳・バターなどを入れて混ぜる(2回)
チーズを乗せてトースターで焼く
全て“上からかけるだけ”で完成します。片手で扱いやすい冷凍ポテトは、洗う・切るが不要でとても優秀です。
●参考リンク
フーディストノート「世界一簡単!レンチンして焼くだけ「マカロニグラタン」レシピ
市販品を使った“アレンジするだけ”クリスマスレシピ
市販ロールケーキで“簡単ブッシュドノエル”
工程を少なくするため、市販のロールケーキをそのままデコレーションします。
●手順
ロールケーキを皿に乗せる
ホイップクリームを自由に絞る
粉砂糖で雪を演出したり、好きなお菓子で飾り付け
100円ショップのクリスマスピックを刺してもOK
これだけでクリスマスケーキが完成。火も包丁も使いません。
●参考動画
COOKPAD「クリスマスに♡簡単可愛いブッシュドノエル」
カット済み食材でつくる“手巻き寿司クリスマス”
包丁不要のアレンジ。カット済みの刺身セット・卵焼き・きゅうりスティック・ツナ缶を並べるだけ。
●ポイント
手巻き寿司は「置いて包むだけ」なので片手でも参加しやすい
家族と作業がシェアしやすく、子どもも喜ぶ
赤・黄・緑と色が華やかでクリスマス感が出る
●参考リンク
片手でも料理は作れる「手巻き寿司は片手で作れる」
クリスマスカラーの“簡単パフェ”
市販プリン・ヨーグルト・いちご・グラノーラを「重ねるだけ」。
●片手で盛り付けやすいポイント
コップ型容器を使う
食材は入れるだけ、乗せるだけ
トッピングも市販の物でOK!
少ない動作で華やかに見えるので、パーティにとてもオススメです。自分が食べたいフルーツやお菓子を自由に入れてみましょう!
●参考リンク
COOKPAD「子供と手作りパフェ。簡単です」
片手調理を助ける便利グッズ紹介
使いやすいまな板&固定補助グッズ
片手調理で一番危険でハードルに感じるのは「切る工程」。できれば「切らないレシピ」を選ぶのが安全ですが、それでも必要な場合は補助具が役立ちます。
●おすすめグッズ
食材を固定できる「ワンハンド調理板」
片手で刻んだり混ぜたりできる「ハンディフードプロセッサー&スライサー」
転がりやすい食材を安定させて切れる「まな板」
片手でも扱いやすい調理器具
電子レンジ調理器(パスタ・煮物・蒸し料理)
ワンプッシュで開けられる調味料容器
片手で押さえて使うハサミ型スライサー
これらは、負担を減らすだけでなく、料理の楽しさも増してくれます。
家族と一緒に使いたいアイテム
トング
大きめスプーン
食材を浅く入れられるバット
片手で食材をつまんだり動かしやすい道具は、家族と一緒に調理する際にもとても便利です。
家族や子どもと一緒につくるクリスマス料理のコツ
役割分担のアイデア
料理を「全て1人でやる」のではなく、“得意な部分だけ参加する” ほうが負担が少なく楽しめます。
例:
食材を皿に並べるのはあなた
包装を開けるのは家族
盛り付けは子ども担当
こうすることで、片手でも「自分が作った」という満足感につながります。
共同作業を楽しくする工夫
クリスマスソングを流す
調理工程を写真に撮る
「これ美味しいね!」と声を掛け合う
料理は“コミュニケーションの時間”。できた料理以上に、“一緒に過ごした時間” が宝物になります。
無理しない・疲れないためのポイント
片手調理では、姿勢と疲労がたまりやすいので
座って作業する
調理時間を短めにする
重たいものは持たない
軍手などで滑り防止
を意識しましょう。
まとめ:片手でも、クリスマス料理は十分楽しめる
クリスマス料理は「華やかで大変そう」というイメージがありますが、片手調理でもできる方法はたくさんあります。
切らない
火を使わない
市販品で代用
家族と分担する
そんな工夫を取り入れるだけで、「自分にもできた!」という達成感と、温かい食卓が生まれます。
今年はぜひあなたらしいクリスマス料理をつくって、食べる時間だけでなく“つくる時間”も楽しんでください。
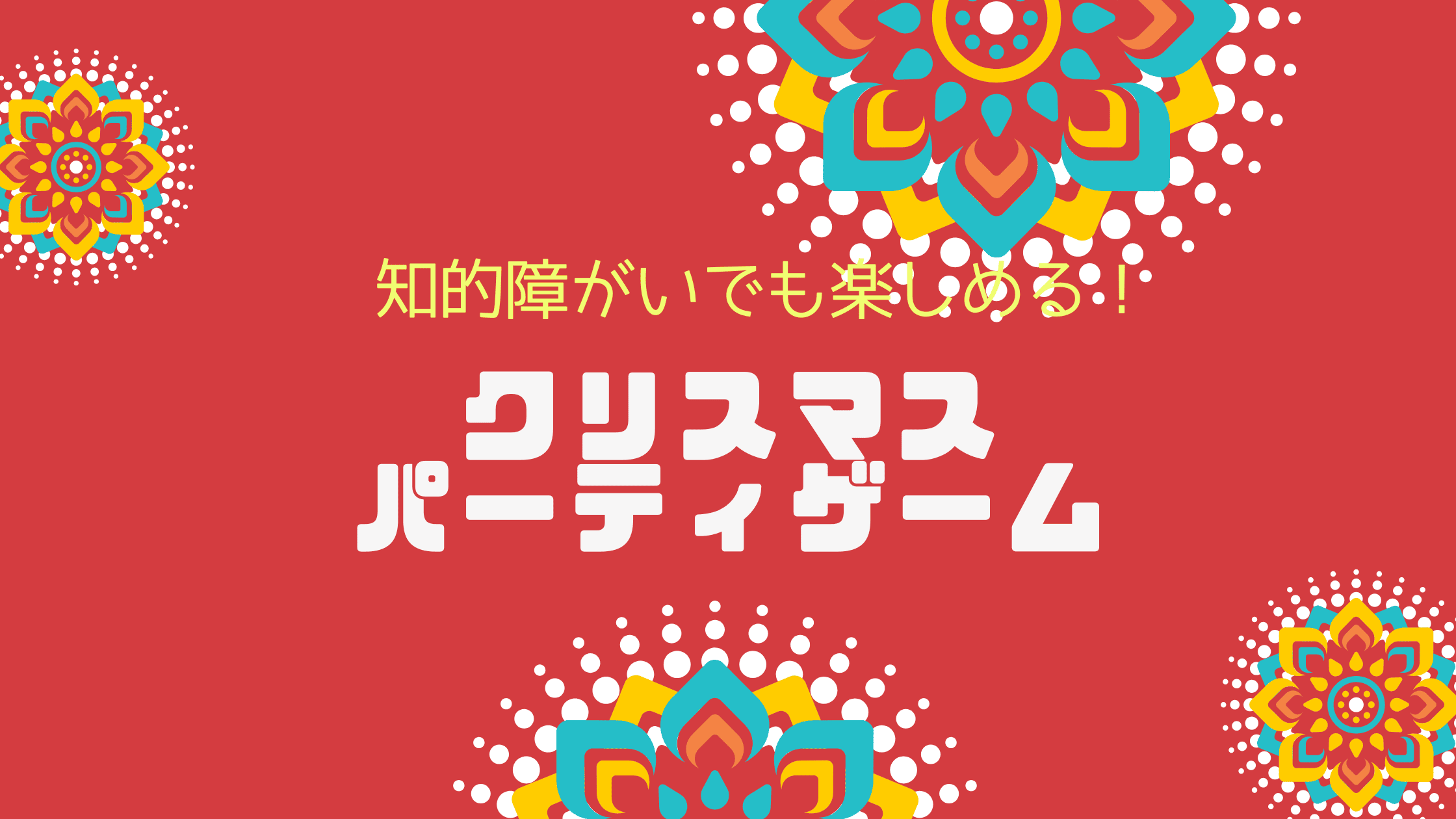
- ゲーム
- 知的障がい
知的障がいでも楽しめる!クリスマスのパーティゲーム
クリスマスパーティーは、ケーキやプレゼントだけではなく、みんなで笑い、動き、つながるゲームでさらに記憶に残る時間になります。
知的障がいを持つ人にとっても、「難しすぎない」「ルールが分かりやすい」「参加しやすい」ゲームは、安心・楽しい時間をつくる鍵です。
本記事では、知的障がいをもつ方とその家族・支援者・友人が一緒に楽しめる、クリスマスパーティー用ゲームを紹介します。ルールの工夫、準備のポイント、動画やリンクも交えて、おうち・施設・地域どこでも使えるアイデアをお届けします。
ゲームを選ぶときのポイント
分かりやすさと参加しやすさ
知的障がいをもつ人がゲームに参加しやすくするためには、ルールが簡潔で、動作が直感的であることが重要です。たとえば「どれだけ遠くへ投げる」ではなく「何色のボールを箱に入れる」など明確な目標があると安心です。
安全性と体力配慮
動きすぎたり、複雑な動きを必要とするゲームでは、疲れやすさ・転倒リスクが増えます。椅子に座ってできるゲームや、声だけで参加できるゲームも検討しましょう。
ゲーム後の振り返り/共有タイム
ゲームが終わったあとは、「どのくらい嬉しかったか」「どうして楽しかったか」を言葉で共有する時間を持つと、参加した実感を味わえます。支援者がその場を促す役を担うとさらに効果的です。
クリスマスパーティゲームアイデア4選
ゲーム1:サンタさんをさがせ!
演出:サンタ帽や赤いマフラー、サンタクロースの人形などを隠して「サンタさんを探してね」と呼びかける。隠れたものを見つけたらベルを鳴らすなど。応用:チーム戦にし、「何個探せるか競う」。レベルに応じて隠す範囲や個数を変える。
ゲーム2:クリスマスの音楽にあわせて椅子取りゲーム
演出:クリスマスソングが流れている間に椅子のまわりを歩き、音楽が止まったときに椅子に座る。回数が増えるごとに椅子を減らしていく。配慮:歩幅を小さめに、座る椅子は背もたれ・肘掛け付きにすると安心。動画参考
https://www.youtube.com/watch?v=hdZpWfeUB7g
ゲーム3:プレゼントボックスリレー
演出:紙箱などにラッピングをして、軽い「プレゼント箱」を手にしてリレー。箱を落とさず次へ渡す。応用:箱の中に「次のチームは〇秒早く」などの指令カードを入れておくと笑いが出る。配慮・工夫:箱は軽量・柔らかい素材。立つのが難しい人は座って参加。参考動画:https://www.youtube.com/watch?v=XfyoIrbI9Eo
ゲーム4:クリスマスクイズ
演出:サンタやトナカイの豆知識・クリスマスの歌・世界のクリスマス習慣などをクイズ形式で出題。応用:難易度を調整して「絵で選ぶ」「音で聴く」など多様な形式に。リンク参考:【クリスマスクイズ 全30問】簡単・子供向け!おもしろ雑学三択問題を紹介
準備と運営のポイント
準備:環境の配慮と道具の工夫
部屋の照明を少し落としてツリーライトを目立たせたり、音量を控えめにしたりすることで“楽しめる空間”を作れます。参加者の特性(感覚過敏・疲れやすさ)を事前に把握し、配慮シートを用意するとスムーズです。
運営:役割分担とサポート体制
ゲームを始める前に司会・ルール説明・補助スタッフを配置すると安心です。座席配置や移動ルートも整理しておくと安全性が高まります。
振り返り&フォロー:楽しかった思い出を共有
ゲーム後に「どれが一番楽しかった?」など感想を言える時間を入れましょう。写真や動画を撮って後日参加者にシェアするのも良い方法です。
よくある質問
Q:どれくらいの時間がベスト?
クリスマスパーティーゲームは、疲れやすい参加者もいるため、1ゲーム5〜10分、全体で30〜40分程度が目安です。
Q:人数が少なくても楽しめる?
はい。3〜4人でもチーム分け(2人対2人)や交替制を使えば十分楽しめます。
Q:オンラインでもできる?
ZoomやLINEなどを使えば、クリスマスクイズなどはオンライン対応版が可能です。カメラを使って景色を共有してもOK。
まとめ
クリスマスは「全員で楽しむ時間」です。障がいがあっても、環境・ルール・道具を少し工夫すれば、誰もが笑顔になれるパーティーをつくれます。
ゲームの目的は勝ち負けではなく「一緒に楽しめたこと」「参加できたこと」が大切。その価値を共有できれば、クリスマスはよりあたたかく、意味のある時間になります。
このガイドを、あなたのパーティー準備の手助けにしてみてください。
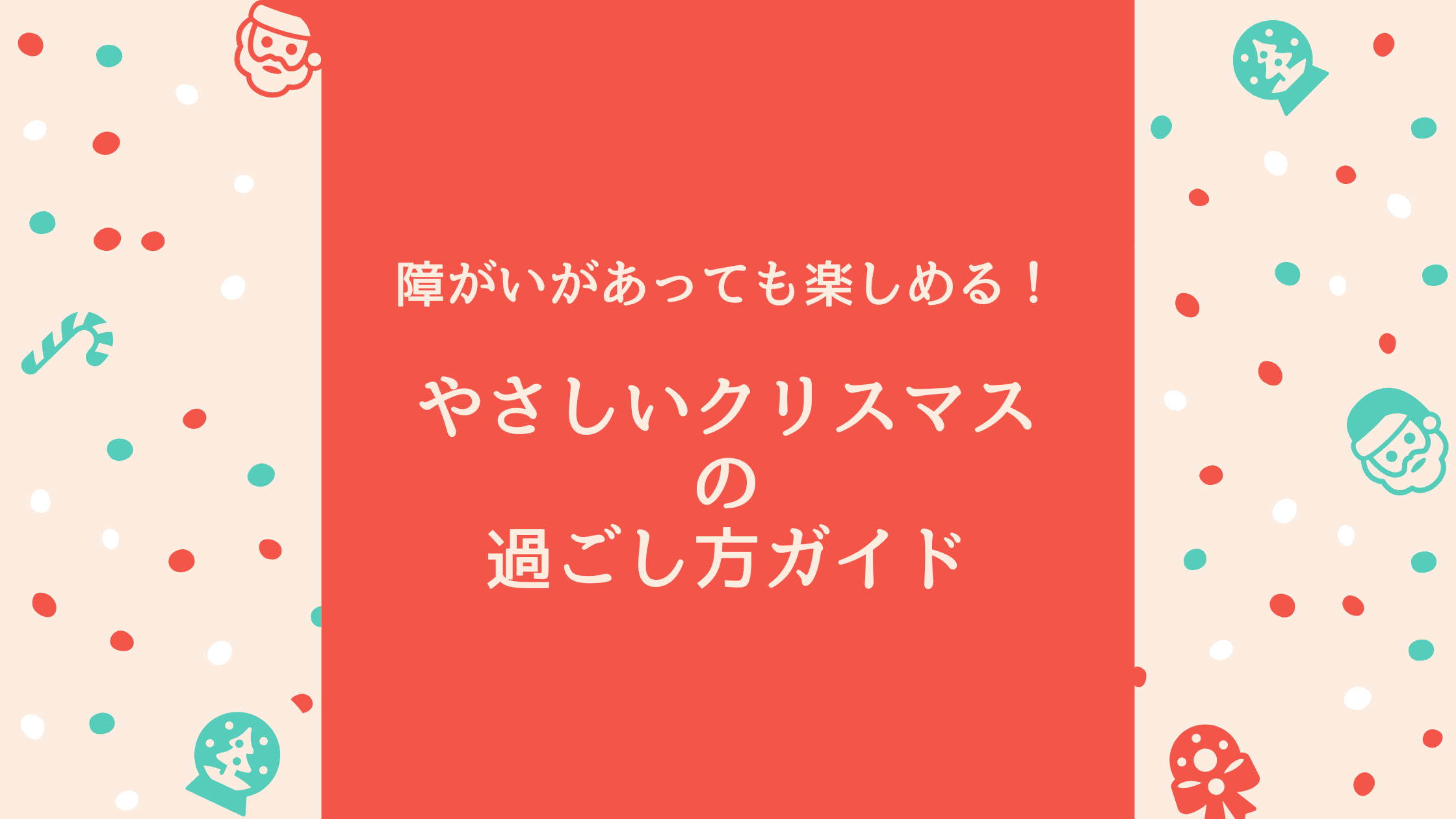
- おでかけ
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 感覚過敏
- 知的障がい
障がいがあっても楽しめる!“やさしいクリスマス”の過ごし方ガイド
クリスマスは、本来「楽しむ日」なのに人混み・音・慣れない予定の増加によってしんどさが出やすい時期でもあります。特に身体障がい・精神障がい・発達障がいがある人にとっては、外出の負担や感覚刺激、スケジュール増加が大きなストレスになることがあります。
そこでこの記事では、「誰でも楽しめる」「無理しないで参加できる」クリスマスの過ごし方を、特性別にわかりやすく紹介します。あなたや家族に合う“やさしいクリスマス”のヒントがきっと見つかるはずです。
クリスマスを“やさしく”するための基本アイデア
静かな場所で楽しむ工夫
騒音が苦手な人向けのクリスマス空間づくり
人混みや大音量が苦手な人は、まず“音量コントロール”を意識するだけで、驚くほど過ごしやすくなります。
イルミネーションイベントに行くなら、混雑が少ない平日の早い時間帯が理想的です。また、家でクリスマスを楽しむなら、照明をこだわるだけでも雰囲気は十分に作れます。
イルミネーションは“下見”と“混雑回避”がコツ
バリアフリー情報が充実している大規模スポットを選ぶと安心です。日本各地のイルミネーション情報は「ウォーカープラス」などで確認できます。https://illumi.walkerplus.com/
他の記事では首都圏のオススメスポットも紹介しています。
https://www.minnanosyougai.com/article1/kurumaisukurisumasu/
無理しない参加方法を選ぶ
「短時間だけ参加」も立派な選択
クリスマスイベントは、最初から最後まで参加しなくてはいけないわけではありません。“行ってみて無理だったら途中で帰る”というスタンスで十分です。特に精神障がい(不安、パニック症状など)がある人は、選択肢を多く持つことが心の余裕につながります。
在宅で参加できる“オンラインクリスマス”の広がり
コロナ禍以降、家から参加できるオンラインイベントが急増しました。手話つきオンラインミサ、オンライン合唱、クリスマスの朗読会など、障がいに関係なく参加できる形が広がっています。
例えば、教会・福祉団体・自治体が配信するオンラインイベントは年々増加していますので、「教会 クリスマス 配信」などで検索してみるのもオススメです。
予定の詰めすぎを避ける
クリスマスシーズンは気づくと予定でいっぱいになりがちです。そのため、あえて予定数を「半分にする」「1日1予定までにする」など、余白を作るだけで負担が減ります。
特性別・やさしいクリスマスの楽しみ方
身体障がいの人の過ごし方
バリアフリーな外出スポットを選ぶ
車いすユーザーや片麻痺の人にとって、段差・舗装・トイレ・駐車場などの環境は大切です。大規模イルミネーションは、ほとんどの会場でバリアフリー導線が整ってきています。
バリアフリー情報を調べるには、以下のサイトが便利です。WheeLog!:https://wheelog.com/ (車いすでも行ける場所を共有するアプリ)
片手で楽しめるクリスマス料理・工作
身体の使い方に制限がある場合でも、片手調理グッズを利用すればクリスマス料理は簡単に準備できます。・片手で使えるまな板・シリコンカップケーキ・市販品+ひと工夫でクリスマス仕様など、無理なくイベント感を楽しめます。
外出が難しいなら“家クリスマス”が王道
家で楽しむクリスマスは、実は一番自由度が高い方法です。照明・香り・好きな映画(音声ガイド付き作品なら視覚障がい者も安心)を活用し、負担の少ない環境でゆっくり過ごせます。
精神障がい(不安・うつ・パニックなど)の人
“人混みゼロ”のクリスマスを選ぶ
クリスマス=外出ではありません。家の中での静かな過ごし方は、むしろ精神的な安定に合っています。
・静かな音楽・温かい飲み物・自分のペースで開けるプレゼントなど「刺激の少ない楽しみ方」に焦点を置くことで負担が減ります。
“孤独感”が出やすい時期こそオンライン交流
精神的な辛さが強い人にとって、クリスマスは孤独感を感じやすい時期です。SNSやオンラインコミュニティでは、クリスマス会・おしゃべり会などを無料で開く団体も増えています。
・NPOのピアサポート・コミュニティの雑談会・YouTubeライブの参加
“距離感のある交流”ができるオンライン空間は、精神的にも優しい場所です。
プレゼントの準備も完璧じゃなくていい
クリスマスの“やらなきゃ”を減らすために「今年はプレゼントなし」「メッセージカードだけ」「後日落ち着いて買う」などの選択肢を持つと気が楽になります。
発達障がい(ADHD・ASDなど)の人
感覚刺激を抑えたクリスマス環境づくり
発達障がいの中でもASD傾向のある人は、光や音の刺激が大きいと疲れやすくなります。そのため、照明を控えめにしたり、静かなクリスマスミュージックをかけたりすると安心しやすいです。
参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=amBrquOaXQ4
ADHDの“うっかり”を減らすクリスマスの工夫
ADHDの人は・プレゼントの買い忘れ・予定のダブルブッキング・準備の先延ばしが起こりやすい傾向があります。
そのため、・買い物は「前日まとめ・リマインダーセット」・予定は「紙カレンダー+スマホ」・装飾は「最低限の1セットを毎年使う」など、負担の少ない仕組みづくりが大切です。
ルーティンが崩れがちな時期こそ柔軟に
発達障がいの人は、日常のリズムが乱れると不安が強まります。クリスマス時期だけ「特別なスケジュール」を目に見える形で作っておくと、安心できます。
家族・友人との過ごし方の工夫
“できることベース”で役割を決める
障がいがある人に「無理な役割」を与えると負担になります。「できること」をベースに役割分担をすると、助け合いながら楽しめます。
例・片手が使いづらいなら飾り付けは家族が担当・精神的に不安定なら準備は最小限に・感覚過敏があるなら環境調整を家族がサポート
静かで優しい時間を一緒に作る
クリスマス=派手なイベント、という固定概念は捨てましょう。一緒に温かい飲み物を飲むだけでも立派なクリスマスです。
“支える・支えられる”の両方が自然でいい
障がいがある人でも大切な人たちを喜ばせることはできます。歌、メッセージ、動画編集、料理の盛り付け…小さなことが“贈り物”になります。
まとめ:クリスマスは“無理しない幸せ”で十分
障がいがあっても、クリスマスの楽しみ方は無限にあります。大切なのは「できる方法で楽しむ」「無理をしない」「心地よさを大事にする」この3つだけです。
クリスマスは“特別な日だから頑張る日”ではなく、“自分を大切にする日”でもあります。今年はぜひ、あなたにとって一番優しいクリスマスを選んでください。
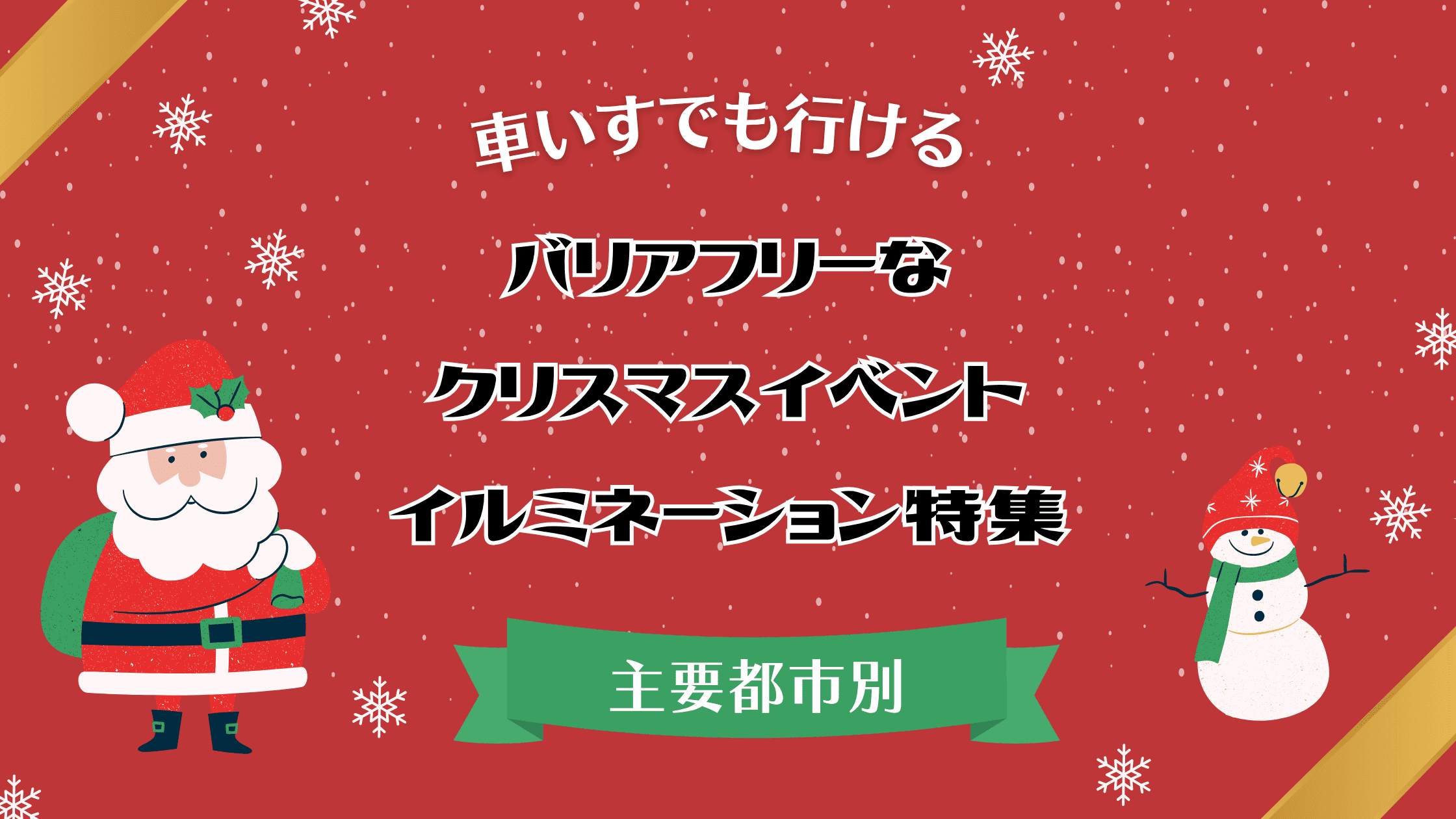
- おでかけ
- 趣味
- 旅行
車いすでも行ける!バリアフリーなクリスマスイベント・イルミネーション特集|主要都市別アクセスガイド
クリスマスの街は心が躍るものですが、車いすユーザーにとっては「段差は?」「人混みは?」「トイレは?」と、楽しむ前に不安が先に立つこともあります。
しかしここ数年、日本のイルミネーションやクリスマスイベントはバリアフリー化が進み、「ぜひ来てほしい」という姿勢がハッキリ見える場所が急増しています。
この記事では、✅ 車いすで行きやすいクリスマスイベント✅ 主要都市(東京・大阪・福岡)のバリアフリー状況✅ 実際のアクセス方法・混雑状況への配慮ポイントを中心に、安心してお出かけできる情報をまとめました。
今年は「行けるか不安」ではなく、「ここに行きたい!」が選べるクリスマスを楽しみませんか。
東京|設備もスタッフサポートも充実したイベントが多い都市
東京ミッドタウン(六本木):バリアフリー整備が行き届いた都会の光
車いすでも安心
東京ミッドタウンの「MIDTOWN CHRISTMAS」は毎年大人気。敷地全体が段差の少ない構造で、トイレ・エレベーターも豊富です。
・外苑東通り側エントランスは完全フラット・ガーデンエリアの通路は舗装されており、車いすが進みやすい・スタッフ数が多く案内が丁寧
12月19日(金)~25日(木)混雑が予想されますが、12月18日(木)以前なら比較的スムーズに楽しめます。
公式案内:https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/
アクセスのしやすさ
・都営大江戸線「六本木駅」8番出口直結(エレベーターあり)・日比谷線からも地下通路で移動可能
現地の雰囲気が伝わるYoutube動画はこちら
https://youtu.be/Duwup9PPdYQ?si=H0qnMm1ILwn5zv90
東京スカイツリータウン ドリームクリスマス
車いすで動きやすい広い動線
東京スカイツリータウンは、商業施設・広場・展望台のどこも広い通路とエレベーターが豊富です。夜間も明るく、安全に移動できます。
・ソラマチ1階〜4階すべてエレベーター接続・スカイツリー展望台のバリアフリー案内も充実・クリスマスマーケットは比較的回遊しやすい配置
公式案内:https://www.tokyo-skytree.jp/event/info/xmas2025
アクセス
・東武「とうきょうスカイツリー駅」すぐ・半蔵門線「押上駅」はエレベーターが複数あり移動しやすい
現地の雰囲気が伝わるYoutube動画はこちら
https://youtu.be/emDEQxQEzDs?si=1zyz4VidRT45FKc-
大阪|「歩きやすさ・見やすさ」を考えたイルミネーションが多い
大阪・光の饗宴(御堂筋イルミネーション)
道幅が広くて車いすで動きやすい
御堂筋イルミネーションは歩道がとても広く、車いすでもゆったり通れます。数キロにわたる光の道を、好きな距離だけ楽しめるのが特徴です。
・歩道は平坦で舗装が良い・休憩できる場所が多い・混雑が分散しやすく安心
公式サイト:https://hikari-kyoen.com/
アクセス
区間が長いため、どこからでも参加可能。最寄り駅の多くがエレベーターを設置しています。
現地の雰囲気が伝わるYoutube動画はこちら
https://youtu.be/9ERF8VkqqNM?si=UeFmG1Kp_kM-EXl3
大阪城イルミナージュ:段差少なく広い園内が魅力
歴史的建造物のバリアフリー工夫
大阪城公園は段差が少なく、イルミネーション会場も車いすで回りやすい動線が整っています。
・園内は舗装済み・臨時スタッフは誘導が丁寧・天守閣付近のスロープも幅が広い
公式情報:https://illuminage.jp/
●アクセス
・JR大阪城公園駅にエレベーターあり・大阪メトロ「森ノ宮駅」もバリアフリー対応
現地の雰囲気が伝わるYoutube動画はこちら
https://youtu.be/f45jiCL6cOQ?si=NkfoNwrICoGJPFLI
福岡|イベントの“距離が近い”から楽しみやすい街
アクロス福岡「こびとの森イルミネーション」
車いすで安心できる理由
アクロス福岡は福岡市の文化施設で、館内も外周もバリアフリーが行き届いています。
・入り口から会場までフラットな動線・館内に複数の車いす対応トイレ・天神地下街から地上までエレベーターで接続
イルミネーションは大規模過ぎず、動きやすい規模のため、長距離移動が不安な方や、疲れやすい方にも優しい設計です。
公式サイト:
アクセス
・地下鉄「天神駅」16番出口から徒歩すぐ・地下街と直接接続して雨の日も安心・周辺にカフェが多く休憩しやすい
現地の雰囲気が伝わるYoutube動画はこちら
https://youtu.be/8wUQNfNRSJI?si=aODu48sbDDXpJ1RD
福岡クリスマスマーケット|ローカルで温かい雰囲気
●車いすで回りやすいレイアウト
福岡クリスマスマーケットは会場が点在していますが、導線が広めで移動しやすいのが特徴です。
・動線に余裕がある・平坦で坂や段差が少ない・屋根ありエリアもあって雨でも安心
公式:https://christmas-advent.jp/
車いすでイルミネーションを楽しむためのポイント
人混みを避ける“時間帯選び”
・平日18時前・土日の開場直後この2つは比較的スムーズに見て回れます。
暖かい場所で休憩を挟みながら
イルミネーションは冬のイベント。カフェや商業誌悦など、近隣の施設を事前チェックしておくと安心です。
現地スタッフに声をかける勇気
バリアフリーイベントはサポート体制が整っていることが多く、「混雑を避けたい」「近いルートで見たい」なども丁寧に案内してくれます。
まとめ:車いすでも“行ける場所”はこんなにある
バリアフリー化が進んだ日本。車いすユーザーが「行きたい」と思った時に気軽に足を運べる場所が確実に増えています。
大事なのは、・無理のないペースで楽しむ・安心できる会場を選ぶ・サポートのある場所から挑戦する
今年はぜひ、光の中をあなたのペースで歩いてみてください。クリスマスがもっと近く、もっと優しいものになりますように。
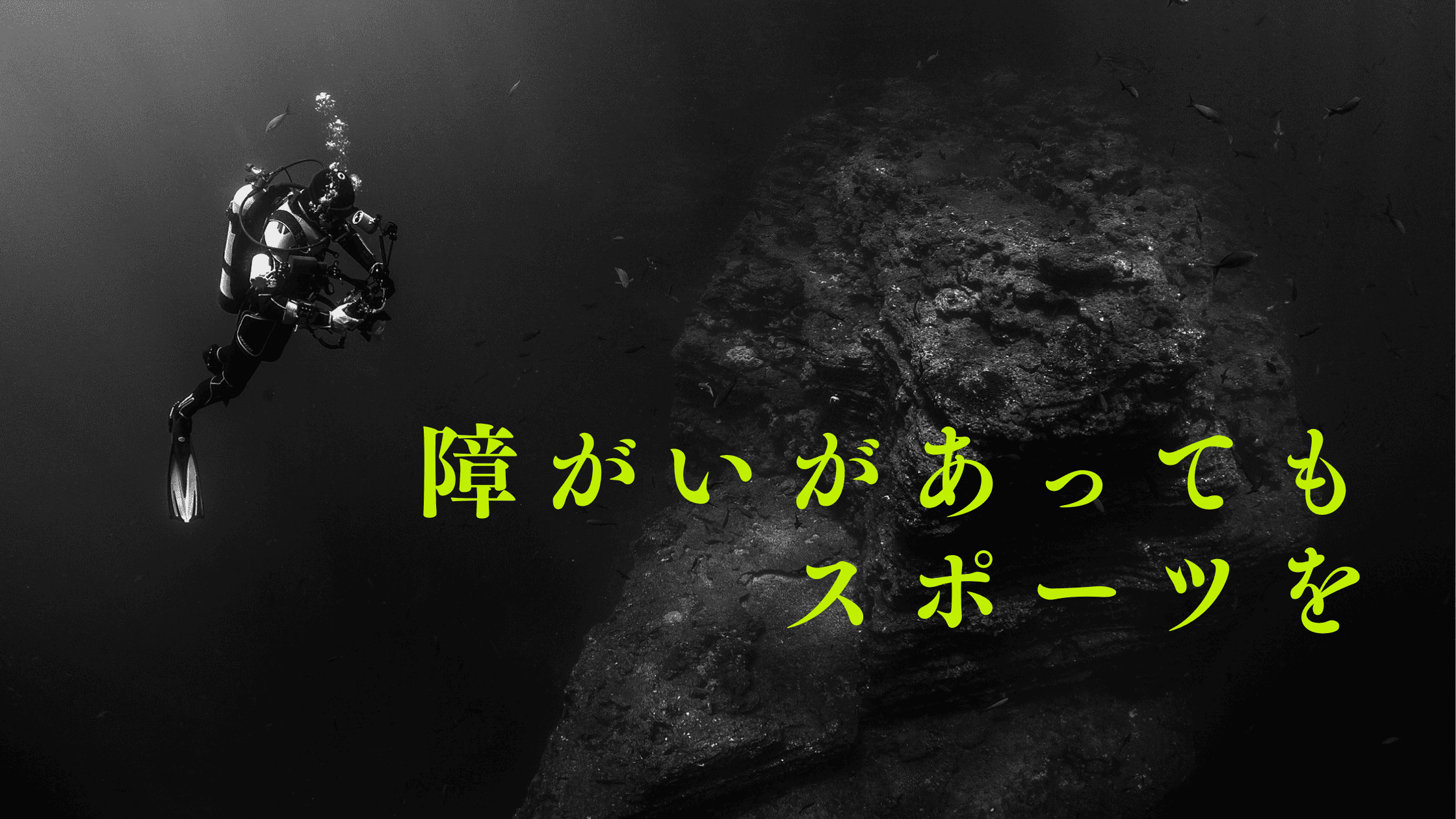
- スポーツ
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
障がいがあってもスポーツを
「スポーツをやってみたい。でもハンディキャップがあるから…」そんな風に思っていませんか?実は、障がいのある人にこそ取り組みやすく、多様な楽しみ方ができるスポーツの世界があります。
義足や車いす、視覚サポート、ルールの調整がなされた「パラスポーツ」「障がい者スポーツ」と呼ばれるものです。
この記事では、まず障がい者スポーツとは何かを整理し、続いて代表的な競技をジャンル別にご紹介。さらに、参加を始めるためのステップや注意点も解説します。
スポーツが“遠い世界”ではなく「私にもできること」になるヒントが見えてくるはずです。
障がい者スポーツとは何か
定義と背景
障がい者スポーツ(アダプテッドスポーツ、パラスポーツなどとも呼ばれ)とは、障がいがあってもスポーツ活動に参加できるよう、競技規則・用具・環境を「調整・適応」したスポーツを指します。
たとえば陸上や水泳といったオリンピック種目をベースに、車いす使用・義足使用・視覚障がい用の支援などを加えたものが多く紹介されています。
なぜ“参加”が拡大しているのか
国際的な障がい者スポーツ大会(パラリンピックやデフリンピック、スペシャルオリンピックスなど)を契機に、障がいを持つ人のスポーツ参加が注目されてきました。
日本では文部科学省・スポーツ庁が「障害者スポーツの普及促進・競技力向上」を掲げています。
クラス分け・用具の工夫とは
障がいの種類や程度が異なる選手が公平に競えるよう、各競技には「クラス分け」の制度があります。
例えば用具を使った車いす競技や義足競技では、障がいの影響を最小限にしつつ“実力で競う”環境が整えられています。
ジャンル別代表種目を知ろう
車いす・義足・座位など身体障がい中心の競技
車いすバスケットボール:コートやゴールは一般と同じ。ただし車いすを用い、点数制限(持ち点制度)で障がいの度合いを調整。
ウィルチェアーラグビー:「車いすラグビー」とも呼ばれ、激しいコンタクトありのスポーツ。
車いすテニス・義足陸上・車いすマラソンなど:一般種目をベースに適応されている。たとえば陸上競技では義足・車いす・視覚障がい者用の種目あり。
ボール・的当て・協働性が高いスポーツ
ボッチャ:重度四肢機能障がい者も参加しやすく、自分のボールを「ジャックボール(白色)に近づける」ことを競う戦略性の高いスポーツ。
ゴールボール:視覚障がい者用。音の出るボールを使い、チームでゴールを競う。
座位バレーボール・5人制サッカー(ブラインドサッカー)なども紹介されています。
水上・アウトドア・多様な環境でのスポーツ
カヌー、サイクリング、馬術、射撃など:障がいの種類に応じ用具やコースが調整されています。
海・山などにも展開されており、アウトドア志向の方にも楽しみの幅が広がっています。
“やってみたい”を後押しする体験・観戦の切り口
競技に参加するだけでなく、まずは観戦や体験会に参加するのもおすすめです。
例えば、社会人320名アンケートでは「東京パラリンピックで観戦したい競技」の第1位に車いすバスケットボール、第2位にボッチャという結果が出ています。
スポーツを始めるためのステップとポイント
ステップ① 興味ある競技を“体験”してみる
まずは「気になる競技」を見つけ、地域の障害者スポーツセンターや体験会に参加してみましょう。
全国に障害者スポーツ専用施設・優先利用施設が数多くあります。
ステップ② 自分の体・障がいの特性を知る
競技を選ぶ際、自分の身体の使いやすさ、移動手段、用具の準備などを考えることが大切です。
たとえば車いす移動が多い場合は車いす競技、水や泳ぎが得意なら水泳競技など。
ステップ③ 継続・仲間づくり・目標設定
スポーツを続けるためには、「仲間と一緒に」「目標を持って」「楽しめる環境で」行うことが鍵です。
クラブ活動や地域チーム、支援団体を活用して、環境を整えましょう。
注意点:安全・ルール・用具の確認
障がい者スポーツにはルール・用具の適応があり、身体や感覚に配慮が必要です。
参加前には障がいの特性・健康状態・用具のフィットを確認すると安心です。
よくある質問と“やってみたい”人へのヒント
Q:障がいが重くても参加できる競技はありますか?
はい。例えばボッチャやゴールボールは比較的重度の障がいがあっても取り組みやすい競技です。
始める前に「用具レンタル」「補助者あり」の体験会を調べましょう。
Q:用具・費用はどれくらい必要?
競技によって異なりますが、初期はレンタルや体験会で“まずは参加”がおすすめです。
クラブで共有用具を使えるケースもあります。
Q:観戦だけでも楽しめますか?
もちろんです!
パラスポーツの“スゴ技動画”や紹介動画も沢山あり、興味を持つきっかけになります。
まとめ:スポーツを通じて見える“自分らしさ”
障がいがあってもスポーツは、“できること”を発見し、“仲間”とつながり、“挑戦する喜び”を得る場になり得ます。競技を選ぶことも、始めることも、誰かのためではなく“自分が楽しむ”ためのもの。
まずは「体験する」「続けてみる」「自分なりの形をつくる」の3ステップからスタートしてみましょう。
スポーツが、あなたの可能性をひらく鍵になるかもしれません。
🔗参考リンク・動画
障害者スポーツとは(大分県障がい者スポーツ協会) https://oita-syotaikyo.org/what-is-syospo/
パラスポーツ競技紹介 https://parasports-start.tokyo/sports/
動画+解説で知る!車いすバスケットボール https://www.parasapo.tokyo/topics/109017
障害者スポーツ – スポーツ庁(文部科学省) https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop06/1371877.htm

- 福祉
- 身体障がい
- 仕事
世界と比べてどう?日本の身体障がい者支援を考える
日本では「バリアフリー」「障がい者雇用促進」といった言葉が当たり前になっていますが、世界の先進国やアジアの国々と比べたときに、どこが優れていて、どこに課題が残されているのでしょうか。
特に身体障がいを持つ人々の支援・社会参加という視点から、制度・就労・暮らし・権利保障など多角的に見ていきます。
日本の支援制度の概要と歴史的背景
日本における制度のスタートと変化
戦後まもなく、身体障がい者福祉法(旧法)が制定され、障がいを持つ人々への福祉支援の基盤が整備されました。
例えば、1960年代以降、障がい者自立生活運動なども生まれ、制度や支援のあり方に変化が見られています。
障害者雇用促進法と法定雇用率制度の構図
日本には、一定規模以上の企業に身体・知的・精神障がいを持つ人の雇用を義務付ける法定雇用率制度があります。
最近では2026年7月から民間企業の障がい者雇用率が 2.7% に引き上げられる予定です。
制度の枠組みと国際的な流れ
国連の 障害者権利条約(CRPD)を受けて、「障がい=個人の問題」から「障がい=社会のバリアによるもの」という社会モデルへの転換が世界的に進んでいます。
日本でもその動きが出ていますが、制度設計には医療・リハビリ重視の「医学モデル」の影響が根強いとの指摘があります。
世界との比較から見えた日本の強みと弱み
強み:従来制度の整備と社会的認知
日本には身体障がい者に対する福祉制度、障がい者手帳・等級制度、障がい者雇用義務などの制度が比較的早期に整っており、ある種の「制度基盤」が存在している点は強みといえます。
例えば、「Japan: People With Disabilities」では障がい者支援制度の概要が紹介されています。
弱み:就労・社会参加の実態と制度適用のギャップ
制度はあっても実際の社会参加や就労の実績では、他の先進国と比べて「対象範囲」「参加度」「選択肢の多様性」に課題があります。
例えば、日本の法定雇用率 2.3 %などは、フランス 6 %、ドイツ 5 %と比べると低く、支援対象も「より重度」の障がい者に偏っているという分析があります。
比較から浮かび上がる“アクセスと質”の差
障がいを持つ人が医療・福祉・地域生活サービスにアクセスする際、日本では「専門家が少ない」「相談窓口がばらばら」「地域格差がある」などの質的課題が報告されています。
例えば、身体障がい者と健常者の医療体験(patient experience)を比較した研究では、障がい者は「継続性」「地域対応」「サービスの包括性」の面で劣っていたことが示されています。
日本が抱える「身体障がい支援」の主要な課題
就労機会の限定と“形式的達成”の問題
法定雇用率があるにも関わらず、多くの企業がその達成に向けて「簡易作業」「別枠雇用」など限定的な雇用形態にとどまるという批判があります。
実際、2024年の報道でも「全企業のうち46%しか達成していない」とされ、数値上の達成だけでは実質的インクルージョンが進んでいないことが指摘されています。
障がいの幅・適用範囲の制限と対象格差
日本では支援の対象となる「障がい者」が法律上・制度上「一定の等級・レベル」を満たす必要があるケースが多く、他国と比べて“軽度障がい”や“支援が必要だが制度対象外”の層が見えにくくなっている点も課題とされています。
比較研究によれば、日本は「機能障がいがより深刻な人」に制度が寄っているという指摘があります。
地域間・サービス間の格差、生活支援の難しさ
地域によっては交通・建物・福祉サービスのバリアが未だ残っており、「障がいがあるから外出しづらい」「地域サービスが整っていない」といった声があります。
例えば「Top Most Disability-Friendly Countries Guide」では、日本は改善されつつあるが「アクセスに難あり」とも指摘されています。
今、世界が進めている支援の潮流と日本にとってのヒント
アンチ差別・合理的配慮を中心に据える動き
欧米では、雇用義務制度(クオータ制)から「合理的配慮」「差別禁止」を柱とした制度へと移行が進んでいます。
日本も2021年改正障害者雇用促進法で“合理的配慮”が企業義務化されましたが、実践に至るまでにはまだ課題があります。
Lived-experience(当事者経験)を政策・実践に活かすモデル
海外では障がい当事者自身が政策立案・支援サービス設計に参加することで、より実効的な支援が生まれています。
日本においても「当事者参画」の重要性が強調されており、支援の質を高める鍵となっています。
“インクルーシブ社会”を意識した環境整備・テクノロジー活用
アクセシビリティ(交通・建築・サービス)やICT/アシスティブテクノロジーの活用は、身体障がい者の自立と参加を促す上で、世界的にも重要なテーマです。
日本もそのトレンドに乗りながら、更なる整備が求められています。
身体障がい者支援をより良くするために、私たちにできること
支援制度を知り、自分ごととして捉える
まずは自分の住む地域・職場・学校でどのような支援制度があるかを把握することが大切です。
そして「制度を利用する・活用する」視点だけでなく、「制度を改善していく」視点も持つことが、持続可能な支援につながります。
発想を「支援される側」から「共に創る側」へ
身体障がいを持つ人を“支援される存在”とだけ捉えるのではなく、「共に働く」「共に暮らす」「共に支える」という視点を持つことで、社会の在り方が変わっていきます。
企業・地域・個人が“当事者中心”の視点を持つ
企業には、雇用率の達成以上に「働きやすい職場」「キャリアを描ける雇用」を問いかけたいです。地域・学校・自治体には、「障がいがある人が“普通の生活”を送れる環境」という観点を強めていきましょう。
個人としても、「身体障がい者も当たり前に参加している世界」を意識した行動・理解が重要です。
まとめ:制度・実践・意識がそろってこそ“支援の質”が変わる
日本の身体障がい者支援には、制度的な基盤が整っているという面があります。
一方で、就労・地域参加・多様な障がい度合いへの対応・アクセス整備といった“質”の面では、世界と比べて改善の余地があります。
世界の潮流をヒントにしつつ、日本ならではの文化・社会資源を活かし、「障がいがあってもあっても自分らしく暮らせる・働ける」社会を目指していきましょう。
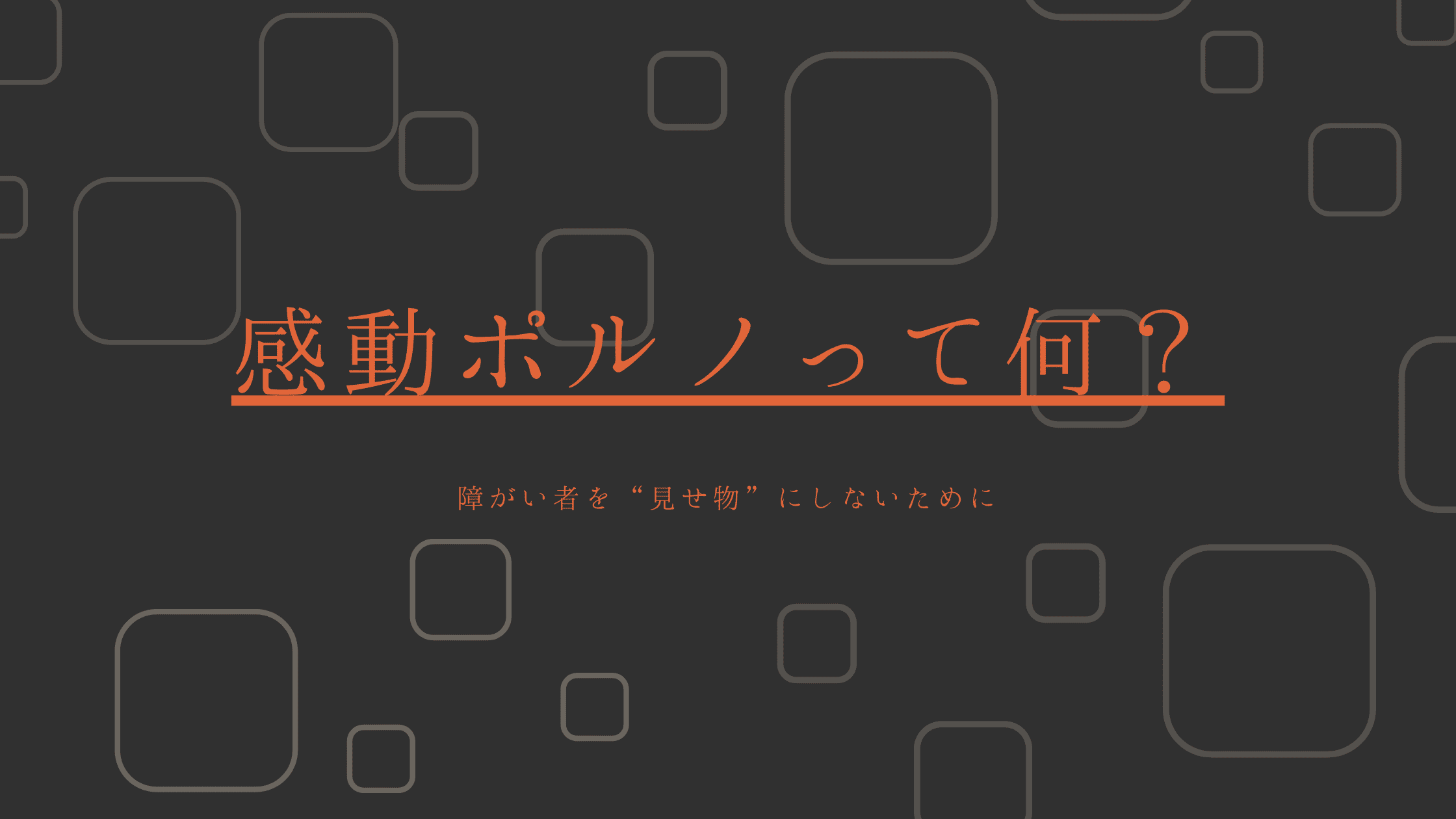
- 福祉
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
感動ポルノ(インスピレーションポルノ)って何?障がい者を“見せ物”にしないために
障がいを持つ人の「頑張って克服する姿」「勇気をくれる存在」というイメージが、メディアやSNSでは頻繁に流通しています。
一見、前向きでポジティブに思えるその描かれ方にも、実は重大な問題が潜んでいます。これが、いわゆる「感動ポルノ(Inspiration Porn)」と呼ばれる現象です。
この記事では、障がいをめぐるこの構図を、日本のメディアや社会のなかで改めて検証します。
なぜ問題とされるのか、当事者・支援者はどう向き合うべきか、そして私たちにできることは何かを一緒に探っていきましょう。
メディアと「感動ポルノ」の構図
「障がいを乗り越えた人=感動を与える人」という物語
テレビ番組やチャリティ番組では、障がいのある人が“挑戦”して“克服”する姿が強調されることがあります。NHKの番組、バリバラでは「検証!〈障害者×感動〉の方程式」という回でこの構図を問いかけています。
このような物語の構造には、障がい → 努力 → 成功/克服 →健常者を感動させる、というような流れが隠れていることがあります。
こうした描かれ方は、障がいをもつ人を「感動を提供する存在」「否定的な期待を払拭するための素材」として扱ってしまうリスクがあります。
参考リンク:〝感動ポルノ〟求める社会って?バリバラ大橋さんが伝えたかったこと
「障がい者役割」が強化されるという批判
学術的には「障がい者役割(disability role)」という概念があり、障がいを持つ人が「困難を克服すべき存在」「可哀そうな存在」という期待の枠に押し込められてしまうと指摘されています。
この枠組みでは、当事者が“普通に生きる”ということ本来の選択肢が見えにくくなり、「特別でなければならない」というプレッシャーを生むこともあります。
参考リンク:「感動」するわたしたち──『24時間テレビ』と「感動ポルノ」批判をめぐって
日本における事例と社会的な反応
例えば、 24時間テレビ のような大型チャリティ番組では、「障がいを持ちながら~」という感動ストーリーが多く扱われてきました。これに対して「障がいを持つ人を見世物のように扱っている」という批判も出ています。
また、当事者・親の立場から「私の子どもはあなたの感動のための存在ではない」といった声もあがっています。
参考リンク:なぜ「24時間テレビ」は「感動ポルノ」に変わったのか…日本テレビがそれでも番組を継続する理由、障がいのある私の娘は、あなた方の「感動ポルノ」ではない
なぜ「感動ポルノ」が障がい者にとって問題になるか
当事者の主体性を削ぐ可能性
「障がいをもっていても頑張ってるね」という言葉が、本人の意思や背景を抜きに繰り返されると、「これを達成しなければ価値がない」といったプレッシャーになりえます。
実はこの言葉が、当事者が感じる“ただ存在していい自分”を奪いかねないのです。
多様な人生/多様な障がいの経験を縮小してしまう
感動ポルノ的な構図では、障がい者が「困難を克服する」物語に偏重し、「生きづらさ」の語られ方が一面的になります。
それは「成功した人」だけが注目される構図を作り、苦しみ・日常・失敗・変化の過程を軽視する傾向があります。
社会的期待と疲弊を生む
「障がいをもっててもこのくらいできるね」といった称賛も、裏では「当たり前の成果を出さなければならない」という期待になりえます。
結果、当事者は疲弊し、自分のペースを見失うこともあります。
参考リンク:「障害者だから」という古い枠を超えた、自分の意志を言える社会に。 LITALICO発達ナビ
当事者・支援者ができること/発信のヒント
自分の物語を、自分の言葉で語る
当事者のSNS投稿やブログでは、「私はこう感じた」「私はこう考えた」という一人称が増えています。これは、他者の期待ではなく、自分自身のリアルに焦点を当てる発信方法です。
たとえば、「障がいがある私の日常」や「支援を受ける私」という語られ方ではなく、「私のやり方で生きる」という文脈です。
メディア・支援機関に対して“問い”を持つ
支援機関・メディア・教育機関では、障がい者を“感動させる素材”としないよう、以下の意識が求められます。
芝居じみた演出ではなく、当事者の意志・背景をきちんと尊重する
“成功物語”だけに注目せず、日常・困難・普通を語る
当事者の声を制作・発信の中心に置く
周囲の理解を少しずつ変えていく
非当事者も、次のようなことを心がけることで、感動ポルノを回避する社会づくりに貢献できます。
「すごいね」だけで終わらず「どんな工夫があったの?」と質問する
「頑張ったね」ではなく「あなたのそのままでいい」という視点を持つ
障がいを“感動”のための素材とせず、“共に生きる”関係づくりに目を向ける
まとめ:称賛ではなく理解を、物語ではなく関係を
「あなたのそのままでいいよ」という言葉が、私たちがこれから目指す社会の根底にあるべきです。
障がいをもつ人を「頑張ったね」と称賛するだけではなく、彼らが「そのままに生きられる」環境をつくること。称賛の裏にある“期待”を手放し、モノ化されない、関係性に基づいた社会を少しずつ紡いでいきましょう。
🔗参考リンク
「感動ポルノの何が問題なのか?」https://note.com/androyer/n/n82b6d8ee7c7e
「チャリティか、感動ポルノか? 身体障害とメディア表現について考える」https://inclusive-media.net/note-01/1.html
「『感動ポルノ』という社会の押し付けから見える障がい者差別を考える」https://mbit.co.jp/mag/column/13267

- スマホ
- 情報
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
障がい×SNS発信 ― あなたの声が世界を変える時代
障がいを抱える当事者、支援者、家族…さまざまな“声”が、いまSNSを通じて社会に届きつつあります。「発信すること」で、理解の輪が広がり、偏見の壁が揺れ、少しずつ“共生”の景色が見えるようになってきました。
本記事では、障がいを持つ人がSNSで発信する意義、具体的な方法、注意すべきことを整理します。
あなたの“発信”が、誰かの希望になるかもしれません。
なぜ「当事者のSNS発信」が注目されているのか
社会への“直接届ける声”としての価値
障がいに関する情報は、専門家や報道だけでは伝わりにくい“リアルな暮らし”があります。そうした暮らしを「当事者の言葉」で発信することで、社会や支援の在り方を変えるきっかけになります。
実際、遺伝性疾患や難病の当事者がSNSで自らの体験を発信する動きが増えています。
参考リンク: 病気や障がいがある当事者の「SNS発信」、社会に届けるためのポイントは?
若者・デジタルネイティブ世代の影響力
若い世代を中心に、SNSはコミュニケーションと自己表現の場となっています。
障がいを抱える人たちも、TikTok、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)などで“自分らしさ”を発信する姿が増えており、フォロワー数をベースに影響力を持つケースも出ています。
参考リンク: 総フォロワー6.5万人のインフルエンサーが描く発達障害当事者から見える世界を没入体験
情報の“共創”と“つながり”の時代へ
SNS発信は一方通行ではなく、共感・共有・対話を生みます。
障がいに関しては「理解されない」という孤立感が生まれやすいですが、発信を通じて“同じ経験を持つ人”“理解を示した人”がつながることで、新たなネットワークが生まれています。
SNS発信を始める前に知っておきたいポイント
目的とターゲットを明確にする
なぜ発信したいのか、誰に届けたいのかを考えることが出発点です。
例えば「同じ障がいを持つ若者に安心を届けたい」「職場で理解を促したい」など、自分の“声”が持つ意味を言葉にしましょう。
プラットフォームと形式を選ぶ
SNSにはそれぞれ特徴があります。
YouTube/動画形式:視覚・聴覚で語ることで理解を深めやすいです。
Instagram/フィード+ストーリーズ:暮らしの一コマを軽く発信しやすいです。
X(旧Twitter)/テキスト+リンク:短文で「気づき」を共有し、議論を喚起できます。自身の“強み”(言葉、動画、写真)や生活リズムに合った形式を選びましょう。
参考リンク:「軽度知的障害」とともに生きる。当事者としてYouTubeで発信を続けるえりかんさんが伝えたいこと
発信の守りとリスクに備える
SNS発信には光だけでなく“影”もあります。誹謗中傷、プライバシーの露出、誤情報の拡散などのリスクがあります。
発達障がいのある人がSNSでトラブルに巻き込まれる実例も報告されています。発信を続けるためには、無理をせず、自分のペース・安全な範囲で取り組むことが大切です。
参考リンク:発達障害のある方がSNSでどのようなトラブルに巻き込まれる危険性があるか【利用者ブログ】
実践:発信を続けるための3つのステップ
ステップ① “小さな1投稿”から始める
例えば、障がいとの付き合い方を1分で語る動画、日常の“困った”を正直に綴ったツイート等。
大きな演説ではなく、リアルな“声”が共感を生みます。
ステップ② 継続と振り返りを習慣化する
定期的な投稿(例:週1回)と、投稿後の反応を振り返ることで、発信内容がブラッシュアップされ、自分の発信スタイルが見えてきます。
「どんな投稿が反応されやすいか」「自分が書いて心が軽くなるか」などを観察しましょう。
ステップ③ フォロワー・コミュニティとの関係を育てる
発信は“届ける”だけでなく、“つながる”ことも大切です。
コメントに応える、小さなメッセージを返す、他の当事者の投稿にいいねやリプライを送ることで、フォロワーは“ただの数字”から“つながった仲間”になります。
結果として、発信者自身の居場所・支えにもなります。
発信をさらに価値あるものにするために
自分の「声の核」を持つ
「何を伝えたいか」を深く考えることで、ブレずに発信を続けやすくなります。
例えば「私だから知っている働き方」「視覚障がいと旅行のリアル」「ASD当事者の時間管理術」など。
ビジュアル・ストーリーを意識する
動画や写真、テキストを組み合わせることで、視覚的にも印象的な発信が可能です。
例えば、発達障がいを抱える当事者が「朝のルーティン」を動画で見せることで“わかる”発信になります。
発信を“つながる活動”に発展させる
フォロワーとのやり取りを出発点に、オンラインイベント、ライブ配信、コラボ投稿などに発展させることで、発信が“孤立しない”活動になります。
例えば、障がい当事者が集まる座談会をライブ配信するなどの試みも。
参考リンク:障がいがあっても、自分らしく。S N S座談会―プロに学ぶ発信力のコツ
注意すべき点と守るべきルール
プライバシーと開示のバランス
自身や周囲の人のプライバシーを守りつつ、リアルな体験を届けるには“どこまで開示するか”を事前に考えることが重要です。
誹謗中傷・炎上リスクの備え
障がいをテーマにした発信は、ポジティブな意味でも注目されやすい反面、批判や誤解の対象にもなり得ます。発信を続けるためには、心が疲れたら休む、支援者と相談する等の“出口”を持つことが大切です。
参考リンク:LITALICO発達ナビ
コンテンツのアクセシビリティ確保
動画なら字幕・手話、画像なら代替テキスト、テキストなら読みやすいフォント・構成など、障がいに応じた配慮が必要です。
これにより「伝わる」発信が実現します。
まとめ:あなたの“声”が変える、未来の景色
障がいを持っているからこそ見えている景色があります。その景色を、スマホの画面を通して、SNSという場で発信すること。それは、別の誰かの「わかる」に寄り添い、社会にひとつの問いを投げかける行為です。
ちょっとした不安、ちょっとした喜び、ちょっとした工夫――それらを言葉にすることで、孤立感は“つながり”に変わります。SNSは、あなたの声を“届くもの”に変えるツールです。そして、届いた声はきっと、誰かの未来を少しだけ変える力を持っています。
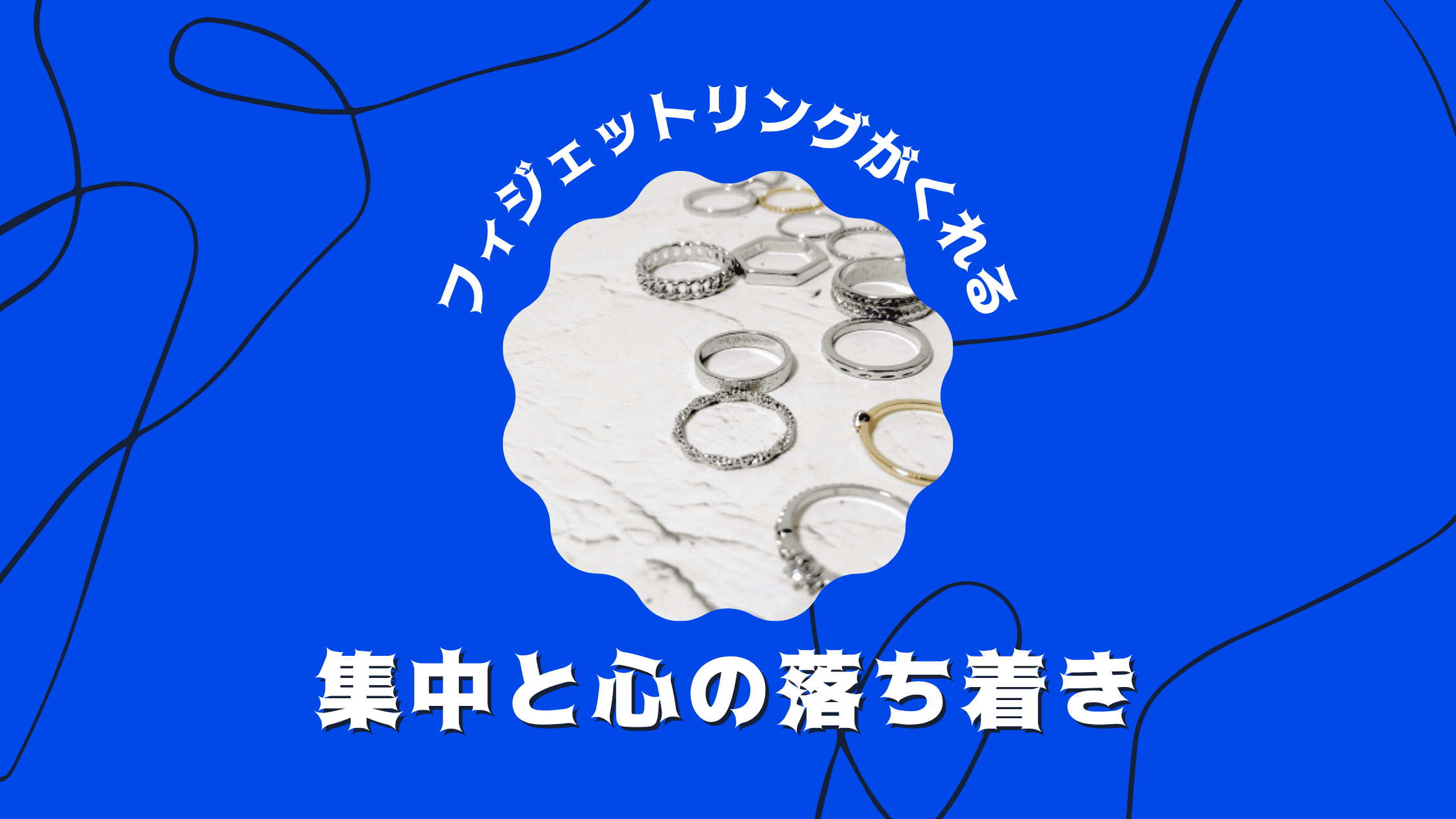
- 精神障がい
- 発達障がい
- ファッション
フィジェットリングがくれる集中と心の落ち着き
「落ち着かない」「手持ち無沙汰でそわそわする」「人と話すときに緊張してしまう」——そんなとき、指先でくるくる回すだけで心が少し軽くなる。それが、フィジェットリング(Fidget Ring)です。
最近は発達障がいのある人や、不安・緊張を感じやすい人の間で「安心グッズ」として注目を集めています。本記事では、フィジェットリングがもたらす心理的効果や活用法、実際の体験談を通して、“小さなリングが支える大きな効果”について考えてみましょう。
フィジェットリングとは?
そもそも「フィジェットリング」って何?
フィジェットリングは、指に装着して回したり動かしたりできるリング型のアイテム。「フィジェット」とは英語で「そわそわする」という意味です。つまり、“そわそわ”を安心に変えるための道具とも言えます。
一般的なものは、外側のリングが回転する構造。仕事中・授業中・会話中など、「落ち着かない場面」で自然に触れることができるのが特徴です。
参考リンク:Amazon|フィジェットリング新着ランキング
海外でも注目される「集中力アップツール」
アメリカやイギリスでは、フィジェットツール全般(スピナー、キューブ、リングなど)がADHD・ASD当事者のサポートツールとして広く知られています。特に、フィジェットリングは見た目がアクセサリーに近く、人前でも使いやすい点が高く評価されています。
「手の動き」が心を整える理由
指先を動かすことで「思考の渋滞」がほどける
発達障がいのある人は、頭の中に同時にたくさんの情報が浮かびやすい傾向があります。そんなとき、指先を動かすことで脳の過剰な刺激を分散し、思考が整理されやすくなるといわれています。
心理学的にも、単純な反復運動は「自己調整行動」と呼ばれ、安心感や集中の持続に効果的とされています。
参考動画:ADHDを解消する方法
不安や緊張を「見えない形でケア」できる
フィジェットリングの良いところは、誰にも気づかれずに不安を和らげられること。人と話すとき、発表の前、通院の待合室など、手を動かすだけで少し心が落ち着く。これだけで「自分をコントロールできている」という感覚を持てるのです。
実際に使ってみた——当事者のリアルな声
ケース①:ADHD当事者・会社員(30代女性)
会議中、緊張して足を貧乏ゆすりしてしまうのが悩みでした。フィジェットリングを使うようになってから、手の中で動かすだけで落ち着けるように。見た目もおしゃれなので、周囲に気づかれないのが助かります。
ケース②:ASD当事者・在宅ワーカー(40代男性)
作業中に集中が切れると、無意識にリングを回している。それだけで不思議と“切り替えスイッチ”が入るんです。指の感触が「今ここ」に戻してくれる感覚があります。
ケース③:身体障がい者・大学生(20代女性)
手に軽い麻痺があるのですが、リハビリの一環としても役立っています。無理のない範囲で指を動かせるので、遊びながらリハビリできて楽しいと感じます。
フィジェットリングの選び方と活用法
自分に合うタイプを選ぶ
金属製:回転がスムーズで長持ち。やや重みがあるため、指の動きで安心を得やすい。
シリコン製:軽くて柔らかい。肌が敏感な人や金属アレルギーがある人におすすめ。
デザイン重視型:見た目がアクセサリーとして自然で、日常使いしやすい。
参考リンク:フィジェットリングどこで売ってる?実店舗・通販・人気モデルを完全ガイド
日常に取り入れるコツ
会議・授業・待ち時間など、「落ち着かないとき」に手に取る
1日数分でも、意識して回して“呼吸を整える時間”を作る
リングを触りながら「今ここにいる」と意識することで、マインドフルネス効果も期待できる
まとめ
障がいの有無にかかわらず、誰もが不安や緊張を抱える日があります。そのたびに、外の世界に答えを求めるのではなく、指先ひとつで自分を落ち着かせる力を思い出すこと。
それが、フィジェットリングの本当の魅力です。
自分に優しく、他者にもやさしく。「落ち着く自分」をつくる第一歩を、今日から指先で回してみませんか?
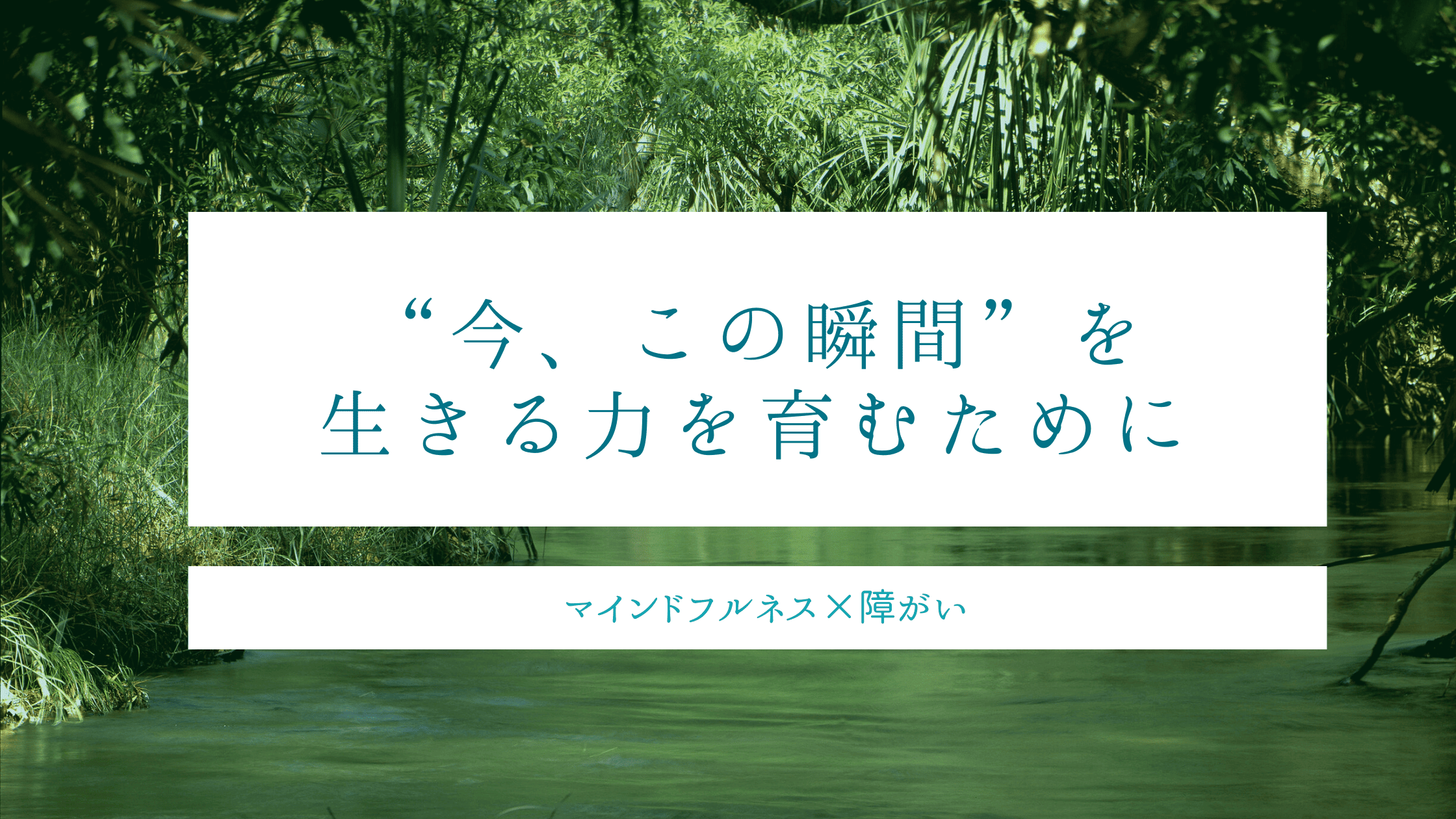
- マインドセット
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
“今、この瞬間”を生きる力を育むために
私たちは日々、たくさんの刺激や不安、周囲の期待にさらされています。特に障がいがあると、「できないこと」に意識が向きやすく、心が休まる時間を持つことが難しいこともあります。
そんな中で注目されているのが「マインドフルネス」。これは「今この瞬間に意識を向ける」心のトレーニングで、過去や未来に振り回されず、目の前の現実を穏やかに受け入れる力を育てます。
マインドフルネスは決して“特別な人”だけのものではありません。呼吸を感じること、音を聴くこと、手を動かすこと――そうした日常の中に、心を整えるチャンスがたくさんあります。
この記事では、障がいを持つ人がマインドフルネスをどのように取り入れ、どんな変化を感じているのかを紹介します。焦りや不安を和らげ、ありのままの自分で生きるためのヒントを、一緒に探していきましょう。
なぜ「今、この瞬間」に意識を向けるのか〜障がいと共に生きる日々の中で
気づかないうちに走っている「思考の自動操縦」
障がいを抱えると、たとえば移動の配慮、環境のバリア、体力・疲労・外部からの期待など、さまざまな「考えなければならないこと」が増えます。
結果として、頭の中は未来や過去、あるいは「どうすれば…」という思考であふれ、自分自身の“今”の感覚が置き去りにされがちです。
マインドフルネスとは何か〜評価せず「ただ観る」こと
日本マインドフルネス学会では、マインドフルネスを「今、この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずに、とらわれのない状態で、ただ観ること」と定義しています。障がいとともに生きる中で「〜しなければ」「〜すべきだ」という思考に気づき、それをちょっと脇に置くことで、心と体に余白をつくることができます。
参考リンク:日本マインドフルネス学会
障がい者・支援者の視点からのマインドフルネスの可能性
研究によれば、知的障がいや発達障がいのある人向けにもマインドフルネス・プログラム(例:MBSRなど)が生活の質(QOL)を向上させる可能性があるとされています。また、障がいを抱える人の親や支援者を対象とした遠隔マインドフルネス介入の試みもあります。
マインドフルネスが障がいを抱える人にとって意味するもの
自分の感覚・思考・感情に気づくこと
障がいを持つことで、自分の体や感覚が以前と異なることに気づいたり、不安・焦り・疲労を抱えたりすることが多いです。
マインドフルネスでは「今、ここで感じていること」に意識を向けるトレーニングを通じて、その感覚に名前をつけ、認めることで“苦しみのループ”を緩める働きがあります。
非評価・非反応の態度を養うこと
「自分はダメだ」「もっとできるはずだ」という思いを繰り返すと、余計なストレスになります。
マインドフルネスでは、体験そのものを評価せず、“ただ観る”態度を育てることで、そのような思考の渦から少し距離をとることができます。
繰り返し・習慣化による“道具化”
障がいがあると、疲労や体調の波があり、集中力や意欲も安定しないことがあります。
そのため、「マインドフルネスを特別な時間だけで終わらせず、日常に取り入れる習慣化」が特に重要になります。研究でも、継続したマインドフルネス介入が心理的な効果につながることが支持されています。
参考リンク・文献:日本国内における未成年者を対象としたマインドフルネスの実践に関する研究動向とその課題
障がいとタイプ別に見るマインドフルネスの応用
筋・運動系障がい(身体障がい)へのアプローチ
身体障がいがある場合、移動・姿勢・疲労がマインドフルネス実践時のハードルになることがあります。
ここでは、座位でもできる「ボディスキャン瞑想」や「呼吸に意識を向ける短時間ワーク」が有効です。例えば、椅子に座って背もたれを使いながら、1〜2分間、自分の足や手の触感、呼吸の動きを丁寧に観察する。疲れた日は、立ち上がらずに行えるワークから始めると良いでしょう。
発達障がい・知的障がいのある人向けマイルドな実践
知的障がいや発達障がいがある人に向けた研究では、“思考を止める’ことよりも、「目の前の感覚(音・匂い・触感)に気づく」トレーニングが効果的という結果があります。
具体的には、好きな音楽を流しながら「今、どの音が聞こえるか?」と問いかける、散歩中に「風が肌に触れている感覚」を味わうなど、“感覚集中”型のマインドフルネスが取り入れられています。
精神障がい(不安・うつ・PTSD含む)との関係
精神障がいを抱える場合、マインドフルネスは“思考の暴走”や“過剰な反応”を緩める目的で使われることがあります。
たとえば、マインドフルネス・ストレス低減法(MBSR)やマインドフルネス認知療法(MBCT)は、うつ・不安の再発防止プログラムとしても知られています。障がいを持つ人が日々抱えるストレスや「安定を維持しなければ」という圧力に対して、「今ここにある呼吸」「今の身体の感覚」に戻る練習が有効になることがあります。
参考リンク:ストレスをためない心の態度 マインドフルネスのすすめ
実践ステップ:障がいを持つ人でも無理なく始めるマインドフルネス
ステップ① 身体・環境を整える
まず、実践のハードルを下げるために以下のような工夫をしましょう。
安定した姿勢をとれる場所・時間を見つける(車椅子、座位、寝た状態など)
照明・音・温度など、身体がリラックスできる環境にする
初期は1〜2分から始め、無理に長くせず“習慣化”を目指す
ステップ② 自分に合った「気づき」のツールを使う
マインドフルネスには様々な形式があります。障がいのある人は、自分の得意な感覚・動きを活かすことで実践しやすくなります。
呼吸に意識を向ける簡単ワーク
ボディスキャン(体の一部ずつ観察)
感覚集中型ワーク(「肌に触れている感覚」「足底の感触」など)また、日本国内の学会誌でも実践の枠組みが紹介されています。
参考リンク:マインドフルネス
ステップ③ 継続と振り返り/仲間や支援者と共有する
継続を助ける工夫として、日記形式で「実践した時間」「感じたこと」「続けてよかったこと」をメモしておくのがおすすめです。障がいを持つ人の周囲には支援者・家族・仲間がいることが多いため、「一緒に実践」「振り返りを共有」することでモチベーションを保ちやすくなります。また、“支援現場×マインドフルネス”という観点では、職業リハビリテーションの場での導入可能性も研究されています。
注意点・障がいを持つ人がマインドフルネスを行う際の配慮
無理をしない/過度な期待を手放す
マインドフルネスは万能ではありません。研究でも「すべての人に必ず効果が出るわけではない」ことが指摘されています。特に障がいやトラウマのある人は、古い痛み・記憶・感覚が呼び起こされる場合もあるため、“安全な環境で少しずつ”が重要です。
体調・疲労・環境の波を理解する
障がいを持つ日々には、体調・疲労・センサー感覚の過敏などが起こりやすいです。
座位が辛い日、動きづらい日には短く実践する、または横になって行うなど、柔軟に調整しましょう。
専門家・支援者との連携を
もし呼吸困難・筋・神経系の障がいや重度の精神症状がある場合、マインドフルネスを始める前に医療・心理の専門家に相談することをおすすめします。
導入プログラムでは「安心できる支援付き」が望ましいとされています。
事例紹介:障がいを抱えながら実践したマインドフルネスの声
Aさん(車いす利用/身体障がい)
Aさんは、移動の際に体力や疲労に悩んでいました。
マインドフルネスを少しずつ取り入れ、毎晩ベッドで「呼吸を丁寧に感じる」時間を2分設けました。
すると、「移動時に感じる体の緊張が少し軽くなった」「移動後すぐに休むしかなかった日が、少し動ける時間が増えた」と変化を感じたと言います。
Bさん(発達障がい/感覚過敏あり)
Bさんは、騒がしい場所や変化の多い動きに疲れやすかったのですが、「歩くときに足裏の感触を5秒意識する」「電車内で窓のガラスに触れた感覚を味わう」といった“感覚集中型マインドフルネス”を取り入れました。
その結果、「気づいたら息が浅くなっていた」「でも、気づけることで“あ、ちょっと休もう”と自分に声をかけられるようになった」と語ります。
Cさん(精神障がい/不安・うつ傾向)
Cさんは、不安の波が来る度に“思考の渦”に陥っていました。
マインドフルネスで「思考が来たら、雲が流れるようにただ通り過ぎる」というメタファーを使って練習すると、「あれ、思考に飲まれてたけど、抜けられた」と感じた日が増えたそうです。
数週間の実践後、「不安が来たときに“来たね”って言える自分がいた」と話しています。
まとめ:障がいをもっていても、“今、この瞬間”に寄り添える自分になる
マインドフルネスとは、特別なポーズや長時間の瞑想ではなく、「今、ここにあるもの」に意識を向ける習慣です。障がいをもって生きると、それぞれの体・環境・感覚に独自の課題があります。だからこそ、自分に合った方法で、少しずつ“気づき”を育てることが大切です。
マインドフルネスを通じて得られるものは、
自分の身体・感覚・思考に気づくこと
執着せず、評価せず、体験を観ること
日常に“余白”をつくること
この3つを少しずつ生活に取り入れ、支援者や家族と共有することで、「障がいがあるからこそ得られるやさしさ」や「丁寧な生き方」が育まれます。あなたのペースで、“今、この瞬間”と向き合える時間を始めてみてください。
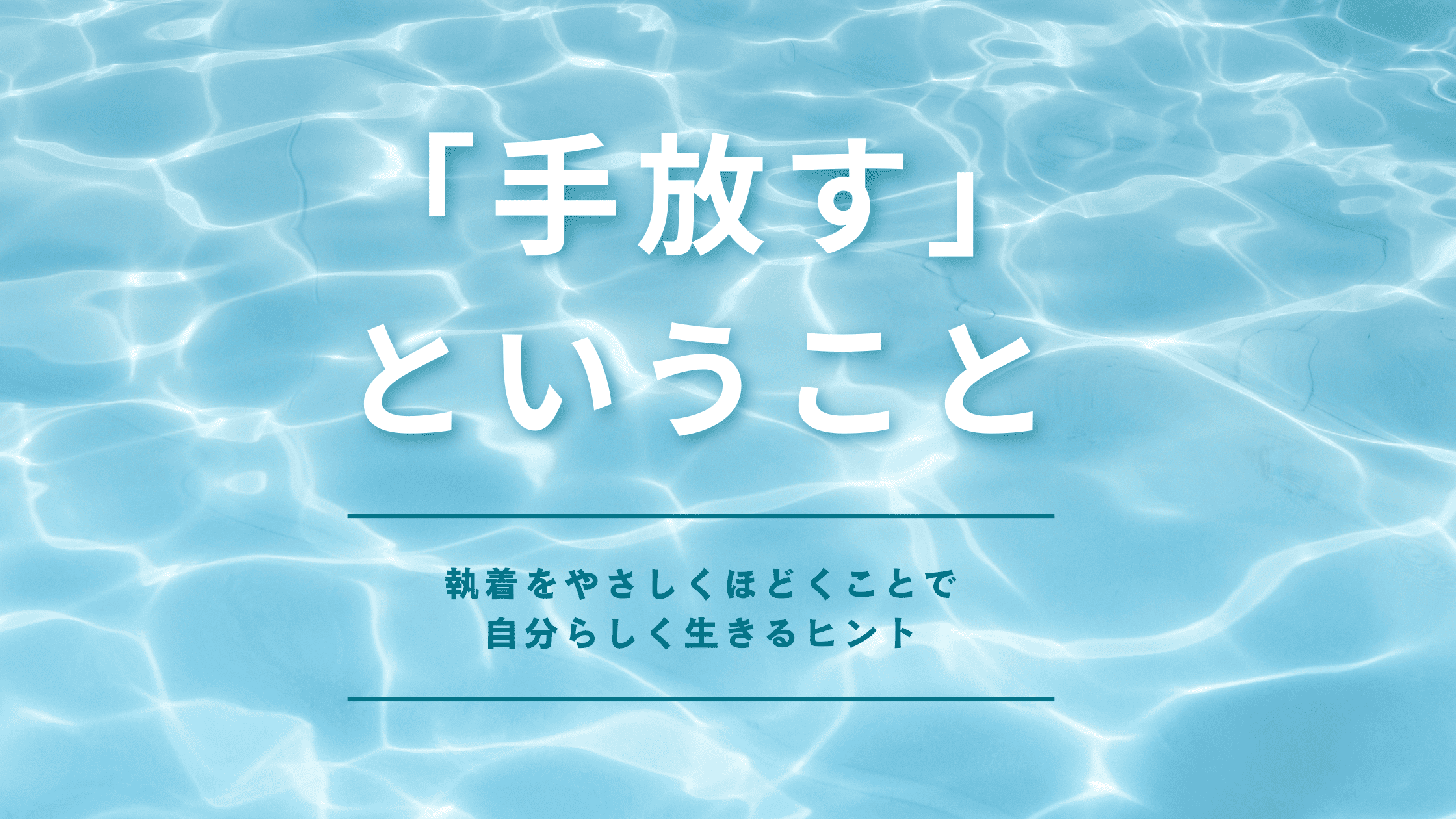
- マインドセット
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
「手放す」ということ ー 執着をやさしくほどくことで、自分らしく生きるヒント
はじめに:なぜ“手放す”が必要なのか
障がいを抱えて生きると、「できないこと」や「制限されること」に目が向きがちです。体の動き、環境のバリア、過去のトラウマ、支援が追いつかない状況――そういった日々の中で、多くの人が「無理を続ける」か、「あきらめる」かの二択に追われてしまうことがあります。
しかし、「手放す」という選択は、あきらめや投げやりではありません。むしろ、それは「未来に向けて自分のエネルギーを解放する」優しい決断です。
研究では、執着や手放せない思考が不安・うつ・ウェルビーイング低下に関わっていることが示されており、手放すことには心理的な解放効果があるとされています。
障がいのある人にとって、「手放す」ことは、環境や自分を苦しめているものを軽くし、“自分らしい生き方”を取り戻す鍵になるかもしれません。
本記事では、「何を手放せばいいのか」「どうやって手放すのか」「手放したあとの世界はどう変わるのか」を、障がいという視点を交えながら解説します。
執着と障がい――手放せない心の根っこ
過去の経験・トラウマとの向き合い
障がいがあることで、過去の“できなかったこと”や“失敗した感覚”を何年も引きずることがあります。このような思考のループは、手放すことの難しさにもつながります。
研究では、手放せない思考が不安・うつの予測因子になることが報告されています。
たとえば、「あの時助けられなかった」「もっと努力すればできたはず」という思い。そのストーリーを抱え続けることが、自分を縛る鎖となることもあるのです。
身体・環境の制限と“解決すべき”という思い込み
障がいを持つと、身体の制限や周囲の環境バリアに何度も直面します。
「このバリアを完全になくさなければならない」「自分が変わらなければならない」という思い込みが、過度なストレスになることもあります。
しかし、手放すとは「すべてを解決しようとする思い込み」を少しずつ手放すということでもあります。
“普通”“完璧”へのこだわりを手放す
「普通に動ける」「健常者と同じように振る舞う」――このような価値観に囚われてしまうと、自分の体やペースを否定しがちです。心理学的に言えば、変化への恐れや安心を捨てることの恐怖が、手放しを妨げる要因となることがあります。
障がいがあるからこそ、“完璧”を目指すのではなく、“自分に合った生き方”を手放すことで見えてくる世界があります。
参考リンク:「手放すか」「手放さないか」で物事を考えている人の心理分析
手放すためのステップ――障がいがあるからこそできる工夫
ステップ①今、自分が抱えている“手放したいもの”を明らかにする
自分が何を抱えているのかを見つめることから始まります。
どんな思いがいつも心の中にあるか?
それを抱えていることで、どんな苦しみや無力感があるか?
この問いかけによって、手放す対象が明確になります。書き出すことで思考が整理され、「何を置いていくか」が見えてきます。
ステップ②手放す準備――許可とサポートを確保
手放すことには「許可」が必要です。「手放してもいいんだ」「このままで良いんだ」という自己許可は、支援を受けるための第一歩です。また、専門家や仲間、支援団体のサポートを得ることで手放しやすくなります。マインドフルネスの研究では、手放す能力(letting go)が心理的健康に直接関わっており、支援や意識があることで変化が促されるという報告があります。
参考リンク(海外):セルフケアとして手放す
ステップ③実践と習慣化――少しずつ“軽く”していく
いきなり全部を手放す必要はありません。小さな習慣から始めることで、体と心が変化に適応できます。たとえば
毎日「今日はこれを手放してみよう」と決めて、気持ちを書き出す
「ありがとう」と「もう大丈夫」の言葉を自分にかける
環境の整理(資料・物・関係)を1つずつ進める
手放すこと=捨てることではなく、「そのものから少し離れる」「執着から距離を置く」ことです。
手放した先に見えるもの――障がいがあるからこそ得られるやさしさ
生きるスペースをつくる
手放すことによって、苦しみや無力感が減り、“生きるためのスペース”が生まれます。足りないものを補おうとする疲れから解放され、「今あるもの」で生きる豊かさを感じやすくなります。
自分とのやさしい対話ができる
障がいがあると、自分の体や感覚と向き合う機会が多くなります。手放す習慣が身につくと、自分を責める声が少なくなり、自分とのやさしい対話が可能になります。マインドフルネス的視点では、「手放す」ことが心身の平穏につながるとされています。
参考リンク(海外):鍵は手放すこと
支え合い・共生の思いが育まれる
手放すことで、他者の助けを受け取りやすくなり、支え合いの関係が自然に生まれます。障がいがある人と支援する側の関係を「一方的」ではなく「相互的」に変えるきっかけともなります。
実践例:障がい者が手放して得た気づき
例1:車いすユーザーが“完璧な移動”を手放したとき
車いすユーザーのAさんは、“段差がゼロの移動”を理想にしていました。しかし「完璧なバリアフリー」を追い続けたことで疲れ切ってしまった経験があります。
そこで「小さい段差なら工夫できる」「周囲の人に声をかける時間もOK」と心を切り替え、移動時の“余白”を許しました。その結果、移動自体が少し楽になり、予期せぬ優しさやサポートに気づきやすくなったと語っています。
例2:発達障がいを持つBさんが“みんなと同じ動き”を手放したとき
ASD傾向のあるBさんは、「みんなと同じように振る舞わなければ」という思い込みから、疲弊していました。
そこで「自分のペースでもいい」「自分のやり方でいい」と許可を出しました。それにより、仕事の仕方を変え、得意な時間帯・環境を利用して効率が上がったといいます。
例3:慢性疾患を抱えるCさんが“苦しくない毎日”を手放したとき
慢性疾患を持つCさんは、「毎日元気でなければ意味がない」と自分にプレッシャーをかけていました。
そのプレッシャーを手放し、「今日は休んでもいい」「体調が悪くても価値がある」と自分に語りかけるようにしました。その後、無理のないペースで活動できるようになり、“できること”に目を向けられるようになったそうです。
よくある「手放せない」テーマと向き合い方
執着する物・所有
物を捨てられない「ためこみ症」の背景には、手放すことへの恐怖や自分を変えることへの抵抗があるとされています。
参考リンク:ため込み症 ハートクリニック
障がいがある人にも、補助具・支援機器・環境を変える際の“手放し”が心理的負荷になることがあります。少しずつ整理することで、負担を軽くできます。
人間関係・支援者との依存
支援者や家族に頼り続けることは安心ですが、それが「自分で何もできない」という思い込みに変わると自尊心が下がることも。“手放す”とは、支援を受けることを自ら選び、同時に自分の意志で動くことを意味します。
自分の“べき”論・完璧主義
「こうあるべき」「他人と同じように」という価値観に固執すると、手放すべき思い込みが整理できないまま心が疲弊します。この“べき論”を見直すために、マインドフルネス的に「今の自分」を受け入れる練習が有効です。
手放すためのツール・実践ワーク
感謝ジャーナル+手放しリスト
毎日「今日はこれを手放してみよう」と書き出すワーク。併せて「感謝できること」を数項目書くことで、手放しと受け取りのバランスが取れます。
呼吸+瞑想による手放しの実習
マインドフルネス瞑想では、「手放す態度(letting-go)」が重要視されています。静かに座り、心に浮かんだ“手放したい思い”をただ観察し、呼吸とともに「手放してもいい」という許可を自分に出す練習。
支援グループ・対話の場をつくる
同じような境遇の当事者や支援者と「何を手放したか」「どう感じたか」を共有することが、手放しを深化させます。支え合いながら、変化を実感できます。
まとめ:手放すことは終わりではなく、新しい始まり
“手放す”という言葉を聞くと、どこか切ない響きがあるかもしれません。しかし、手放すことは「終わり」ではなく、「新しい生き方への扉を開くこと」です。
障がいがある・ないにかかわらず、私たちは何かを抱えながら生きています。その抱えものを少しずつでも手放すことができたとき、体と心に少しの“ゆとり”が生まれ、そのゆとりは、やさしさや自由、そして新たな可能性へつながります。
どうか、焦らず、自分のペースで手放していきましょう。手放しの先には、“手ぶらになっても価値がある自分”と出会える世界が広がっています。

- スポーツ
- 睡眠
- 生活
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 感覚過敏
呼吸の力を取り戻す — 障がい者にこそ知ってほしい呼吸法ガイド
私たちは毎日、何も意識せずに「呼吸」をしています。けれど、ストレスや不安、体の不調が続くと、その呼吸は知らぬ間に浅く、速く、苦しくなっていくものです。
特に、障がいのある人にとっては、身体の動かしづらさや感覚の敏感さ、緊張のしやすさなどから、呼吸が乱れやすい傾向があります。それは「がんばりすぎ」のサインでもあり、「少し休んでね」という体からのメッセージかもしれません。
呼吸は、心と体をつなぐ“橋”のようなもの。深く穏やかな呼吸は、心を落ち着かせ、体を整え、前を向く力を取り戻すきっかけになります。
この記事では、障がいのある方でも無理なく実践できる呼吸法や、日常に取り入れるためのちょっとしたコツをご紹介します。
呼吸と障がい
呼吸の役割と普段見えにくい問題点
呼吸は、全身に酸素を届け、不要な二酸化炭素を排出するとともに、自律神経の調整にも関わる基本的な生理機能です。日常では無意識に行われますが、障がいのある人にとっては「浅い呼吸」「息切れ」「胸式呼吸優位」などの傾向が表れやすく、その結果、疲労感や不調を招くことがあります。
たとえば、呼吸器疾患を持つ人たちを対象とした「呼吸リハビリテーション」の解説では、正しい呼吸法をトレーニングすることでQOL(生活の質)の向上が期待できるとされています。
参考リンク:呼吸リハビリテーションの目的と効果|正しい呼吸法でQOL
障がいの種類と呼吸への影響
障がいがあるということは、必ずしも呼吸に関係するわけではありませんが、次のようなケースでは呼吸が影響を受けやすくなります
筋力障がい・脊髄損傷などで胸郭や横隔膜の動きが制限され、深呼吸が難しい
呼吸器疾患(COPD、喘息など)を併発している場合、呼吸効率が落ちやすい
精神障がい(不安障がい、パニック障がいなど)により過呼吸傾向、呼吸の浅さ・速さに陥ることが多い(呼吸が交感神経優位になりやすい)
こうした背景を理解したうえで、呼吸法を取り入れることが「ただの健康法」以上の意味を持ちます。
呼吸法の種類と、その選び方
腹式呼吸(横隔膜呼吸)
腹式呼吸は、横隔膜を使って腹部を膨らませ・へこませるように息を吸って吐く方法です。「深い呼吸」を意識しやすく、自律神経の副交感神経を働かせる効果も期待できます。
YouTubeにもわかりやすい実演動画があります。
https://youtu.be/axaBPA4ZQlE?si=zID6rArgnHflFyhL
腹式呼吸の利点としては、肩こりや首の筋肉の緊張を軽くする効果、リラックス、そして呼吸の効率化が挙げられます。
参考リンク:厚生労働省 こころもメンテしよう こころと体のセルフケア、腹式呼吸の効果とは?メリットと正しい方法
478呼吸法(4-7-8 呼吸法)
478呼吸法は、吸う(4秒)→息を止める(7秒)→吐く(8秒)のリズムで行う方法です。ゆっくり吐く時間を長くすることで、自律神経を落ち着ける効果が期待されます。
呼吸のリズムを整えることで、緊張・不安の軽減、寝つきの改善などが見込まれます。
参考リンク:478呼吸法とは?心と身体をリラックスさせる4つの手順と注意点
参考動画
https://youtu.be/tlYqEuWHUxc?si=Lvooon0uyhJT-a__
https://youtu.be/0Nlag4-X_Og?si=fPm_Kqgnc-8fLHd8
呼吸筋トレーニング/ストレッチ法
呼吸を補助する筋肉(肋間筋、腹横筋、横隔膜など)をストレッチや軽いトレーニングで動かすことで、呼吸能力を高めることができます。
YouTubeには「呼吸筋ストレッチ体操」という動画もあります。
https://youtu.be/fikReXjXJcA?si=s8n04VsKtzFI0WAf
呼吸と動きを組み合わせる方法
ヨガやピラティスでは呼吸と体の動きを連動させる方法が使われます。
特に初心者向けで呼吸法を重視したピラティス動画もあり、呼吸に意識を向けながら体を整えることができます。
https://youtu.be/UFfa-lK90DM?si=0V79zxPUAKwQYAcL
障がい者が呼吸法を取り入れる際の工夫と注意点
無理をしないことが第一
呼吸法を取り入れようとした時、最初から「長時間・高負荷」でやろうとすると、逆に息苦しさや疲労を招く場合があります。
最初は1〜2分から始め、できれば座位・安定した姿勢で行うことが安全です。
補助道具やサポートを使う
呼吸が苦しい場合は、椅子・背もたれを使う、クッションを背中に置く、手すりを握るなどして、身体が支えられた状態で練習するのがよいです。
また、視覚障がいがある人は音声ガイドを活用する、手すり等を使って体を安定させながらゆったりやるなど工夫するとやりやすいでしょう。
呼吸法導入前に医師・理学療法士へ相談
呼吸器系の疾患や胸郭の可動性制限がある人は、誤った呼吸法をすると逆効果になることがあります。
特に心臓・肺に既往がある場合は、専門家の指導を受けることが望ましいです。
呼吸法を生活に取り入れるステップと習慣化のコツ
ステップ1:呼吸法を体験してみる
まずは短時間、軽く行うことから始めます。例えば、夜寝る前の1〜2分や、休憩時間の合間などに取り入れてみましょう。
YouTube動画を見ながら真似してみるのも有効です。
ステップ2:振り返り・記録
呼吸法をしたあと、「どこが楽になったか」「どの姿勢でやりやすかったか」などを記録しておくと、自分に合った方法が見えてきます。
ステップ3:段階的に強化
慣れてきたら少しずつ時間を長くしたり、呼吸筋トレーニングを取り入れたりしてステップアップします。
ステップ4:他のケア習慣と組み合わせる
睡眠改善、ストレッチ、軽い運動、リラクゼーションと組み合わせると相乗効果があります。
特に呼吸法が睡眠品質を改善したという研究もあります。
まとめ:呼吸は「生きるリズム」
呼吸は、誰にでも与えられた「命のリズム」です。しかし、障がいがあると、体の動きやストレス、生活リズムの乱れから、知らず知らずのうちにそのリズムが浅く・速く・不安定になってしまうことがあります。
そんなときこそ、「呼吸」に意識を向けてみることが大切です。呼吸は、努力ではなく「寄り添い」で整うもの。無理せず、焦らず、あなたのペースで呼吸を育てていきましょう。