- マインドセット
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
「手放す」ということ ー 執着をやさしくほどくことで、自分らしく生きるヒント
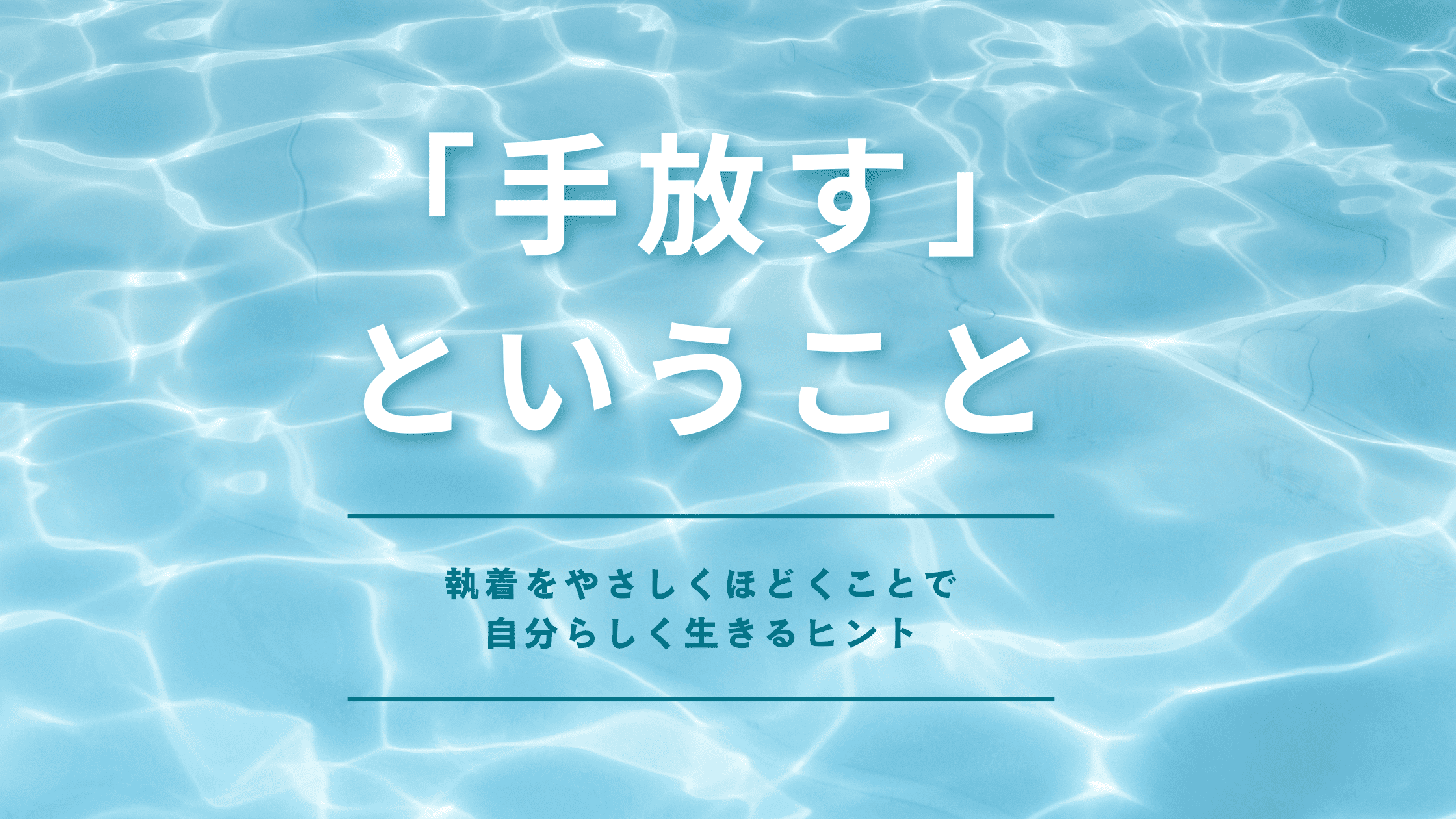
はじめに:なぜ“手放す”が必要なのか
障がいを抱えて生きると、「できないこと」や「制限されること」に目が向きがちです。
体の動き、環境のバリア、過去のトラウマ、支援が追いつかない状況――そういった日々の中で、多くの人が「無理を続ける」か、「あきらめる」かの二択に追われてしまうことがあります。
しかし、「手放す」という選択は、あきらめや投げやりではありません。
むしろ、それは「未来に向けて自分のエネルギーを解放する」優しい決断です。
研究では、執着や手放せない思考が不安・うつ・ウェルビーイング低下に関わっていることが示されており、手放すことには心理的な解放効果があるとされています。
障がいのある人にとって、「手放す」ことは、環境や自分を苦しめているものを軽くし、“自分らしい生き方”を取り戻す鍵になるかもしれません。
本記事では、「何を手放せばいいのか」「どうやって手放すのか」「手放したあとの世界はどう変わるのか」を、障がいという視点を交えながら解説します。
執着と障がい――手放せない心の根っこ

過去の経験・トラウマとの向き合い
障がいがあることで、過去の“できなかったこと”や“失敗した感覚”を何年も引きずることがあります。
このような思考のループは、手放すことの難しさにもつながります。
研究では、手放せない思考が不安・うつの予測因子になることが報告されています。
たとえば、「あの時助けられなかった」「もっと努力すればできたはず」という思い。
そのストーリーを抱え続けることが、自分を縛る鎖となることもあるのです。
身体・環境の制限と“解決すべき”という思い込み
障がいを持つと、身体の制限や周囲の環境バリアに何度も直面します。
「このバリアを完全になくさなければならない」「自分が変わらなければならない」という思い込みが、過度なストレスになることもあります。
しかし、手放すとは「すべてを解決しようとする思い込み」を少しずつ手放すということでもあります。
“普通”“完璧”へのこだわりを手放す
「普通に動ける」「健常者と同じように振る舞う」――このような価値観に囚われてしまうと、自分の体やペースを否定しがちです。
心理学的に言えば、変化への恐れや安心を捨てることの恐怖が、手放しを妨げる要因となることがあります。
障がいがあるからこそ、“完璧”を目指すのではなく、“自分に合った生き方”を手放すことで見えてくる世界があります。
参考リンク:「手放すか」「手放さないか」で物事を考えている人の心理分析
手放すためのステップ――障がいがあるからこそできる工夫

ステップ①今、自分が抱えている“手放したいもの”を明らかにする
自分が何を抱えているのかを見つめることから始まります。
- どんな思いがいつも心の中にあるか?
- それを抱えていることで、どんな苦しみや無力感があるか?
この問いかけによって、手放す対象が明確になります。
書き出すことで思考が整理され、「何を置いていくか」が見えてきます。
ステップ②手放す準備――許可とサポートを確保
手放すことには「許可」が必要です。
「手放してもいいんだ」「このままで良いんだ」という自己許可は、支援を受けるための第一歩です。
また、専門家や仲間、支援団体のサポートを得ることで手放しやすくなります。
マインドフルネスの研究では、手放す能力(letting go)が心理的健康に直接関わっており、支援や意識があることで変化が促されるという報告があります。
参考リンク(海外):セルフケアとして手放す
ステップ③実践と習慣化――少しずつ“軽く”していく
いきなり全部を手放す必要はありません。
小さな習慣から始めることで、体と心が変化に適応できます。
たとえば
- 毎日「今日はこれを手放してみよう」と決めて、気持ちを書き出す
- 「ありがとう」と「もう大丈夫」の言葉を自分にかける
- 環境の整理(資料・物・関係)を1つずつ進める
手放すこと=捨てることではなく、「そのものから少し離れる」「執着から距離を置く」ことです。
手放した先に見えるもの――障がいがあるからこそ得られるやさしさ

生きるスペースをつくる
手放すことによって、苦しみや無力感が減り、“生きるためのスペース”が生まれます。
足りないものを補おうとする疲れから解放され、「今あるもの」で生きる豊かさを感じやすくなります。
自分とのやさしい対話ができる
障がいがあると、自分の体や感覚と向き合う機会が多くなります。
手放す習慣が身につくと、自分を責める声が少なくなり、自分とのやさしい対話が可能になります。
マインドフルネス的視点では、「手放す」ことが心身の平穏につながるとされています。
参考リンク(海外):鍵は手放すこと
支え合い・共生の思いが育まれる
手放すことで、他者の助けを受け取りやすくなり、支え合いの関係が自然に生まれます。
障がいがある人と支援する側の関係を「一方的」ではなく「相互的」に変えるきっかけともなります。
実践例:障がい者が手放して得た気づき

例1:車いすユーザーが“完璧な移動”を手放したとき
車いすユーザーのAさんは、“段差がゼロの移動”を理想にしていました。
しかし「完璧なバリアフリー」を追い続けたことで疲れ切ってしまった経験があります。
そこで「小さい段差なら工夫できる」「周囲の人に声をかける時間もOK」と心を切り替え、移動時の“余白”を許しました。
その結果、移動自体が少し楽になり、予期せぬ優しさやサポートに気づきやすくなったと語っています。
例2:発達障がいを持つBさんが“みんなと同じ動き”を手放したとき
ASD傾向のあるBさんは、「みんなと同じように振る舞わなければ」という思い込みから、疲弊していました。
そこで「自分のペースでもいい」「自分のやり方でいい」と許可を出しました。
それにより、仕事の仕方を変え、得意な時間帯・環境を利用して効率が上がったといいます。
例3:慢性疾患を抱えるCさんが“苦しくない毎日”を手放したとき
慢性疾患を持つCさんは、「毎日元気でなければ意味がない」と自分にプレッシャーをかけていました。
そのプレッシャーを手放し、「今日は休んでもいい」「体調が悪くても価値がある」と自分に語りかけるようにしました。
その後、無理のないペースで活動できるようになり、“できること”に目を向けられるようになったそうです。
よくある「手放せない」テーマと向き合い方

執着する物・所有
物を捨てられない「ためこみ症」の背景には、手放すことへの恐怖や自分を変えることへの抵抗があるとされています。
参考リンク:ため込み症 ハートクリニック
障がいがある人にも、補助具・支援機器・環境を変える際の“手放し”が心理的負荷になることがあります。少しずつ整理することで、負担を軽くできます。
人間関係・支援者との依存
支援者や家族に頼り続けることは安心ですが、それが「自分で何もできない」という思い込みに変わると自尊心が下がることも。
“手放す”とは、支援を受けることを自ら選び、同時に自分の意志で動くことを意味します。
自分の“べき”論・完璧主義
「こうあるべき」「他人と同じように」という価値観に固執すると、手放すべき思い込みが整理できないまま心が疲弊します。
この“べき論”を見直すために、マインドフルネス的に「今の自分」を受け入れる練習が有効です。
手放すためのツール・実践ワーク
感謝ジャーナル+手放しリスト
毎日「今日はこれを手放してみよう」と書き出すワーク。併せて「感謝できること」を数項目書くことで、手放しと受け取りのバランスが取れます。
呼吸+瞑想による手放しの実習
マインドフルネス瞑想では、「手放す態度(letting-go)」が重要視されています。
静かに座り、心に浮かんだ“手放したい思い”をただ観察し、呼吸とともに「手放してもいい」という許可を自分に出す練習。
支援グループ・対話の場をつくる
同じような境遇の当事者や支援者と「何を手放したか」「どう感じたか」を共有することが、手放しを深化させます。支え合いながら、変化を実感できます。
まとめ:手放すことは終わりではなく、新しい始まり
“手放す”という言葉を聞くと、どこか切ない響きがあるかもしれません。
しかし、手放すことは「終わり」ではなく、「新しい生き方への扉を開くこと」です。
障がいがある・ないにかかわらず、私たちは何かを抱えながら生きています。
その抱えものを少しずつでも手放すことができたとき、
体と心に少しの“ゆとり”が生まれ、
そのゆとりは、やさしさや自由、そして新たな可能性へつながります。
どうか、焦らず、自分のペースで手放していきましょう。
手放しの先には、“手ぶらになっても価値がある自分”と出会える世界が広がっています。