- 精神障がい
- 発達障がい
『普通に食べたいのに食べられない』心の葛藤と摂食障がいの本当
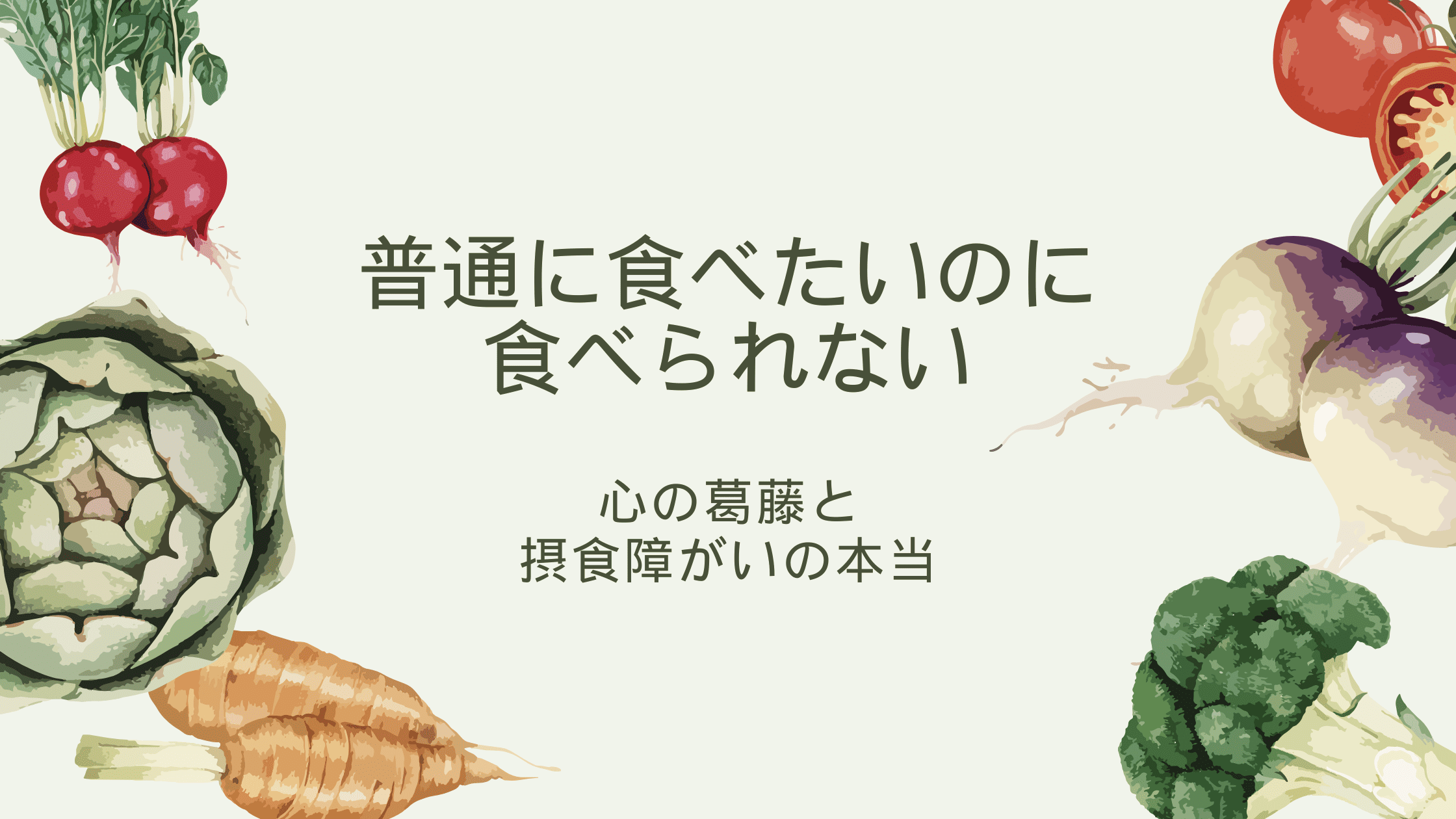
「痩せたいわけじゃない。食べたい。でも、こわい。」
「食べるのが止まらない。苦しい。でも、やめられない。」
これは、摂食障がいを抱える人の中にあるリアルな葛藤です。
「ただ普通に、食べられたらいいのに」
「食べること」には生きるための行動だけでなく、感情・自尊心・人間関係のパターンが色濃く表れます。
この記事では、摂食障がいの基本的な知識だけでなく、苦しんでいる心の内側にも目を向けながら、回復へのヒントを探ります。
摂食障がいとは?

食の問題ではなく、心のSOS
摂食障がいとは、食行動に強いこだわりや異常が現れる精神疾患です。単に「痩せたい」「太りたくない」ではなく、不安や孤独、自分への否定感などを“食”を通して表現している状態です。
代表的なタイプと特徴
- 神経性やせ症(拒食症)
食べる量を極端に制限し、体重が著しく低下。自分を“太っている”と感じてしまうボディイメージの歪みがある。 - 神経性過食症(過食症)
過食と嘔吐・下剤の乱用を繰り返す。食への執着と自己嫌悪を行き来する。 - 過食性障がい(むちゃ食い障がい)
衝動的に大量に食べるが、排出行為は伴わない。コントロール不能な「むちゃ食い」が継続。 - 回避・制限性食物摂取障がい(ARFID)
味や匂い、食感への敏感さなどが原因で食事量が極端に減る(摂食障がいの新しい分類)。
「食べること」が苦しい理由

“食=不安”という感情の根っこ
「食べると太る」「食べると罪悪感がある」
こうした感情は、自己否定やコントロール欲求と深く結びついています。
- 「食べたらダメ」=“いい子でいなければ”という思い込み
- 「食べてしまった」=“私はダメな人間”という全否定
- 「痩せている私」だけが存在価値を持てる
これらは家庭環境や過去の傷つき体験、自尊心の低さからくる「思い込み」として心の中に根づいています。
「ちゃんと食べなきゃ」は呪いになることも
周囲の「しっかり食べて」「少し太った方がいいよ」という言葉も、摂食障がいの人には強烈なプレッシャーとなります。
❝ 体重や食べた量で、自分の価値を測ってしまう。
食べたことをなかったことにしたくて、すぐにトイレに走った。 ❞
これが、食行動の背後にある「こころの叫び」です。
摂食障がいになりやすい人の傾向

性格傾向:まじめで我慢強く、優しい人
摂食障がいを経験する人の多くに共通するのが以下のような傾向です
- 完璧主義・努力家
- 人に迷惑をかけたくない
- 感情を飲み込むクセがある
- 人からどう思われるかを過剰に気にする
環境要因:育った環境や文化の影響も
- 子どもの頃、他人や親から体型や食事に厳しく指摘された
- 「いい子」「成績優秀」「我慢が美徳」と言われ続けた・思い込んでいる
- SNSやメディアの「痩せ=美しさ」という価値観に強く影響された
こうした背景が心の奥に「ありのままの自分では価値がない」という根深い思い込みをつくり、食を通じた自分コントロールにつながっていくのです。
回復とは、「普通に食べる」ことではない

治すより「自分と仲直りする」こと
摂食障がいの回復とは「以前のように食べられるようになること」ではなく、“自分との関係性”を変えていくことです。
- 「ちゃんと食べられなくてもいい」と思える
- 「食べられない日があっても自分を責めない」
- 「太っても自分の価値は変わらない」と思えるようになる
これが“心の回復”です。
少しずつ、身体感覚を取り戻す
- 食べたい・食べたくないという感覚に注意を向ける
- 食事中の“味”や“匂い”を味わうようにしてみる
- 食後の罪悪感に気づいて、そっと受け流す
食べることを“罰”にしない。
それが少しずつ「自分を生きる」練習になっていきます。
周囲ができることは「そばにいる」こと

避けたい言葉・態度
- 「もっと食べなよ」「それじゃ足りないよ」
- 「私なんてもっと太ってるよ」
- 「あなたは細いから大丈夫」
→ これらはすべて「食べる=責められること」として心に残ります。
代わりにできること
- 食事の話題以外をたくさん共有する
- 何もできなくても「そばにいるよ」と伝える
- 良い・悪いではなく「苦しかったね」と気持ちを受け止める
大切なのは「何か言おうとしないこと」かもしれません。
沈黙の中にある“安心”が、回復の土台になります。
回復への道しるべ|支援とつながる勇気を

摂食障がいは、ひとりで抱えるにはあまりにも重たいものです。
しかし、支援やつながりによって、必ず“光”は見えてきます。
どこに相談したらいい?
- 心療内科・精神科(摂食障がい外来)
- 精神保健福祉センター・地域包括支援センター
- 自助グループ(NABAなど)
「摂食障がい 自助グループ (お住まいの地域)」で検索するのもおすすめ - 児童・生徒であれば、スクールカウンセラーや養護教諭
「言葉にならない気持ち」でも大丈夫
「助けて」と言えなくても、「しんどいです」だけで十分です。
回復への第一歩は「ひとりじゃない」と気づけた瞬間から始まります。
おわりに:“食べられない私”も、ちゃんと生きている
「食べたいのに食べられない」
「普通に戻れない自分が、情けない」
でも、そんなあなたも、ちゃんと生きています。
毎日、目の前の苦しみと向き合って、あなたは踏んばっている。
それだけで、十分に価値のあることです。
どうか、あなたの「食べること=生きること」が少しずつ楽になりますように。
誰かのためではなく、あなた自身の人生のために。