- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
- 仕事
みんなと違うを力に変えて——障がい者の起業家が拓く道
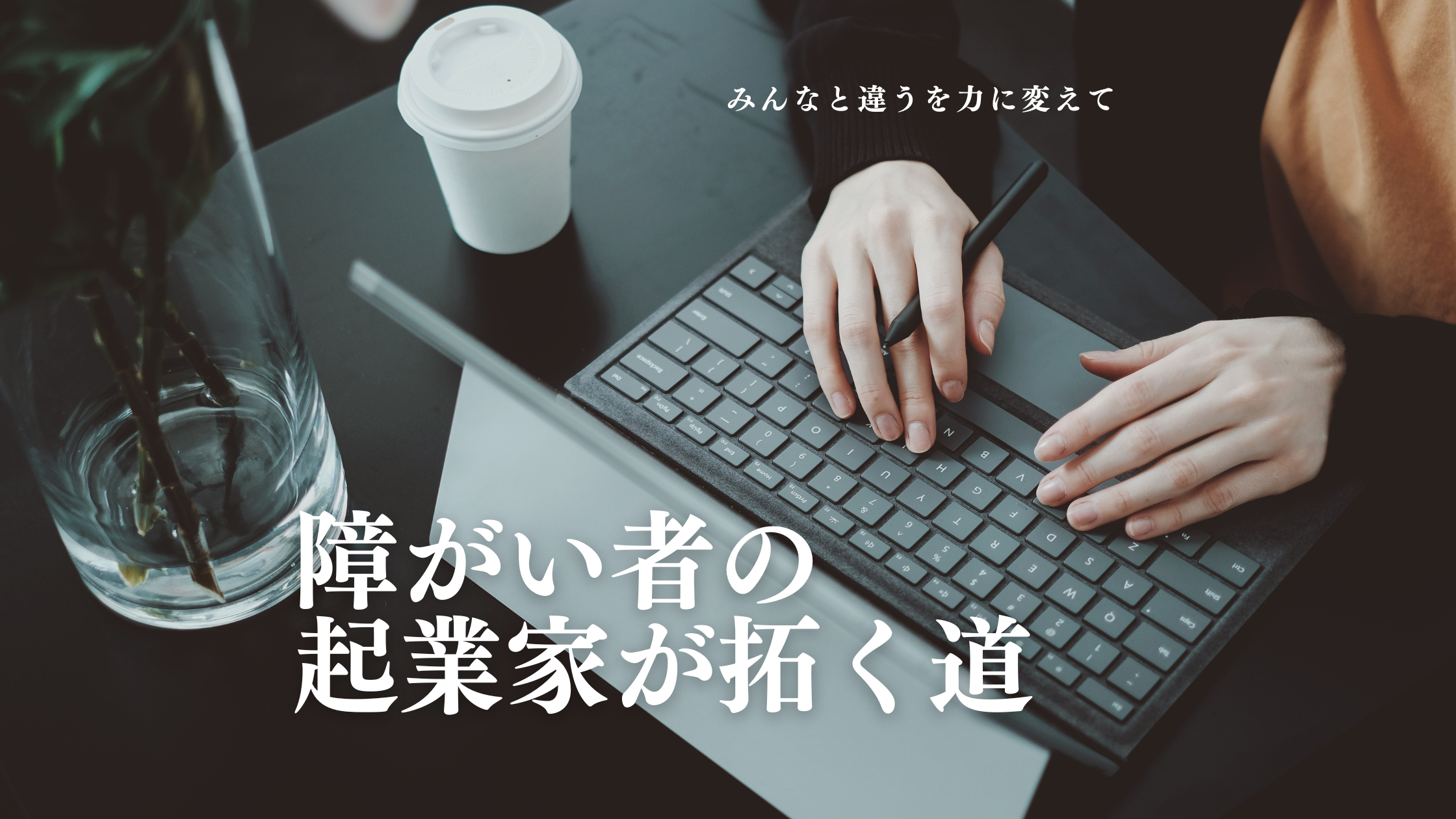
障がいは社会の中で時に「制約」として見られることがあります。
しかし、近年ではその経験や特性を逆に「強み」として活かし、起業家として道を切り拓く人たちが増えてきました。
従来の「障がい者=支援される側」という一面的なイメージを覆し、自らビジネスを立ち上げる姿は、多くの人に勇気を与えています。
この記事では、障がいを持ちながら起業に挑む人々の事例や背景、そこから学べるヒントについて紹介します。
障がいを強みに変える起業家たち

経験を事業の原点にする
障がいを持つ人の中には、自らが直面した課題を解決するためにビジネスを始めた人が少なくありません。
たとえば、移動の不便さを経験した車椅子ユーザーが、バリアフリーな旅行サービスを立ち上げる。
あるいは、発達障がいの特性を活かして、ITやデザインなどの分野で独自のサービスを展開する。
こうした事例は「必要は発明の母」という言葉を体現しています。
当事者だから生まれる共感
自らが障がい当事者であることは、顧客の気持ちを深く理解する強みになります。
例えば聴覚障がい者が手話を使ったオンライン教育サービスを運営する場合、利用者にとって「分かってもらえる安心感」が大きな魅力となります。
参考リンク:起業家インタビュー 誰かの「行きたい」のために 情報の力でバリアを越える 「WheeLog」代表・織田友理子さん
起業の背景にある社会の変化

障がい者雇用から起業へ
日本では法定雇用率によって障がい者雇用が進められていますが、「働きたい分野での仕事がない」「能力が活かせない」と悩む人も少なくありません。
そんな中で「自分で仕事をつくる」という発想が注目されるようになりました。
ICT技術が拓く可能性
インターネットやクラウドサービスの普及により、障がいがあっても在宅でできる仕事やオンライン事業が広がっています。
ECサイトでの販売、SNSを使った集客、オンライン講座の提供など、場所に縛られない働き方が起業の追い風になっています。
参考動画:発達障害・うつ 仕事を入社4か月で退職。企業したら楽になった話
実際の起業事例

1. カフェ経営で地域とつながる
聴覚障がいを持つ人が経営する「手話カフェ」では、手話が使える環境を提供しながら一般客との交流を生み出しています。
地域にとっても新しい文化の交流拠点となり、ビジネスとしても持続的に成長しています。
2. eスポーツでの挑戦
発達障がいの特性を持つ若者が集まり、eスポーツチームを立ち上げた例もあります。
集中力や得意な分野を武器にしながら、スポンサーやイベント出演を通じて事業化するケースです。
3. アートやデザインを事業に
知的障がいを持つ人が描いた絵を商品化し、グッズやアパレルとして販売する事業所も注目されています。
独自の感性は他にない魅力となり、ファンを獲得しています。
起業を支える仕組みと支援
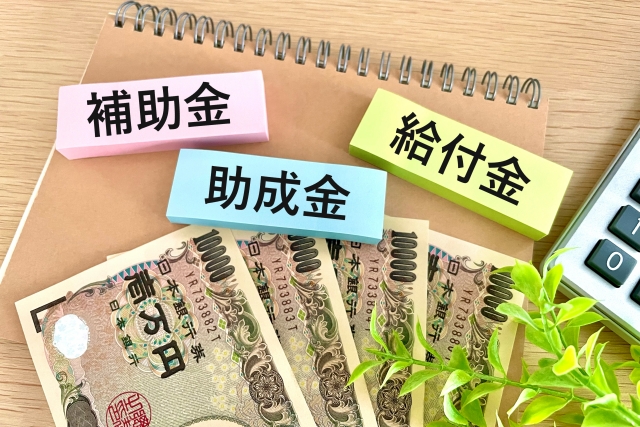
補助金や制度
障がい者が起業する際には、補助金や融資、活用できる制度があります。
- 起業支援制度「県女性・若者・障害者創業支援融資」(茨城県)
- 創業支援等事業者補助金
- 小規模事業者向け融資(日本政策金融公庫)
- ものづくり補助金
障がい者に特化した助成金はありませんが、個人事業税が減免、または非課税になる可能性があります。
参考リンク:起業したい障害者に向けた助成金制度はある?利用できる制度を紹介
民間のサポート団体
NPOや起業支援団体も、障がい当事者の起業を応援しています。
ビジネスプラン作成の支援や、クラウドファンディングのサポートを行う団体もあります。
参考リンク:創業・ベンチャー支援センター
障がいを持つ起業家に学ぶ生き方のヒント
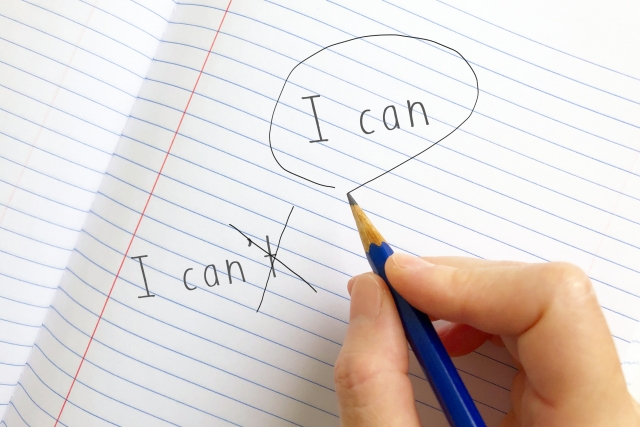
「できないこと」より「できること」に目を向ける
白黒思考ではなく、自分にできる範囲や得意分野を活かすことで、新しい可能性が開けます。
「違い」が強みになる
「みんなと同じ」ではなく「みんなと違う」からこそ見える視点があります。
そこに価値を見出すことが起業家精神につながります。
社会とつながる勇気を持つ
起業を通じて地域や顧客とつながることができます。
それが自分の自信を育て、さらに事業の発展につながるのです。
おわりに:みんなと違うからこそ拓ける道
障がいを持つことは「ハンデ」だけでなく「個性」であり、起業の大きなエネルギー源となり得ます。
今後さらに、障がい者起業家が増えることで、多様性を受け入れる社会が加速していくでしょう。
もしあなたが「やりたいことがあるけど不安」と思っているなら、先輩起業家の事例や支援制度を参考にして、一歩を踏み出してみませんか?
参考資料:障害者による創業・起業