- 情報
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
- 仕事
支援される側から、支援する側へ。経験を力に変えた人のストーリー
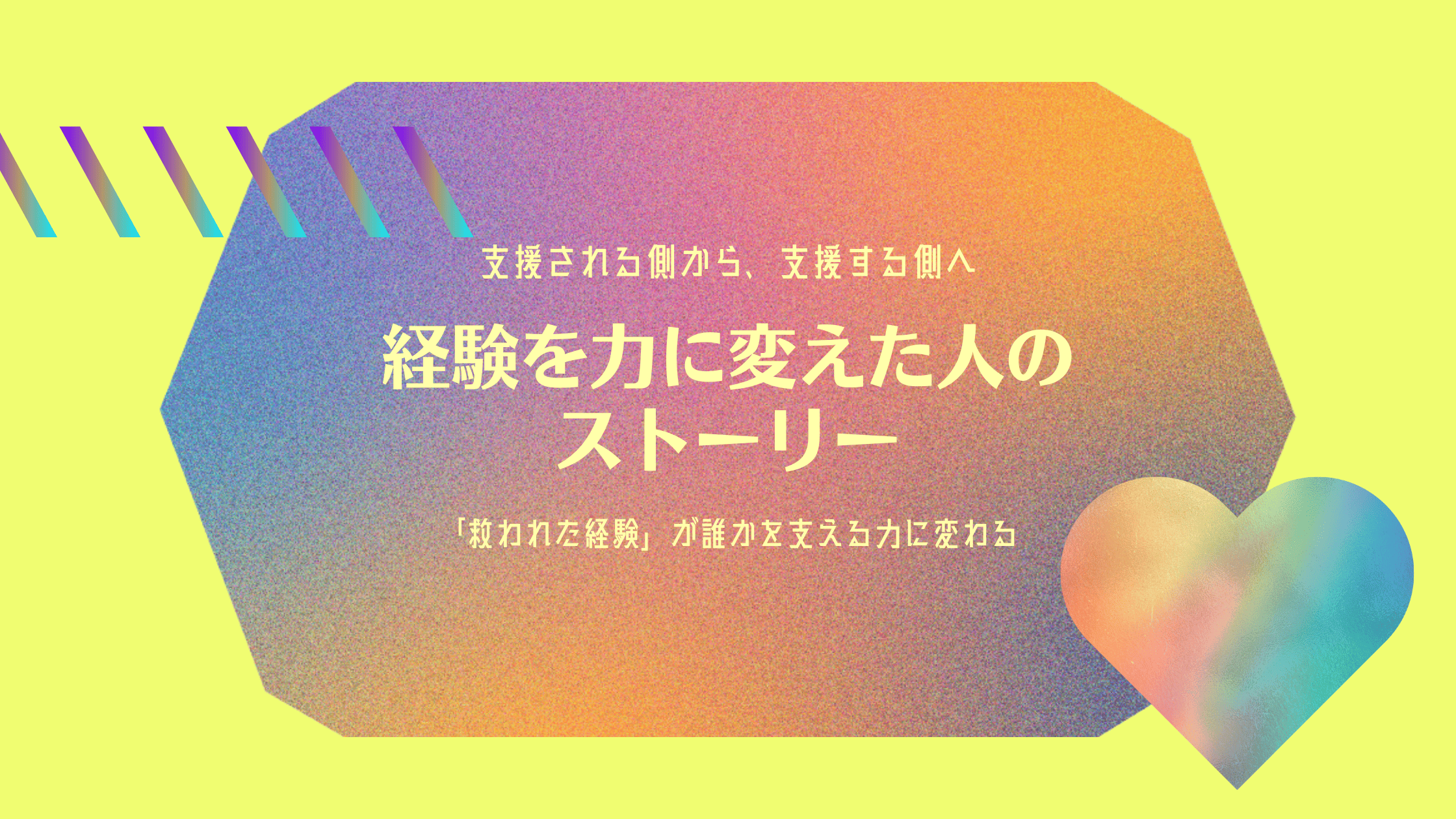
はじめに:「救われた経験」が誰かを支える力に変わる
人生には支援を受ける時期もあれば、誰かを支える側に立つ時期もあります。
特に精神障害当事者や身体障害者などが「支援する側」へ転じる場合"同じ経験を乗り越えた人だからこそ伝えられる言葉"が、多くの人に力を与えます。
この記事では、当事者から支援者へ歩んだ具体的な事例や制度も含め、その力の構造を探ります。
当事者経験から支援者へ:成功事例に学ぶ

ピアスタッフとして就労し、支援を広げたケース
精神障害を抱えていたAさんは、就労継続支援B型を経てピアスタッフ職員として採用されました。
その後、当事者会の設立や電話相談センターの運営なども手掛け、経験を基にした支援活動を軸にしています。
参考リンク:堀合 研二郎 氏「精神障害を持つ本人として 同じ境遇の人の助けになりたい」
「ギルドケア」による支援活動スタート
「支援を受ける側」から一歩踏み出し、「保護ではなく機会を与える」を理念に活動するギルドケアでは、多くが元利用者。
社会で孤立しがちな境界知能や発達障害の人々に対して、機会を作ってきた実践が評価されています。
参考リンク:きっかけをつくるギルドケア
ピアサポート導入で支援の質向上
就労の場において、当事者経験を持つ支援者(ピアサポーター)の存在により、職場全体に“リカバリーの視点”が浸透し、偏見の減少や支援の質向上に繋がった事例もあります。
参考リンク:障害者職業総合センターNIVR
支援者としての葛藤と学び

当事者経験が諸刃の剣に
当事者だからこそ特有の共感や理解を提供できる一方で、同じ経験でも背景が異なることへの葛藤や、主観の押し付けを自覚するケースもあります。
支援者は、当事者としての経験を活かしながらも、自他の違いをわきまえる必要があるのです。
参考リンク:当事者が支援者になるということ
「内と外」からの理解が支援を深化させる
支援の現場では、定型者(非当事者)と当事者の双方が、「支援する側」「される側」として互いに意見を交わす機会が重要です。
「支援者が理解できない」ものであっても、話し合いを通じて歩み寄りが成されます。
参考リンク:発達支援交流サイト はつけんラボ
制度と仕組みで支援者を応援する仕組み

「ピアサポート体制加算」に見る制度的後押し
精神障害当事者が支援に携われる仕組みとして、障害福祉サービス報酬に「ピアサポート体制加算」が導入され、制度として当事者支援者の位置づけが強固に。
特に50代など同世代の支援者による就労支援も効果を上げています。
参考リンク:場面緘黙症とうつ病日記
リカバリーカレッジなど共に学ぶ教育の場
イギリス発のリカバリーカレッジは、支援者と利用者が対等な「学生」として共に学ぶ場。
当事者と支援者が共創しながら回復を目指す教育モデルは国内でも注目されています。
参考リンク:リカバリーとは医療現場でどのような意味を持つ?種類や支援の方法を解説(医師ジョブblog)
支援される喜びが支援する力に変わる瞬間

共感がもたらす安心とエンパワメント
当事者同士だからこそ生まれる「あなたの気持ちわかる」という理解は、安心感と自尊心を育てる。
そのプロセスそのものが、支援を“受け取る”を超えた共創となります。
参考リンク:当事者の関わり(ピアサポート)について
自分の物語を語ることの力
自身のリカバリーストーリーを話すことで、同じ悩みを抱える人に希望が届く。
語ること自体が“支援者になるプロセス”にもなり得ます。
こうした活動は「リカバリーのバトン」として次につながる力になるのです。
参考リンク:世田谷区ピアサポート活動ワーキンググループ
まとめ|支援される「経験」が、人を支える力になる社会へ
「支援される側」から「支援する側」へ。
そこには、自分が受けたケアを次の誰かへつなぐ、強い意志とやさしさがあります。
社会において当事者の声や視点が活かされることで、支援はより豊かになり、相互理解と共生が進みます。
あなたのその一歩が、支援する力を育むきっかけになるかもしれません。