- 精神障がい
精神障害経験者は“メンタルの先輩”!人を支える力がある
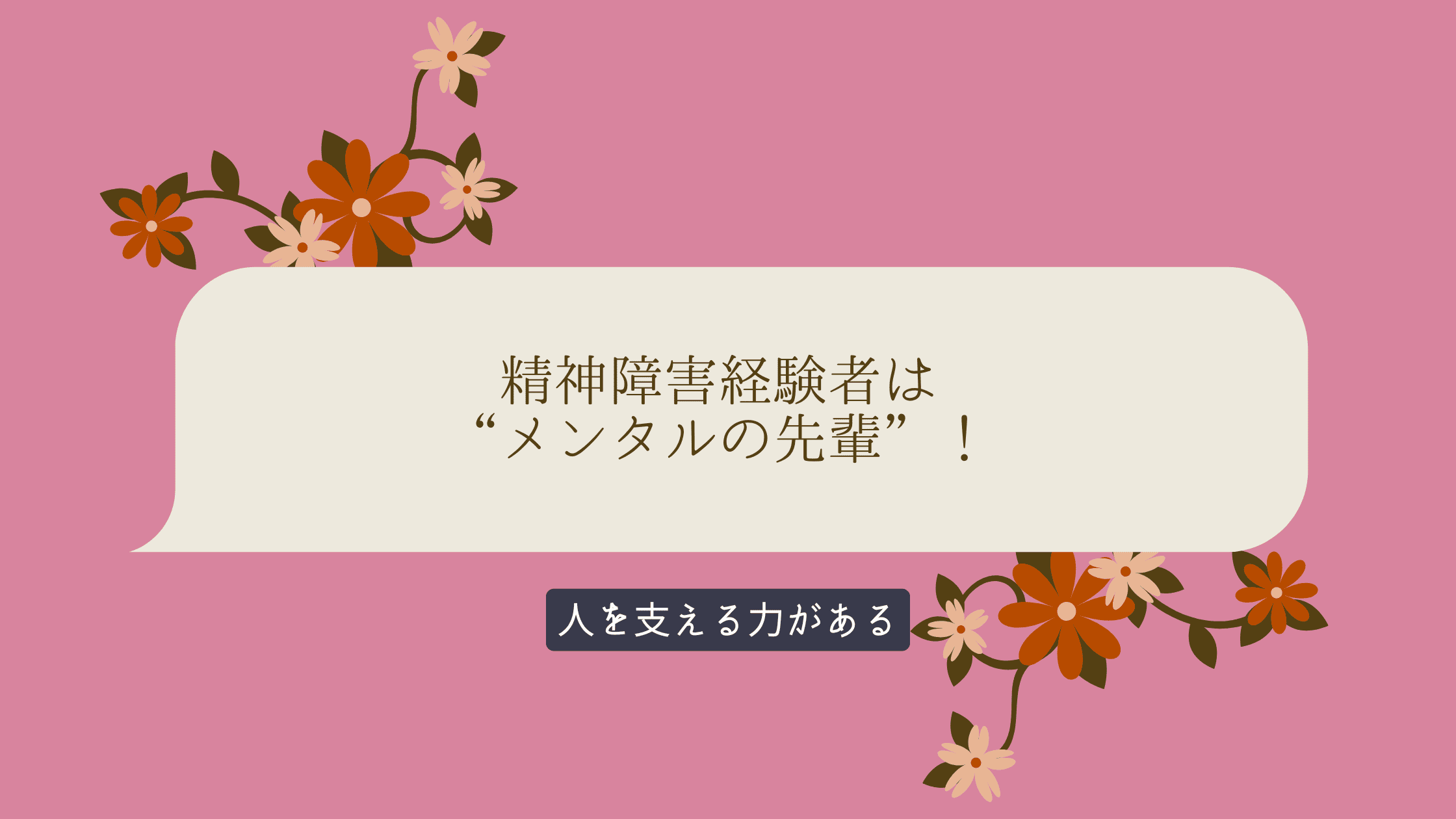
はじめに:経験が“支えの力”になる理由
しかしその経験を乗り越えたからこそ見えてくる「支え合いの価値」。
精神障がいは、痛みや困難を伴うものです。
経験した人だからこそ発揮できる共感や気づきが、同じ悩みを抱える人にとっては大きな励みになります。
当事者が“メンタルの先輩”として活躍する価値と背景を探っていきます。
ピアサポートとは何か:経験知から生まれる支援

ピアサポートの源流と日本での広がり
ピアサポートは、1900年代初頭のアメリカで発生した精神科医療への反発から始まり、同じ経験を持つ者同士による支え合いが基盤となっています。
日本ではセルフヘルプグループやクラブハウス形式の活動を経て、リカバリー志向の支援として定着しています。
参考資料: 厚生労働省
当事者自身が「先輩」として活躍する背景
たとえば、ある精神障がい当事者は精神保健福祉士の資格を取得し、大学院で学びながら仲間への講演や執筆を行っています。
こういったおなじ障がいを持つ人が努力する姿に「私も頑張ろう」と感化される仲間も多いです。
参考リンク:ピアサポートとは何か
回復と支え合いのプロセス|支援の質が高まる理由

回復過程で得られる共感力
ある研究では、精神障がい当事者が地域の精神科デイケアを利用する中で「似た立場の人を助けたい」と感じ、自然とピアサポートへの参加が進んだことが明らかになっています 。
自分が回復した経験が他者への支えに変わる心理がここにあります。
参考リンク:SpringerLink
精神的距離の近さが安心を生む
当事者同士だからこそ「言いにくさ」や「遠慮」が少なく、本音が共有できます。
「理解されている」「分かってくれる」安心感は、専門職には真似できない支援の質につながります。
ピアサポートの社会的意義と実践

地方自治体での制度的導入
福島県では、ピアサポーターの養成研修を修了した方を認定し、退院促進や地域定着支援などを担う制度を導入。
地域生活の構築に当事者の回復ストーリーが役立っている事例があります。
参考資料:ピアサポーターを活用した事業事例集
専門職との協働による支援の質向上
精神保健福祉士や看護師など専門職とピアスタッフが協力することで、支援の幅が広がります。
日本の実践例では、専門職がピアスタッフとの協働から得た学びについても報告されています。
参考資料:メンタルヘルス領域におけるピアスタッフとの協働にむけた専門職者の経験
メンタル“先輩”の支えを日常へ活かす工夫

自分の経験を語ることで希望になる
ピアサポーターが自身の回復までの過程を語ることは、同じ苦しみに悩む人に「自分もできるかも」という希望を届けます。
実話としての語りは、最も心に響く支援になります。
支え合いの場を作る意義
グループ形式やコミュニティ形式の支え合いの場では、互いに支え、支えられる関係が生まれます。
「自分も誰かの支えになれる」という体験は、自尊感情と社会参加を促進するのです。
まとめ:“メンタルの先輩”が照らす未来
精神障がい経験者には、自分の経験を活かして人を助ける“先輩”としての価値があります。
その強みをシステムとして活かすことが、誰もが支え合える社会につながります。
アサーションや支援体制と同じように、当事者自身の声と経験をもっと社会に届けていきましょう。