- 睡眠
- 生活
- 身体障がい
- 痛み
【保存版】片麻痺・しびれで眠れない夜に|身体障がいと快適な眠りのための対策ガイド
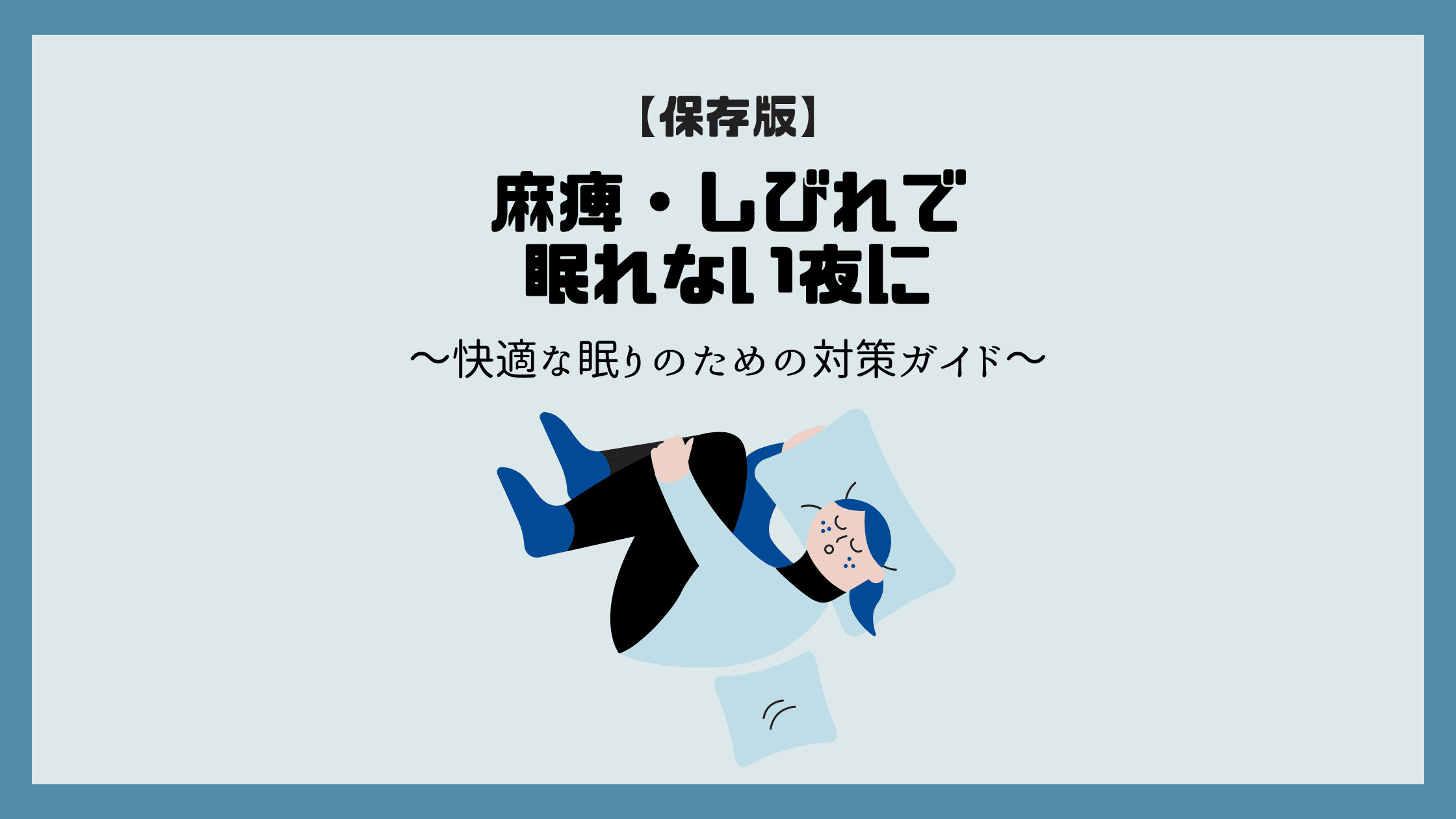
身体障がい、特に麻痺を伴う方にとって、夜の「眠れなさ」は非常につらい問題です。
しびれや痛み、体位交換の困難、寝具との相性など、眠るために乗り越えなければならない障壁は想像以上に多く存在します。
本記事では「麻痺によるしびれや痛みで眠れない」という悩みに焦点を当て、原因から具体的な快眠対策、福祉用具やサポート情報までを幅広く紹介します。
眠りの質を少しでも改善し、毎日の生活に少しでも楽さを取り戻すヒントとなることを願って。
1. 麻痺と睡眠の関係|なぜ眠りにくいのか

麻痺のしびれ・疼痛が眠りを妨げる
麻痺のある方にとって、「しびれ=感覚が鈍い」と思われがちですが、実際にはジリジリ・ビリビリとした不快な感覚や痛みが続き、それが睡眠を大きく妨げる要因となります。
これは「中枢性疼痛(ちゅうすうせいとうつう)」と呼ばれ、脳卒中や脊髄損傷の後遺症でよく見られます。
寝ようとするとかえって痛みやしびれに意識が集中し、リラックスが難しくなる。
そんな悪循環を、多くの方が経験しています。
体位の自由がきかず、寝返りが難しい
健常な体であれば、無意識に寝返りを打つことで血流や筋肉の緊張を調整しながら眠れます。
しかし麻痺があると、麻痺側に負荷をかけることが難しく、同じ姿勢が続いてしまうことが多くなります。
その結果、圧迫感や不快感が強まり、途中で目が覚めたり、浅い眠りしか取れなかったりします。
精神的ストレスや不安も睡眠を悪化させる
「また今夜も眠れないのでは」
「横になるのが怖い」
といった不安やストレスも、睡眠を妨げる大きな要因です。
こうした不安は脳の覚醒を高め、自律神経のバランスを崩しやすくなり、眠りが浅くなるという悪循環を招きます。
2. 医学的に見た「片麻痺としびれ」の仕組み

中枢性疼痛と末梢性疼痛の違い
しびれや痛みには大きく分けて「中枢性」と「末梢性」の2種類があります。
- 中枢性疼痛:脳や脊髄に損傷がある場合。感覚が異常に増幅される。
- 末梢性疼痛:神経が圧迫・損傷されて起こる。ピリピリ、チクチクすることが多い。
片麻痺では、脳卒中などによる中枢性の感覚障害が多く見られ、治療が難しいこともしばしば。
しびれがあるからといって「感覚が残っている証拠」と誤解されることもありますが、しびれや痛みは“回復とは関係ない苦痛”であることが多いのです。
自律神経と痛みの関係
痛みや不快感が続くと、自律神経が乱れがちになります。
特に交感神経が優位になると、身体が「戦闘モード」になってしまい、睡眠に適した状態を作れません。
しびれを「気にしないようにする」だけでは解決しにくい理由はここにあります。
専門医に相談すべきタイミング
しびれや痛みが強くなってきたり、眠れない状態が続いて生活に支障をきたしている場合は、ペインクリニックやリハビリ科の専門医に相談することが大切です。
薬物療法・神経ブロック・運動療法など、多角的なアプローチが可能なこともあります。
参照:ペインクリニックとは
3. 快眠を支える工夫と対策

寝具を見直す
マットレス・まくらの選び方
片麻痺がある場合、体圧分散型のマットレスが有効です。
麻痺側への圧迫を減らし、寝返りをしやすくする構造になっているものを選ぶと、負担を大幅に減らすことができます。
まくらも、首と肩のラインに合った高さや硬さが重要。
麻痺側を下にして寝ることが多い方は、左右で高さや硬さが違う「左右非対称の枕」も試してみる価値があります。
参照:THE PILLOW(左右非対称の枕)
姿勢サポート用のクッションや抱きまくら
横向きにしか寝られない、仰向けが苦しいという場合、身体の傾きを安定させるサポートクッションがあると非常に便利です。
特に「抱きまくら」や「膝下に入れるクッション」などは、筋緊張を緩和しリラックスに役立ちます。
「体が沈みすぎない」「自然に支えてくれる」タイプを選びましょう。
しびれを緩和する温熱・冷却ケア
寝る前に温熱パッドや湯たんぽで麻痺側を温めることで、しびれが和らぐ場合があります。
逆に、炎症や浮腫がある場合はアイスパックで冷やす方が楽になることも。
どちらが合うかは個人差があるため、症状や体調に応じて試してみるのがよいでしょう。
4. 日常生活からできる快眠習慣づくり

寝る前のリラックスルーティンを整える
眠る前にスマホやテレビを見ると脳が興奮し、眠りが遠ざかります。
その代わりに、以下のような「寝る前習慣」を取り入れてみましょう!
- ゆっくりとしたストレッチ(可能な範囲で)
- 湯船につかって体を温める
- 好きな音楽やアロマでリラックスする
こうした習慣が「眠るスイッチ」を自然と入れてくれます。
▽オススメの寝る前ストレッチはこちら
カフェイン・アルコールの摂取を控える
意外と見落とされがちなのが、「飲み物の影響」。
カフェイン(コーヒー、緑茶、エナジードリンク)は覚醒作用があり、しびれを強く感じさせることもあります。
またアルコールも、眠りが浅くなり途中で何度も目が覚めてしまいます。
就寝前はカフェインレスのハーブティーや白湯などがオススメです。
参照:NELL(ネル)マットレス ハーブティーは安眠に効果あり?おすすめの飲み方や注意点を解説
日中の過ごし方が夜の眠りを左右する
昼間に体を動かさずずっと座っていると、夜の眠気がうまく訪れません。
片麻痺があっても、少しのストレッチや軽い活動を心がけることで、体内時計が整いやすくなります。
また、朝起きたら太陽の光を浴びることで、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が安定します。
参照:無呼吸ラボ 乱れがちな体内時計のリズムを保つ鍵は太陽の光にあり
5. 薬や治療に頼ることも選択肢に

神経痛や不眠に効果のある薬の活用
どうしても眠れない日が続く場合、医師の処方による神経痛緩和薬(プレガバリンなど)や睡眠導入剤の活用も視野に入れましょう。
自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、症状に合った薬を短期的に使うことで心身を整えることも大切です。
漢方やサプリメントも検討
西洋薬が合わない方には、漢方薬やハーブ由来のサプリなども選択肢になります。
たとえば「芍薬甘草湯」や「加味逍遙散」は、筋緊張や自律神経の乱れに効果があるとされます。
ただし、体質によって効き方が異なるため、薬剤師や医師に相談のうえで取り入れるのが安心です。
通院だけでなく訪問診療や在宅リハも視野に
通院が難しい方は、訪問リハビリや在宅診療の仕組みもあります。
理学療法士や作業療法士に来てもらって、寝具の見直しやストレッチのアドバイスを受けることで、快眠への近道となることもあります。
おわりに:「眠れる自分」を少しずつ取り戻すために
「しびれが強くて、今夜も眠れないかもしれない」
そんな不安な夜を何度も経験している方にとって、眠りの質が生活のすべてを左右すると言っても過言ではありません。
完璧な解決策は見つからなくても、「少しでも楽になる方法を重ねていく」ことが未来の自分を支える力になります。
無理をせず、自分にやさしく、今日できることをひとつずつ。