- 夏
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 感覚過敏
障がい者でも花火大会・夏祭りに行きたい!
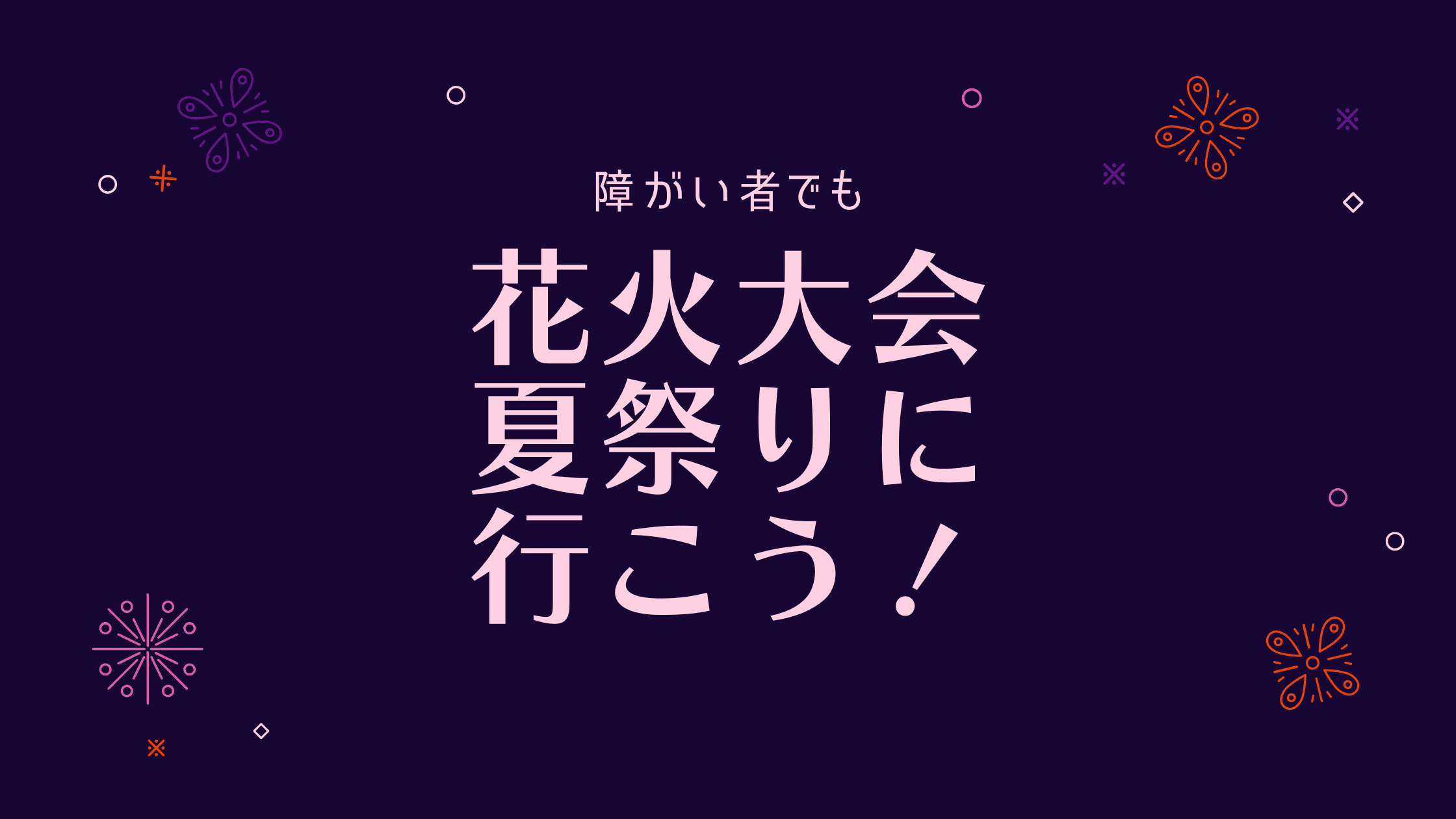
毎年夏になると、全国で花火大会や夏祭りが開催されます。
しかし、障がいや感覚過敏などの特性を持つ人にとっては、「行ってみたいけど不安」という声も少なくありません。
そこで本記事では、障がいの種類別に「どんな配慮があると安心して楽しめるか」「おすすめの準備・サービス」などを紹介します。
車いすや歩行困難な方が安心して参加するために

バリアフリー観覧エリアの選び方
会場によっては車椅子専用スペースが設けられており、案内誘導のあるところもあります。
たとえば都内では車椅子優先レーンや多目的トイレ完備の例も多く、事前に主催者や公式パンフレットで確認することが大切です。
旅行ツアーで安心プラン
障がいのある方向けに添乗員付きで負担軽減した旅行ツアーも増えています。
熱海や高山など温泉地で花火を観覧するプランでは、車椅子席・移動サポートが整っており安心です。
視覚障がい・聴覚障がいのある方が楽しむ工夫

花火×音楽×朗読劇の融合
「みんなの花火」プロジェクトでは、障がい者アーティストの歌や手話通訳、点字パンフレットや花火朗読劇など、視聴覚に障がいがある方でも楽しめる演出を提供しています。
参考リンク:PR TIMES
音と振動で楽しむ工夫
大曲の花火では、振動型デバイス(例:Hapbeat)や難聴者用スピーカーを活用した実験的な取り組みがあり、映像に頼らず五感で楽しむ仕組みが試されました。
参考リンク:PR TIMES
精神障がいや自閉症スペクトラムのある方が楽しむ工夫

混雑や音が苦手な方向けに
多くの花火会場では、早めに到着して静かな鑑賞スペースを確保する工夫が重要です。
川原など混雑しやすい場所を避けるのが安心です。
休憩できる場所と時間を確保
会場周辺に座って過ごせるスペース、公園の芝生、休憩所などを確認しておきましょう。
予備の飲料や耳栓・アイマスクなども準備することが役立ちます。
ゆったり楽しめる場所選び
観客の少ない穴場スポットや混雑が緩やかな小規模イベントを選ぶことで、過度な刺激を避けつつ楽しめます。
感覚過敏がある人が楽しむ工夫

音・光・においの刺激に注意
感覚過敏のある方は、「音」「光」「におい」などの強い刺激に苦しむことがあります。
とくに花火大会では、
・爆音(音の刺激)
・光のフラッシュ(視覚刺激)
・人混みと屋台のにおい(嗅覚刺激)
が大きな負担になることも。
対策アイテムを活用しよう
・ノイズキャンセリングイヤホンやイヤーマフ
・サングラス
・マスク
これらのアイテムで刺激を軽減できます。
事前に会場の動画で雰囲気を確認して、無理のない参加を心がけましょう。
参考リンク:精神科看護特化型訪問看護ステーション
家族や友人と一緒に楽しむためのポイント

情報収集は早めに
障がいを持つ方が同行する場合、事前に車椅子スペースの人数やバリアフリー案内有無を確認することを推奨します。
ツアー・イベントを活用する
観覧席確保や介助体制の整備された添乗員同行の夏祭り・花火イベントを利用すれば安心して参加できます。
アクセシビリティへの対応事例
障がい者対応ツアーでは、歩行補助車両、貸出車椅子、障がい対応トイレなど、ハードとソフトの両面から配慮が提供され、参加者に好評です。
参照リンク:心の翼バリアフリーツアー
行きたい!参加したい!おすすめ花火大会・夏祭り事例
立川まつり国営昭和記念公園花火大会(東京)
5000発の打ち上げとともに、身体障がい者用駐車場、多目的トイレ(39か所)など、設備面が充実しています。
混雑緩和のため事前来場が推奨されています。
隅田川花火大会(東京)
東京最大級の人気大会ですが、公式パンフレットに車椅子優先エリアや案内情報が記載されています。
早めのルート確認が安心です。
大曲の花火 秋の章(秋田)
「障がい者も楽しめる花火」として、視覚・聴覚障がい者向けの朗読劇や振動体験を試行。
特別な配慮のある芸術体験として注目されています。
安全・快適に楽しむための事前準備ガイド

混雑時間を避けて訪れる計画を
入場ピークや終了直前は混雑が最大になりますので、早めの移動・場所確保が鍵です。
帰り道の安全確保も考慮しましょう。
支援機器・用品の持参と使い方
車椅子用の簡易チェア、歩行補助杖、耳栓やアイマスク、予備の飲料・医薬品など、緊急時にも対応できる準備が望まれます。
周囲と連携する安心感
当日現地の係員やボランティアに早めに声をかけておくと、案内や配慮につながります。
受付やインフォメーションセンターの利用も有効です。
まとめ:すべての人が夏の魔法を楽しめるように
障がいがあっても、花火大会や夏祭りの楽しみはあきらめる必要はありません。
事前準備・情報確認・配慮された観覧環境を整えることで、安心して参加できる場が増えています。
あなたや家族、友人が同じ夏の風景を共有できるよう、ぜひ参考にしてみてください。