- 福祉
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
感動ポルノ(インスピレーションポルノ)って何?障がい者を“見せ物”にしないために
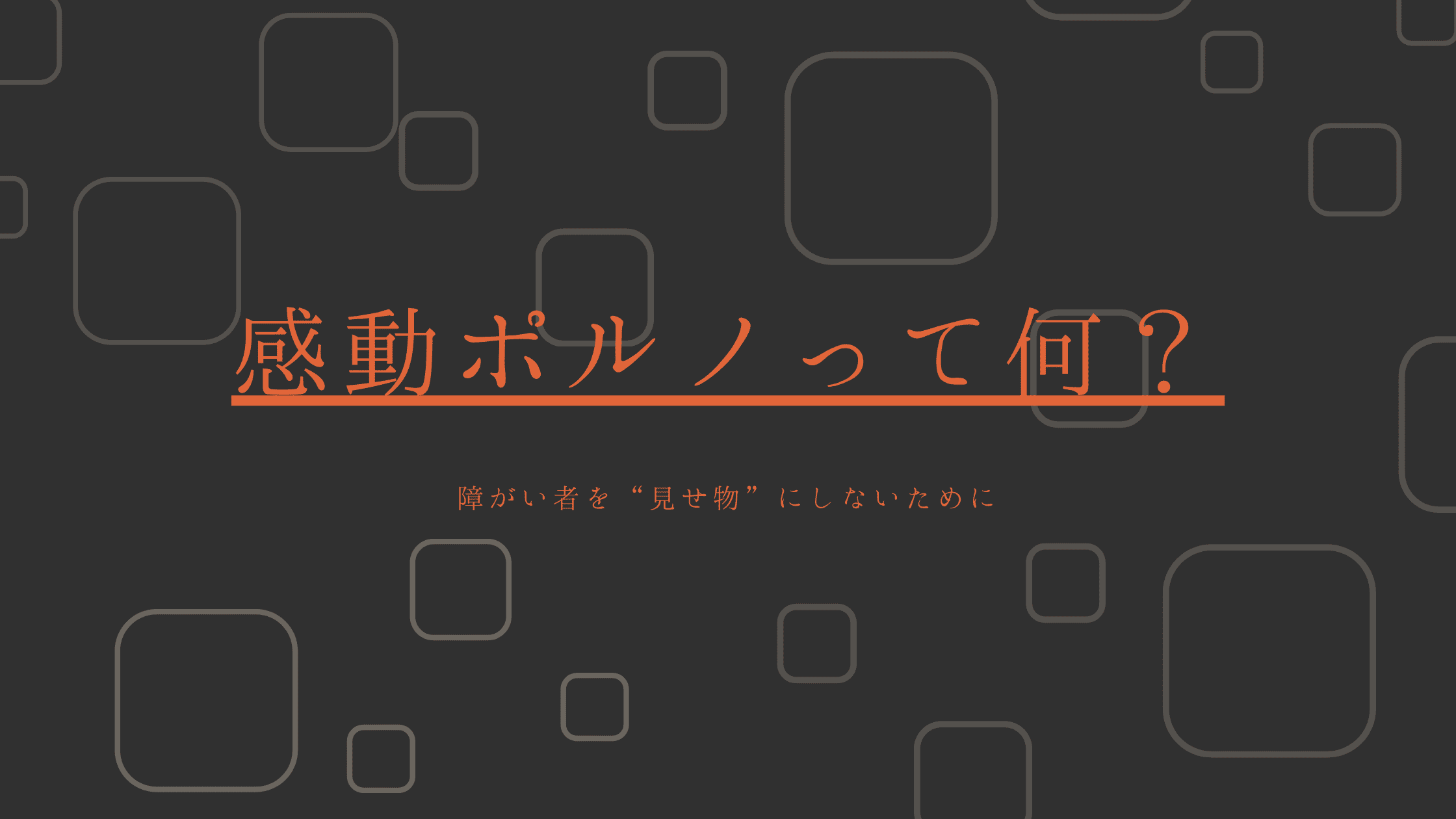
障がいを持つ人の「頑張って克服する姿」「勇気をくれる存在」というイメージが、メディアやSNSでは頻繁に流通しています。
一見、前向きでポジティブに思えるその描かれ方にも、実は重大な問題が潜んでいます。
これが、いわゆる「感動ポルノ(Inspiration Porn)」と呼ばれる現象です。
この記事では、障がいをめぐるこの構図を、日本のメディアや社会のなかで改めて検証します。
なぜ問題とされるのか、当事者・支援者はどう向き合うべきか、そして私たちにできることは何かを一緒に探っていきましょう。
メディアと「感動ポルノ」の構図

「障がいを乗り越えた人=感動を与える人」という物語
テレビ番組やチャリティ番組では、障がいのある人が“挑戦”して“克服”する姿が強調されることがあります。
NHKの番組、バリバラでは「検証!〈障害者×感動〉の方程式」という回でこの構図を問いかけています。
このような物語の構造には、障がい → 努力 → 成功/克服 →健常者を感動させる、というような流れが隠れていることがあります。
こうした描かれ方は、障がいをもつ人を「感動を提供する存在」「否定的な期待を払拭するための素材」として扱ってしまうリスクがあります。
参考リンク:〝感動ポルノ〟求める社会って?バリバラ大橋さんが伝えたかったこと
「障がい者役割」が強化されるという批判
学術的には「障がい者役割(disability role)」という概念があり、障がいを持つ人が「困難を克服すべき存在」「可哀そうな存在」という期待の枠に押し込められてしまうと指摘されています。
この枠組みでは、当事者が“普通に生きる”ということ本来の選択肢が見えにくくなり、「特別でなければならない」というプレッシャーを生むこともあります。
参考リンク:「感動」するわたしたち──『24時間テレビ』と「感動ポルノ」批判をめぐって
日本における事例と社会的な反応
例えば、 24時間テレビ のような大型チャリティ番組では、「障がいを持ちながら~」という感動ストーリーが多く扱われてきました。
これに対して「障がいを持つ人を見世物のように扱っている」という批判も出ています。
また、当事者・親の立場から「私の子どもはあなたの感動のための存在ではない」といった声もあがっています。
参考リンク:なぜ「24時間テレビ」は「感動ポルノ」に変わったのか…日本テレビがそれでも番組を継続する理由、障がいのある私の娘は、あなた方の「感動ポルノ」ではない
なぜ「感動ポルノ」が障がい者にとって問題になるか

当事者の主体性を削ぐ可能性
「障がいをもっていても頑張ってるね」という言葉が、本人の意思や背景を抜きに繰り返されると、「これを達成しなければ価値がない」といったプレッシャーになりえます。
実はこの言葉が、当事者が感じる“ただ存在していい自分”を奪いかねないのです。
多様な人生/多様な障がいの経験を縮小してしまう
感動ポルノ的な構図では、障がい者が「困難を克服する」物語に偏重し、「生きづらさ」の語られ方が一面的になります。
それは「成功した人」だけが注目される構図を作り、苦しみ・日常・失敗・変化の過程を軽視する傾向があります。
社会的期待と疲弊を生む
「障がいをもっててもこのくらいできるね」といった称賛も、裏では「当たり前の成果を出さなければならない」という期待になりえます。
結果、当事者は疲弊し、自分のペースを見失うこともあります。
参考リンク:「障害者だから」という古い枠を超えた、自分の意志を言える社会に。 LITALICO発達ナビ
当事者・支援者ができること/発信のヒント

自分の物語を、自分の言葉で語る
当事者のSNS投稿やブログでは、「私はこう感じた」「私はこう考えた」という一人称が増えています。
これは、他者の期待ではなく、自分自身のリアルに焦点を当てる発信方法です。
たとえば、「障がいがある私の日常」や「支援を受ける私」という語られ方ではなく、「私のやり方で生きる」という文脈です。
メディア・支援機関に対して“問い”を持つ
支援機関・メディア・教育機関では、障がい者を“感動させる素材”としないよう、以下の意識が求められます。
- 芝居じみた演出ではなく、当事者の意志・背景をきちんと尊重する
- “成功物語”だけに注目せず、日常・困難・普通を語る
- 当事者の声を制作・発信の中心に置く
周囲の理解を少しずつ変えていく
非当事者も、次のようなことを心がけることで、感動ポルノを回避する社会づくりに貢献できます。
- 「すごいね」だけで終わらず「どんな工夫があったの?」と質問する
- 「頑張ったね」ではなく「あなたのそのままでいい」という視点を持つ
- 障がいを“感動”のための素材とせず、“共に生きる”関係づくりに目を向ける
まとめ:称賛ではなく理解を、物語ではなく関係を
「あなたのそのままでいいよ」という言葉が、私たちがこれから目指す社会の根底にあるべきです。
障がいをもつ人を「頑張ったね」と称賛するだけではなく、彼らが「そのままに生きられる」環境をつくること。
称賛の裏にある“期待”を手放し、モノ化されない、関係性に基づいた社会を少しずつ紡いでいきましょう。
🔗参考リンク
- 「感動ポルノの何が問題なのか?」
https://note.com/androyer/n/n82b6d8ee7c7e - 「チャリティか、感動ポルノか? 身体障害とメディア表現について考える」
https://inclusive-media.net/note-01/1.html - 「『感動ポルノ』という社会の押し付けから見える障がい者差別を考える」
https://mbit.co.jp/mag/column/13267