- マインドセット
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
障がいとともに歩む感謝日記 — 小さな「ありがとう」が強さになる日常
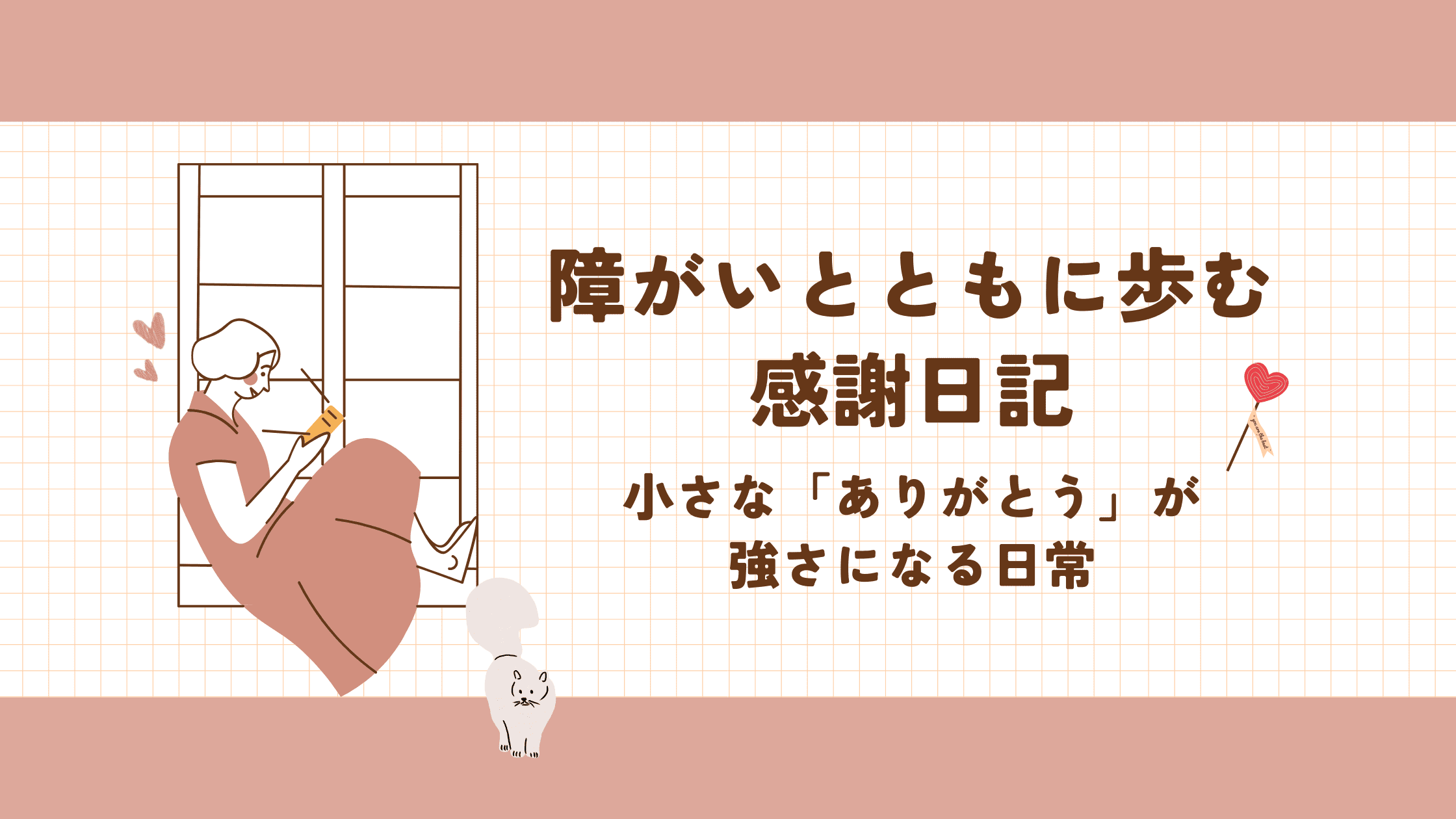
障がいを持って生きていくなかでは、体の制約、環境のバリア、他者の理解不足など、困難に直面することが多いでしょう。
その中で「感謝日記」をつけることは、小さな光を見つけて心を支える習慣として有効です。
感謝日記は「ハッピーなこと探し」ではなく、「現実を受け止めながら希望を育てる」ツールになり得ます。
本記事では、障がい者ならではの視点を踏まえつつ、感謝日記の始め方・コツ・注意点・実践例を紹介します。
感謝日記の効果:研究と実践から見る効用

心と身体の健康を支える作用
感謝日記には、ストレス・うつ・不安の軽減に寄与する効果がいくつもの研究で示されています。
たとえば、香港教育大学の研究では、4週間にわたり感謝日記を週2回書いた医療従事者グループで、ストレス・うつ症状の改善と幸福度の上昇が確認されました。
障がいを持つ人にとって、身体的な痛みや制限、孤立感などと向き合う日々があるからこそ、感謝という行為は「ネガティブ思考のループを断つきっかけ」になり得ます。
参考リンク:世界の研究が証明した「感謝」の驚きの効用
感謝がもたらす関係性の変化
感謝日記を通して自分が受けている恩恵に意識を向けることで、他者への感謝を表現しやすくなります。
恩恵を受けている関係性に気づき、それを言葉にすることは、周囲とのつながりを強め、孤立感を和らげる助けにもなります。
障がいという「受け取る・助けられる」側面を持つ経験は、感謝表現を通じて相互性の輪に変える可能性があります。
障がい者が感謝日記を実践するときの工夫と注意点

小さな「感謝」を見つけられない日への対処
痛みや不調が強い日には「感謝したいこと」がすぐには思い浮かばないこともあります。
そのとき無理に「大きなことを探そう」とするのではなく、ほんの1~2行でもいいので以下のような視点を使ってみましょう
- 「今日は少し体が楽だった時間があった」
- 「暖かい飲み物を飲めた」
- 「スマホで好きな音楽を聴けた」
- 「誰かが優しい言葉をかけてくれた」
こうした小さな光を拾い上げる習慣が、感謝の意識を育てます。
書き方・形式の柔軟性
感謝日記は「こう書かなければならない」ものではありません。
手書きでも、スマホアプリでも、音声で録る方法でもOK。
ベンチャー大学のガイドでは「1日に書く感謝は最大5件。具体性を持たせ、詳細に書くほど効果が高い」と提案されています。
また、「引き算」の視点(もしあの支えがなかったらどうだったか)を書くことで感謝の深まりが増すという手法も紹介されています。
継続と「疲れ感」に配慮する
続けること自体が負担になると逆効果です。
2週間、3カ月など区切りを設けたり、途中で休む期間を入れたりするなど、無理のないペースを設定しましょう。
日本のメディアでも2週間実践の後もモチベーションの維持効果があるという報告があります。
また、ネガティブな感情を無視しないこと。
「感謝できない自分」を責めず、ネガティブを認めつつ、ほんの一瞬の「ありがとう」に意識を向ける態度が大切です。
参考リンク:【感謝日記】“感謝を3つ箇条書き”で毎日が変わる!専門家の解説&体験レポート
感謝日記の書き方ステップとテンプレート

ステップ1:準備とツール選び
手帳、ノート、スマホのメモ、専用アプリなど、自分が楽に使えるものを選びます。
視覚障がいがある人は読み上げアプリ、入力が難しい人は音声入力などの利用が有効です。
ステップ2:感謝を書く時間を決める
夜寝る前など、自分が振り返りやすい時間帯を習慣化。
「寝る前3分」、「起床後5分」など、短時間を目安にすると継続しやすいです。
ステップ3:感謝対象を3つ程度書き出す
具体性を意識して書くと効果が上がります(例:「今日はベッドで痛みが少し軽かった」など)。
また、「誰かへの感謝」「自然・環境への感謝」「経験への感謝」など分けて視点を変えて書くと幅が広がります。
ステップ4:振り返りと表現
感謝したことを読み返してみる、誰かに感謝を伝える、心の中でその「ありがとう」を味わう時間を持つと、感謝の感覚が深まります。
実践例:障がい者だからこそ感じた感謝

エピソード1:車いす利用者の雨の日
Aさん(車椅子利用)は、ある雨の日にバス停で待っていた際、バスの運転手さんが屋根の下で待たせてくれたことを感謝として書きました。
「降りるときに少し手を添えてくれた」
「雨粒が目に入らないように操作板を傾けてくれた」
など、他人の配慮を意識して感謝が深まったと語ります。
エピソード2:視覚障がい者の音の支え
Bさん(視覚障がい者)は、夜道を歩くときに遠くで聞こえた信号音が、自分の位置を教えてくれたことに感謝を書き留めています。
その「音に頼れる瞬間」が、自立感と安心感を与えたとのことです。
エピソード3:慢性痛と小さな快適
Cさん(慢性痛を抱える障がい者)は、不調の合間に「痛みが比較的軽い時間があった」こと、「好きな音楽を数分間聞けたこと」を感謝としています。
大きな出来事ではなく、“その瞬間の快適さ”を拾うことが支えになっていると言います。
感謝日記を続けるための工夫と仲間づくり

リマインダーを活用
スマホの通知やアラーム機能で「書く時間」を知らせてもらうようにすると、忘れにくくなります。
共有・対話する習慣
信頼できる人と感謝項目をシェアする、小さなグループで「感謝を読み合う」場を作ると、習慣の持続性が高まります。
感謝アプリの活用
感謝記録を登録・振り返りできるアプリが登場しており、若年層向けアプリの設計研究も報告されています。
参考リンク:「感謝日記」を実践するのにおすすめノート&アプリ
まとめ:感謝日記で得られる変化
感謝日記を続けた人の中には、日常全体の幸福度が長期的に上がったという報告があります。
障がいを持つ人にとって、感謝日記は「困難と向き合いながらも、光を見つける心の習慣」。
それは自分自身を強くし、支援者・他者との関係を豊かにし、共生社会の文化を育てる一つの方法と言えるでしょう。
参考動画: