- 仕事
- コミュニケーション
【完全ガイド】身体障がいとバリアフリーな職場環境|働きやすさを実現するためにできること
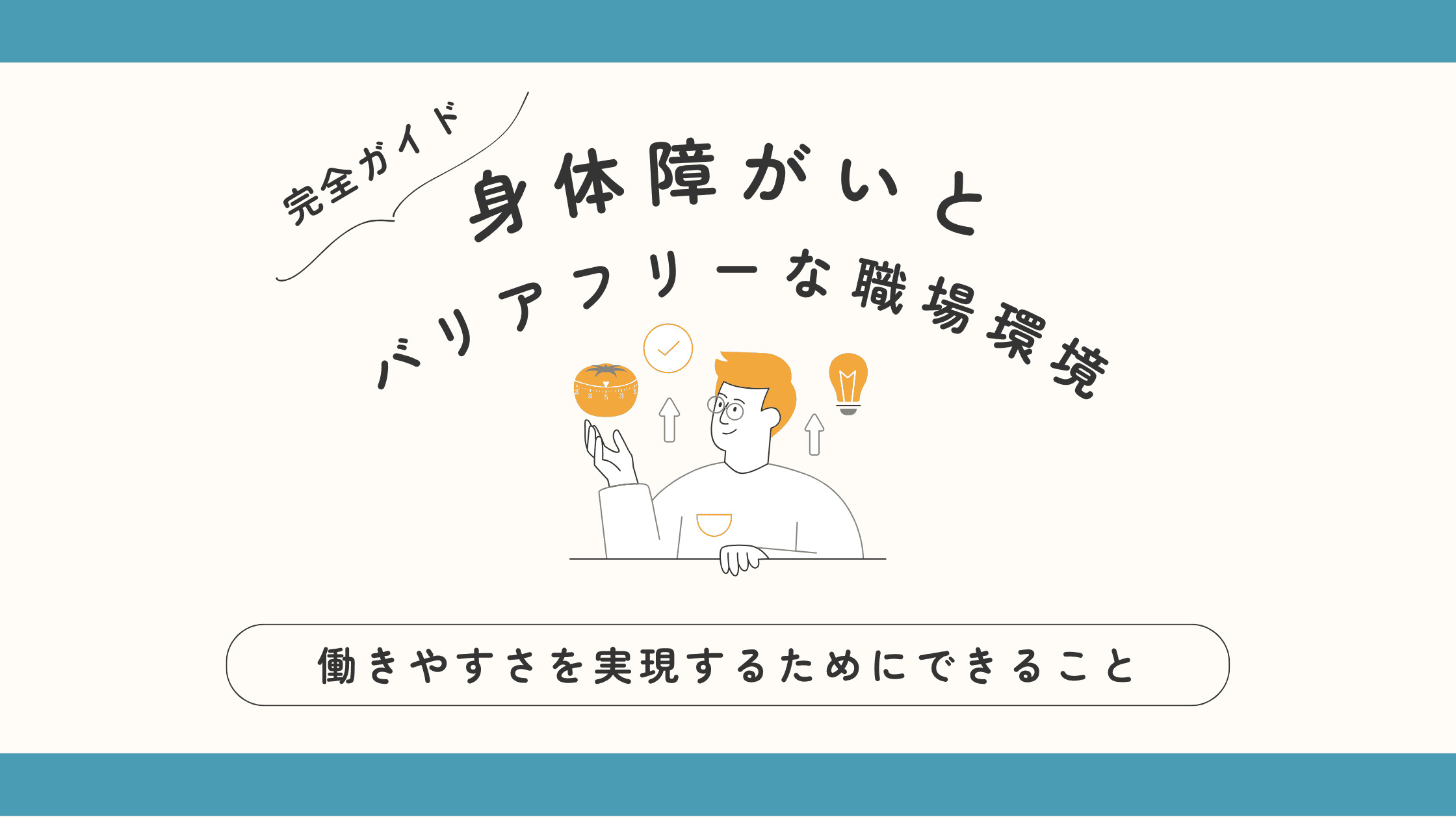
はじめに:“働けるけど働きにくい”現実と向き合う
身体障がいのある人が「働ける能力」を持っていても、「働きやすい環境」が整っていなければ、その力は十分に発揮されません。
近年、障がい者雇用率制度の影響もあり、身体障がいのある人が職場で働く機会は増えつつあります。
しかし実際には、移動・設備・コミュニケーションなど、多くの「バリア=障壁」が存在し、就労継続に苦労するケースも少なくありません。
この記事では、身体障がいを持つ方が働きやすい「バリアフリーな職場づくり」について、多角的に紹介していきます。
ご本人だけでなく、企業や人事担当者の方、同僚や支援者の方にも役立つ内容を意識しています。
1. 身体障がいのある人にとっての“バリア”とは何か

「物理的バリア」はまだまだ多い
身体障がいのある人にとって、最もわかりやすいのが「物理的なバリア」です。
たとえば、車いす利用者にとっては段差や狭い廊下、手の届かないスイッチなど。
義足を使用している人にとっても、滑りやすい床材や長い移動距離は負担になります。
一見、何も問題がないように見える建物でも、「バリアフリー設計」がなされていなければ、日常的な困難に直面します。
情報やコミュニケーションの壁も
「バリアフリー」というと建物や設備の改善を思い浮かべがちですが、それだけではありません。
たとえば聴覚障がいを持つ方にとっては、口頭での指示や電話対応が大きな負担になることがあります。
視覚障がいを伴う場合、文書の読み上げやデジタルデバイスのアクセシビリティも重要です。
職場における「情報のバリアフリー」もまた、非常に大切なポイントなのです。
心の壁、意識の壁が一番高いことも
物理的・情報的なバリアと同時に、見落とされがちなのが「意識のバリア」です。
「配慮しすぎて何も頼めない」「できないと思ってしまう」「腫れ物に触るような対応をされる」など、無意識の偏見や遠慮が、職場における分断や孤立を生み出してしまうこともあります。
2. バリアフリーな職場を実現するための基本視点

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れる
ユニバーサルデザインとは、「すべての人にとって使いやすい設計思想」のこと。
障がいの有無に関係なく使える仕組みを最初から導入しておくことで、後から特別な配慮を必要とせず、自然と多様性を受け入れる職場になります。
たとえば、昇降可能なデスクや段差のないフロア、電子機器の音声読み上げ機能などは、誰にとっても便利で働きやすい工夫です。
参照:練馬区公式ホームページ
対話による「個別配慮」がカギになる
身体障がいといっても、その症状や影響は人それぞれです。
同じく車いすを使っていても「移乗ができる人」「できない人」「長時間座位が困難な人」などさまざま。
だからこそ、本人との丁寧な対話を通して「何に困っているのか」「どこに配慮が必要なのか」を明確にしていくことが重要です。
マニュアル化ではなく、相手に応じた「個別の支援」が信頼関係を生み出します。
「合理的配慮」は法律で義務化されている
企業には、障がい者に対して「合理的配慮」を提供する義務があります(障害者差別解消法・障害者雇用促進法)。
これは「できる範囲で柔軟に対応する」ことを意味しており、過重な負担とならない範囲での職場調整や制度整備が求められています。
参照:内閣府
3. 働きやすさを支える職場環境の工夫

出入り口・トイレ・共有スペースの整備
建物全体のバリアフリー化は、最初の大きな一歩です。
自動ドアの設置、スロープの設置、多目的トイレの確保、エレベーターの点検など、基本的なインフラ整備は欠かせません。
また、会議室や休憩スペースも「動きやすい」「使いやすい」配置が重要です。物理的な移動のしやすさは、職場での自立を促します。
通勤やテレワークへの柔軟な対応
多くの身体障がいのある方にとって、通勤そのものが大きなハードルになることも。
そのため、時差出勤・通勤支援・送迎制度の導入や、自宅から働けるテレワーク環境の整備が重要です。
テレワークであれば、体調に応じた働き方や、移動ストレスのない働き方が可能になります。
職場内でのIT活用による支援
ITツールを活用することで、さまざまなサポートが可能になります。
たとえば、音声入力ソフト、拡大読書機能、チャットツールでの連絡、バーチャル会議など、身体的な制約をカバーできる手段は年々増えています。
「テクノロジーは障がいの壁を壊す鍵」と言われるように、働き方を変える大きな武器になるのです。
4. 実際の職場で見られる好事例と取り組み

大企業が導入するインクルーシブな制度
日本の大手企業では、身体障がいのある方の雇用を積極的に進めるところが増えています。
たとえば、富士通では「特例子会社」を設立し、障がいのある社員が専門性を活かしながら働ける環境を提供しています。
バリアフリー設計だけでなく、キャリアアップ支援にも力を入れており、他企業のモデルケースとなっています。
参照:富士通ハーモニー株式会社
中小企業でもできる柔軟な対応
中小企業でも、創意工夫をもって対応する事例があります。
あるITベンチャー企業では、身体障がいのある社員に対して、業務を完全リモート化し、週1回だけの通勤にすることで負担を大きく軽減しました。
コストをかけずとも、工夫と対話によって「働ける環境」は整えられるのです。
5. 身体障がいのある当事者が働く上で大切にしたい視点

遠慮しすぎず、自分のニーズを伝える勇気
職場での配慮は「伝えないと気づいてもらえない」ことが多くあります。
我慢して働き続けるより、「こうしてもらえると助かる」と率直に伝えることが、長く安心して働ける職場づくりにつながります。
もちろん、伝え方やタイミングには配慮が必要ですが、「遠慮しない権利」も大切にしていきたいポイントです。
自分に合う働き方・職種を見つけていく
「働きやすい職場」は、設備面だけでなく「仕事内容との相性」にも大きく左右されます。
たとえば、外回りよりもデスクワークの方が向いている、短時間勤務から始めたい、PC操作が得意…など、自分の強みや制限を整理することで、選択肢が広がっていきます。
就労移行支援事業所やハローワークの相談員などを頼りながら、少しずつ「自分に合った働き方」を探す姿勢も重要です。
6. 企業側ができること|本当の“共生”を目指して

研修・啓発による意識改革
どんなに制度や設備が整っていても、職場全体の「理解」がなければ共生は成り立ちません。
定期的な障がい理解の研修や、ロールプレイを通したコミュニケーション訓練などを取り入れることで、「違いを自然に受け入れる職場文化」を育てていくことが可能になります。
「できない」ではなく「どうすればできるか」を考える文化
企業にとって大切なのは、障がいを理由に選別することではなく、「どうすれば一緒に働けるか」を柔軟に考えることです。
バリアフリーは“設備”の話ではなく、“価値観”の話でもあります。多様な働き方を支える文化そのものが、企業の魅力や競争力にもつながっていくのです。
まとめ:誰もが活躍できる社会へ
身体障がいのある人が働きやすい職場づくりは、「障がい者のためだけの配慮」ではありません。
それは誰にとっても優しい職場であり、将来的に誰もが必要とする“働きやすさ”の実現でもあります。
「困っている人がいたら、まずは話を聞いてみる」
「制度や設備は完璧でなくても、改善の姿勢を持ち続ける」
そんな一歩一歩の積み重ねが、バリアフリーな社会をつくっていく力になるのです。
関連記事